2013年5月29日(水)
海外メディアも高評価の『サイコブレイク』――木村雅人プロデューサーに気になるアレコレを突っ込みまくる!!
アメリカ・ロサンゼルスで現地時間5月17日に開催されたベセスダ・ソフトワークス主催のメディアイベント“BFG”。そこで『サイコブレイク』のプロデューサーであるTango Gameworks・木村雅人氏にインタビューを行った。
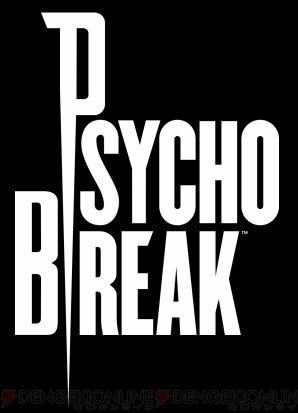
|
|---|
本作は、ベセスダ・ソフトワークス傘下のTango Gameworksが開発を手掛ける、次世代機対応の新規IP(※海外では『The Evil Within』としてリリース)。『バイオハザード』や『デビル メイ クライ』を生み出した三上真司氏がディレクターを務め、“純粋なサバイバルホラー”を目指して開発が進められている注目のタイトルだ。

|
|---|
| ▲主人公の刑事・セバスチャン。精神病院で発生した事件の謎を追ううちに、不可思議な出来事に巻き込まれ……。 |
この記事では、現地で披露されたデモプレイを見た感想と木村プロデューサーへのインタビュー内容をお届けしていく(取材・文/電撃PlayStation)。
■クライマックスで場内から歓声が! “ホラー”に対する日本と海外の文化の違い
今回のデモプレイで印象的だったのは、“ホラー”というジャンルに対する日本と海外の感受性の違いだ。
デモのクライマックスで、左右の壁からグラインダーのような無数の刃物が主人公を切り刻まんと迫ってくるシーンがある。このシーンの前から不可解な出来事が連続して起きるため、日本のメディアは思わず息を飲むところ。しかし、アメリカのメディアからは歓声(“笑い”といったほうが近いかもしれない)が起きていた。ホラーというジャンルの捉え方が世界で異なる中、本作で“怖さ”をどう演出していくのかは気になるところだ。
なお、公開されたデモは以前の記事で紹介したものとシーンは同じながら、次世代機の技術が使用されたアップグレード版という位置づけだ。
【木村雅人プロデューサーへのインタビュー】
デモプレイ後、木村プロデューサーへインタビューを行った。以前にうかがった内容よりも踏み込んだ話を聞くことができたので、ぜひ目を通してほしい。

|
|---|
| ▲Tango Gameworksプロデューサー・木村雅人氏。 |
■敵が学習して強くなる! AI制御にはかなり力が入っている
――海外のメディアの反応はいかがですか?
かなりポジティブに捉えていただいています。北米では“サバイバルホラー”というと少し弱まっているジャンルと捉えられることが多いんですけど、「この作品は楽しみにさせてもらってるよ」という声を多くいただいていますね。
――4月に初めてデモを見せていただいて1カ月が経ちましたが、この間に進化した部分はありますか?
4月に見ていただいたデモから内容的に大きく変わってはいませんが、今回見ていただいたものはネクストジェン(次世代機)のテクノロジーを使っているので、ビジュアル的に進化している部分はあります。もちろんこの1カ月間にゲームの開発は着々と進んでいますので、そこはまた別の機会にお見せできればと思っています。
――今回、ゲームエンジンに“id Tech5”を採用したのはどのような経緯からでしょうか?
“id Tech5”は自社グループのスタジオが持っている高性能エンジンです。何よりもディレクターの三上(※ゲームクリエイターの三上真司氏)のモノづくりの姿勢が、ライブ感あふれるというか、どんどん作り変えながらいいものを模索していくので、プランナーがトライ&エラーができるエンジンがよかった。“id Tech5”はツールがしっかりしていて、その部分がすごく魅力的ですね。元々はFPSを作るために開発されたエンジンなので、TPSに向かない部分もありますが、そこに関しては逆にカスタマイズしていこうと。
――その“カスタマイズ”と言うのは、例えばプレイヤーキャラクターのアニメーションなどですか?
そうですね。後、今回我々が作っているのはサバイバルホラーなので、例えば明るい場所と暗い場所では、明るいところをより明るく、暗いところはより暗くしたいという意図があります。そういう部分で、シェーダーにカスタマイズはかなり加えています。

|

|
|
|---|---|---|
――ゲームの流れは基本的に一本道ですか? それとも自由に動き回れるオープンワールド的な部分もあるのでしょうか?
ゲームの流れの中でスクリプト的に一本道で進んでいく部分と、AI制御などで自由に動き回れる場所は両方あります。「ここはこういう感情を起こさせたいから一本道にしてしまおう」というところは一本道になっていますし、探索であったり、それこそトラップを使って敵を引っかけるということを楽しんでほしいところはAI制御になっています。
AI制御に関してはかなり力を入れていて、最初はチュートリアル的だった敵の動きも、先へ進むことで今までやってこなかった連携をやってきたりします。トラップを最初は使ってこなかったのに、トラップを解除したり使ってきたりするようになりますね。
――敵キャラクターの個々の動きに加えて、例えばノーミスで進んでいくと敵が強くなっていくなど、動的な難易度調整は入っていますか?
そういった調整に関してはまだ確定しているわけではありませんが、入れていきたいという話はしています。
(C)2013 ZeniMax Media Inc. Developed in association with Tango Gameworks. PsychoBreak, Tango, Tango Gameworks, the TA logo, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.
データ