2017年1月24日(火)
『龍が如く6』横山昌義さんへのロングインタビュー。物語の描き方や収録秘話、ユーザーの評判について語る
セガゲームスから発売中のPS4用ソフト『龍が如く6 命の詩。』を手がけた、横山昌義さんへのインタビューを掲載する。

|
|---|
本作は、『龍が如く』シリーズ最新作にして、桐生一馬伝説の最終章。東京・神室町や広島・尾道仁涯町を舞台に、桐生と澤村遥をめぐる物語が描かれる。

|
|---|
横山さんは『龍が如く6』のチーフプロデューサーにして、脚本・演出も手がけている。インタビュー中では発売後の反響から始まり、台本の作成方法や収録時に印象的だったこと、キャラクターの掘り下げ方、さらにはタイアップの裏話などをお聞きしている。ゲームをプレイした人、興味を持っている人はぜひご覧いただきたい。
賛否あるのはうれしいこと!? 発売後の反響に迫る
――発売された後の反響はいかがですか?
大きく2つの意見がありますね。ひとつは素直に「楽しい!」という意見と、もうひとつは遥をめぐる展開があわなかったという意見です。どちらも過去最大に強い声で、一時は検索ワードのトレンド上位に入る勢いでした。
当初から意見はわかれるだろうと予測していましたし、もっと言えばわかれていいと思っていました。それよりも強い反応が出たことが素直にうれしかったですね。
――というのは?
個人的にですが、エンターテインメントは一定の議論がある作品のほうが強く心に残るのではないかと思っています。「まあよかった」で終わってしまうのではなく、「最高だった!」「最低でしょ」など両極な意見がある作品のほうがユーザー間で議論が起きて、コミュニティが活発になります。
さらにユーザーの皆さんが自分の主義主張を第三者に伝えるために、より詳しく作品を振り返って「どうしてそう思ったのか?」を考えてくれるのではないかと。「なんか嫌だ」「なんとなくいい」という漠然な感想を持たれるより、作り手としては作品と真剣に向き合ってもらえた分、幸せなことだと感じています。
これまでのシリーズだと例えばストーリー的には『龍が如く0 誓いの場所』は賛が多く、『龍が如く5 夢、叶えし者』は賛否がありました。ただ、実際のところ『5』のほうが圧倒的に長い期間話題の中心にあり、多くのユーザーに遊んでいただいたというデータもあります。
我々としましてはゲームを作っている以上、売上もそうですが、強くユーザーの方の心に刻まれる商品づくりを目指していますので、長い時間触れ合ってもらうことは何よりの喜びでもあります。
――では本作『6』での一部ユーザーからの否については、そこまで気にされていなかったのですね。

|
|---|
人によってはっきり評価がわかれているのはすごく『龍が如く』らしいです。実はそれこそが11年前に『龍が如く』を発売した時の目標でもありました。
『龍1』の発売前に「10点満点評価でオール8点はいらない。4点や5点がいてもいいから、10点をつけてくれる人を多く作りたい」というようなことをよく話していました。それから時間は経ちおかげさまで国内のビッグタイトルのひとつに挙げてもらえるシリーズに成長しましたが、今でも“尖った作品作り”ということは意識しています。それが今作では如実に反響となって表れたので、私としてはそれがうれしいです。
今作は、毎回イベントに来てくださるような熱心な方たちの中でも、歴代ナンバーワンと言ってくださる人も多くいらっしゃいますし、逆に単純に真島や大吾の登場が少ないから好きじゃないという話もうかがいます。ですが皆さん実際に最後までプレイしてくださって感想をくださるので感謝の気持ちしかありませんね。
単独主人公と複数主人公の大きな違いとは?
――物語についてお聞きします。今回は桐生一馬1人の展開を追うことになりますが、以前のストーリーの書き方に近かったのでしょうか?

|
|---|
そうですね、当時を思い出しました。多人数を描くことに最近は慣れてきていたのですが、1人を中心に描くのと、多人数の主人公を描くのでは描き方がまったく違います。
多人数の場合、新しく出てきたキャラのバックボーンを描くのに時間を割きます。メインストーリーの部分だけを見ると短くなってしまうので、全体を深く描くことはやりにくい。それは『龍が如く4 伝説を継ぐもの』の時から感じていました。
――具体的にはどういうことを感じましたか?
新たな登場キャラが出てくる場合、その人物がなぜそこにいて、何を思っているのか、どういう魅力があるのかを描く必要があります。
『4』で言えば、秋山編に予定より分量を使ってしまい、冴島編が終わった段階で想定尺の半分以上を消化してしまいました。あわてて谷村編でバランスを調整し、桐生編も整えて、最終章にもっていく流れにしました。
一方で主人公が1人の場合、周囲のキャラや敵キャラに分量を割り当てることができます。『龍が如く2』の郷田龍司や『龍が如く3』の峯義孝のような魅力的で輝く敵キャラを作れたのはそのためだと思います。
――『0』は2人の主人公ということで、『4』や『5』よりも密に描けたのでしょうか?
人数も関係しますが、桐生も真島も詳しい背景を描く必要がないので、2人の周辺で起こる事件や、新たなキャラクターを描きやすかったのが大きいです。本作『6』は久々に1人の主人公なので、新たな登場人物を桐生目線でしっかり描くことができたと思います。
――台本制作はどれくらい時間がかかるのでしょう?

|
|---|
『0』が終わった時から着手していますので、半年以上かけています。短いように感じるかも知れませんが、今までの作品の倍近く時間をかけています。今回は書き終えた後もかなりの時間をかけて書き直していますので、トータルで費やした時間は1年以上かもしれません。
また書き出しまでに時間がかかったのも今作の特徴です。やはり話の主軸が“遥の子”という大きな題材でしたので、名越やチームメンバーで相談して、話を詰めるまでには時間が必要でした。
――遥が子ども生んで、桐生が父親を探すことはその時点で決めたのでしょうか?
それは一番最初の企画書を作成する段階で決めています。まず“桐生一馬と澤村遥の子の父親探しの旅”というストーリーコンセプトを名越に出しました。一部のファンの方にはショッキングなことかもしれませんが、私としては、桐生一馬という人間が生きていくうえで絶対に向き合わなければならない“局面”だと考えていました。
これまで暴力という力で局面突破を図ってきた男が直面する“答えのない旅”を描きたいと。一般的な家族愛に恵まれなかった男が、“新たな命”という人生で経験するであろう大トピックにどう向き合っていくのか見てみたいと思いました。
――知った時は驚きましたが、普通に起こることではありますね。

|
|---|
ユーザーの方が遥の子という存在にショックを受けてもらえるというのは、それだけ思い入れを持ってもらっていることですので、我々としては幸せなことです。10年以上作ってきたからこその結果なので、そこを描きたいというところから動き始まりました。
このエピソード自体、キャラクターが1年ごとにきちんと年齢を重ねていく『龍が如く』シリーズだからこそできることですから、そこはきっちり描いていきたいと思い決断しました。
また、今作は桐生一馬という男を描ききることが目標でしたので、『龍5』まででやりきった感のある桐生が再度“強烈な動機”を持って動けるようにする必要もありました。
――“強烈な動機”ですか?
『龍1』から『龍5』までの桐生一馬という男の経験をすべて並べてみると、もう動揺したり弱気になったりと心が揺れるような出来事ってそうそうないと思うんです。
例えば“遥が人質になっている”とかですと、そりゃ必死に助けに行くと思いますが、すでに経験している出来事でしかありません。敵にしても同じです。海外のすさまじい組織が襲い掛かって来ても、躊躇(ちゅうちょ)なく立ち向かうでしょう。
桐生一馬という人間を描く以上、彼の葛藤や苦悩、そして決断を描きたい。ならば今の桐生が未経験でもっとも悩むことは“新たな命との触れ合い”ではないかと。そしてその対象が、彼の唯一の人生の相棒ともいうべき澤村遥の子であるとしたら、これまでに見たことがないような桐生一馬の“今”が描けると思ったんですね。
――それで決めたのが、“遥の子どもと、父親を探す旅”だったんですね。

|
|---|
桐生と遥の関係は、親子なのか、恋人なのか、別の何かなのか……僕にはそういう人がいないので完全にはわかりません。でも、親子でも恋人でもないと思うんですね。
ただ、遥が生んだ子どもであれば、それは桐生にとっても特別な存在であるのは間違いない。そのために行動を起こすのは腑に落ちると考えました。“遥の子ども”という未知との遭遇を描くために用意したストーリーとも言えます。
――そうだったんですね。
豪華な俳優も話題になりましたが、キャスト陣を出すために物語を用意したわけではありません。シナリオができて、キャラの役柄ができあがっていく中で、役にマッチする人にお願いにしました。極道の抗争が物語にからんでくるのは、彼らの知り合いに極道が多いからですね。
――他に物語を作る際に意識したことは?
大阪の城が割れるインパクトを超えるような何かをしたいと思っていました。個人的にはゲームでしかできないようなことを、大事にしています。“動かせる映画”というコンセプトは遊びとしてありだと思うのですが、単に「映画みたいですね」と言われるようなものではない、ゲームだからこそできることをしたいと思っています。
我々もよく決まった展開をしてしまうんですね。ゲームショップ、Webサイト、ゲーム媒体、テレビCMという枠組みの中で毎年同じようなものを露出してしまう。そこを崩したくてさまざまな仕掛けができるよう頑張っています。
何かを突き崩していかないと本当の意味で“一歩外に出ていかない”、ゲームのよさが伝わらない、理解されないと思います。ゲームをよく知らない人や、やらない人に振り向いてもらうための施策は、プロジェクトの初期段階からつねに考えていることですね。それが時にはストーリーやキャスティング、新システムなどのアイデアにも繋がっていきます。
桐生として台本に向かい合った黒田さん
――物語を読まれた黒田さんの反応はいかがでしたか?

|
|---|
収録時に“桐生一馬の最終章”とは伝えていなかったので、後から聞いて驚かれていたようです。黒田さんは途中まで「もしかしたら、ハルトは遥の子どもではないかもしれない」と感じながら演じていたそうです。
収録タイミングにあわせて章ごとに台本が届くため、収録が終わると「横山さん、次の次の章くらいで父親わかりますか?」と聞いてくるのですが、やはり聞きたくない心境もあったようで、結局台本で読んでいました。最後まで読まれて「よかった。納得できた」と話されていました。
全体的に桐生に近い反応をしていたため、感情移入はすごかったですね。
――他の方はどのような印象でしたか?
真島吾朗役の宇垣さんはとにかく驚いていました。ブースに入って2分で出てきましたからね(笑)。「すごいね、龍チームはやるって決めたら、こういうことやれちゃうんだもんね。」って。
あとは、藤原さんやドロンズの石本さんも収録を楽しまれていましたね。ただ宮迫さんだけは尾道弁が本当に大変だったようで、ヘトヘトでした。
――完成発表会で「大変だった」とコメントされていたのは本当だったんですね。
あれは偽りなく本音でしょうね。すべてのセリフで尾道弁の先生から指導されるので、収録終盤はかなり疲れていました。
――逆に、収録がスムーズだった方は?

|
|---|
小栗さんはこれまでのシリーズをプレイされているからか、桐生と染谷を対比させて成り立つような演技をするので、すごかったですね。どう見たって桐生のほうが強そうで、格も上。そのうえで対等に渡り合えるような演技をするのは難しいのですが、しっかりと演じてられていたので驚きました。
実は小栗さんは、アニメ『RAINBOW-二舎六房の七人-』でレギュラー出演されていました。黒田さんと同じ現場だったため、黒田さんの演技も想像したうえで、負けない演技をされていたと思います。実際、まったくと言っていいほど台本に対しての質問はありませんでしたし、リテイクもほぼありませんでした。
――森田順平さんの反応も印象的だったとお聞きしたのですが……。

|
|---|
森田さんには、『5』で名古屋ワイバーンズの冨士田監督をやられた際に初めてお仕事させてもらいました。監督は名古屋編にしか出ていないので、第4部の台本しか渡していなかったのですが、出ている役者に頼んで他の章の台本をかき集めて全章読破してくださったそうです。そのうえで物語を気に入ってくださいました。
――それはすごいエピソードですね。
これまでのシリーズも遊んだり、読んだりされていたようです。
本作でもビッグ・ロウの収録が終わった際に、興奮気味に「読み物として本当におもしろい!」と言っていただいたのはうれしかったですね。俳優としても多くの物語にアプローチされている森田さんにそう言われると、個人的にホッとできるんです。
セリフとキャストのマッチングについて明かす
――広瀬徹のセリフの節々から、ビートたけしさんが監督・出演されている作品の雰囲気を感じられたのですが、セリフを考えるうえで、キャストに影響されることはありましたか?

|
|---|
それはありますね。物語の流れが決まり、台本、セリフを作っていく時に、キャストを想像して当て書きすることもあります。
たけしさんの場合、台本ができる前に出演が決まりました。広瀬が登場するのは4章なので、決まった時点からたけしさんが読んで違和感のないようなセリフに仕上げていきました。
――物語のうえでもかなりのキーマンでしたね。
普段は飄々(ひょうひょう)としながらも、広瀬一家の総長であり、物語のキーマン……当然、キャストを見た人もキーマンになると思われますよね? たけしさんをキャスティングしておいて本当にチョイ役というのはできませんね。
――遊んでいて、序盤は全体的に小ツブなキャラが多いのかと思っていました。染谷であれば、菅井に使われているガッカリするようなキャラなんじゃないかと。

|
|---|
ああ、わかります(笑)。最初の「染谷一家総長の染谷です」というセリフは、一番軽い感じで演技してもらっています。その後、「あれ? あれ?」という感じで彼の内面がドンドン描かれていく。そしていつの間にか好きになっていく、というのを狙ったものです。
――見事に策にハマりましたね(笑)。
桐生にとって染谷は敵であり尊敬できる存在にしたかった。実際、劇中桐生に義理を通すために、尾道まであいさつに来るシーンなどでは、桐生の染谷に対する態度が明らかに変わっています。まあそりゃ新幹線でも4~5時間かけて会いに来たんですもんね(笑)。
――そうですね(笑)。さらにすぐに帰ってしまいますし。
あと、染谷は菅井のことを歯牙にもかけていないのが個人的には気に入っています。いろいろなことをわかっていながらもあの振る舞いをできる染谷……僕の中では、東城会で最後のヒーローという位置づけで描きました。
――南雲にも驚きました。章を追うごとに好きになっていきました。

|
|---|
先ほどの話と関係するのですが、1人の主人公を描くからこそ、周りのキャラを深堀できます。広瀬も後半どんどん存在が増していき、物語が動いていくので、プレイしている人ものめり込まれていったのではないかと。広瀬一家と言えば、個人的には松永や田頭も外せませんね。
――2人とも地味に頼りになるキャラでした。

|
|---|
直情的な宇佐美勇太を田頭がフォローする……田頭は頭がいいし、頼りになるので、執筆するうえで気持ち的にも頼れました。他のメンバーの至らないところをフォローしていて、あの一家を影から支えているキャラ。お気に入りです。
――広瀬一家には広島出身の人をアテンドされたのでしょうか?
広島弁や尾道弁をしゃべれる人を探したのですが、あまりいないので大変でした。そんな中でいい方にお願いできたと感じています。
田頭役の細谷佳正さんは声を知っていたため、確実に合うと思っていました。松永孝明役のドロンズ石本さんは、ギリギリまで別の方が入れた広島弁のテストボイスが入っていたんですね。
――テストボイスというのは?

|
|---|
映像の編集で口パクを作る際に使ったり、役のイメージ作りのためにキャストに渡したりするボイスです。
実は最後に収録したのがドロンズ石本さんでした。石本さんのボイスがテストボイスの方のイメージと近かったので違和感がなく、作業はスムーズに行きました。
――中村悠一さんが演じられたハン・ジュンギは、これまでにいないようなキャラで驚きました。

|
|---|
ワザとらしくキザなキャラでありつつ、カッコよさがしっかりある……ハン・ジュンギはいいキャラになりました。中村さんは『龍が如く』シリーズをかなりプレイしてくださっていると聞いていたので、いいアプローチで来てくれると思っていました。当然ですが世界観については説明なくアフレコに臨まれましたね。
ただ、ハン・ジュンギは『龍が如く』シリーズらしくない過剰な演技をするキャラなので塩梅は確認されていました。ちょっと面を食らっていたと思いますが、「わざとらしくやってほしい」とお願いしました。
――全体を通して、キャラがこれまで以上にさまざまな表情を見せると感じました。
PS4でドラゴンエンジンになったことで、キャラのボーン数……顔の動かせる場所がかなり増えています。これまでも動いていたのですが、ちょっとした肌のゆがみまで拾えるようになりました。
顔の演技は、顔のモーションキャプチャーチームが担当しているのですが、細部までデータをとれるようになったので、しっかり再現されています。それによって、無言の演技ができるようになりました。
――会話シーンがフルボイスになったうえに、カメラが動くようになっています。これまでと比べて作業量的にはどれくらい増えているのでしょうか?
しっかり計算したわけではありませんが……同じ分量を作るとしても数倍の手間はかかると思います。前作と同じようなカメラアングル、カメラワークで作ることはできます。でもこれだけリアルなキャラでそれだと不自然なんですね。
それを不自然でないように見せていくように、すべて手作業で対応しています。これにより、全体のクオリティが上がります。
ウィンドウショッピングを楽しめる街づくりを目指した
――神室町は新たに作り直されています。行ける範囲は狭くなっているのですが、あまりそれを感じさせないどころか、没入できました。
ボリュームの感じ方については、『龍が如く 維新!』の時からチームが意識しているところです。話の尺や遊びにもよるのですが、ステージの面積を広げるのではなく、ちょうど気持ちよく回れる“狭さとテンポ”があるだろうと。
『維新』に洛外という場所があったのですが、そこまで広くないし、密度もないんですね。ただ、移動に疲れず、探索も楽しいというちょうどいい遊びを提供できました。
――広すぎることがいいわけではないと。
遭遇するミッションの数やプレイスポット、高低差などさまざまな要素が相まってなのですが、だだっ広いよりも適度な狭さがあるほうが没入感を高められる考えてます。
『5』では5大都市があるので、福岡であれば中洲の川の景色、札幌であればニッカの看板と時計という象徴するスポットを再現していくことで街っぽさを表現しようとトライしました。ただそれだけでゲームの楽しさが担保されるわけではないんですね。
ビルに入れない、裏路地もないとなると、街が変わっても景色が変わるだけ。そうなると、ただ走っているマラソンのようなものでおもしろくない。そうではなく、街を歩き店に入り、ウィンドウショッピングさせるのがこのシリーズの魅力です。
――確かに、ただ走っているだけだと見た目が変わっても飽きてきますね。

|
|---|
42.195キロをひたすら走らせるのではなく、例えば銀座の中央通りだけを作って、すべてのビルに入って遊べたほうがおもしろい。そういう視点から作っています。そうやって掘り下げる考えで開発していった結果、“シリーズ史上最大”といったような数にこだわる必要がなくなりました。
――なるほど。
以前の公園前通りであれば、神室町ヒルズに行く時に使いますが、ただの道としてあるだけ。それであれば、別の場所に入れるビルを増やしたほうがいいという判断です。それによって、密度を感じられるような作りにシフトしていきました。
もちろん、まだまだやれることはあると思っています。今回の遊びをよりもっと深くするパターンもあるわけです。
――ミニゲームの種類が絞られたのにはそういう理由もあったのですね。
ミニゲームについては2つ理由があります。実際に街で遊ばれなくなったプレイスポットを実装する必要がなかったのがひとつ。次にPS4にシフトするにあたって、一度過去資産の無意味な流用をやめ、あればOKというような幕の内弁当的なプレイスポットの有り方を変えてみようと。
その考えに至ったのは、繁華街ではない尾道という街を舞台にしたことが大きいと思います。
――確かに広島・尾道は、これまでのシリーズにはない街並みになっていると感じました。

|
|---|
シリーズに登場するこれまでの街は繁華街と言える街ばかりでした。もちろん情景や街の住人たちの言葉遣いや文化など、神室町にはない魅力を掘り下げてきましたが、プレイスポットとなると正直神室町と共有するものが多く、全体的な遊び味としては差別化を図ることができませんでした。
尾道を舞台とするにあたって、当初は“カラオケ”や“ゲームセンター”など一般的な繁華街に当然あるはずのものがなく、どうにかしてカタチを変えて流用できないかを考えていたのですが、そこで頭を180度切り替え、この街でしか表現できない遊びを新たに作ることにしたんです。その結果が“スナック”であり“素潜り”であったりします。
――お寺などのプレイスポットも含めて尾道に実際行ったかのような感覚がありました。

|
|---|
ゲームなので、現実の街とは少し異なる場所もありますし、縮尺も異なります。でもイメージはかなり再現できていると思います。
尾道には開発中は何度も行きましたが、先日、ゲームを作り終えてから改めて訪れると街並みが以前とは違って見えました。ゲームでの体験が重なってリアルな街の探索が楽しくなるんですね。ぜひプレイした方には実際尾道に行っていただきたいです。
――フォトコンテストで“旅行カード”をプレゼントしているのも、そういう気持ちからでしょうか?

|

|
|
|---|---|---|
そうです。ゲームを遊んで、尾道に行って楽しんでもらう。街は広くないので、1日あれば回れます。ご飯がおいしく、風がないうえに湿度があるため、温かくて過ごしやすいです。リアルとゲームの両方で“街”を楽しんでいただくのは、『龍が如く』の1つの醍醐味ですので、ぜひ行っていただきたいです。
――ゲーム中でいろいろなことが起きた街なので、歩いているといろいろなことを思い出しそうですね。

|

|
|
|---|---|---|
尾道では市役所の観光課の方が協力してくださったので、いろいろな仕組みを用意しました。千光寺やロープウェイはほとんどそのままゲームに使っています。なるべくリアルに感じられるほうがおもしろさはアップするし、忘れられなくなるからです。訪れたという経験こみで忘れられない作品になるかと。
――広島の街を再現するのは大変でしたか?
デザイナーはテンション高く、楽しみながら開発していました。ただ、これまでシリーズを通じてコンクリートのビルばかりを作っていたスタッフが、木造建築ばかりの街を作ることになったわけですから、苦労もあったようです。
――起伏のある街を作るのは大変だというイメージですが、いかがでしょうか?

|
|---|
起伏も大変ですが、尾道は高いところから街全体を見渡せるのもポイントになります。高台から街を見下ろせるというのは、CG的にごまかしがききにくいので、本当はあまりやりたくないことなんですね。
ただ、想定以上に気合を感じられるものが上がってきたので、やはり楽しかったんだと思います。
――何人くらいが取材に行かれたのですか?
背景制作の取材としては尾道担当のスタッフとアートディレクター、5~6人だと思います。写真を大量に撮ってきて作っていました。
取材という意味では『5』の5大都市のほうが大変でしたけど、今回は街の深い部分まで作りこんでいく必要があったので取材のやり方も深くなっていると思います。街を実際に歩いて感じる閉塞感や密度感といった感覚をつかんで、それをグラフィックで表現していくことができる優秀なチームだと思います。
――巌見造船の設定やキャラが物語に絡んできましたが、こちらはどういう流れだったのでしょうか?

|
|---|
“尾道”は造船業が盛んな街です。切っても切り離せない要素だと考えました。今回は造船のエピソードありきというよりも、舞台となった土地の歴史や文化を縁にストーリーのイメージを膨らませていった結果、物語に深くかかわることとなりました。
『龍が如く』シリーズと横山さんのかかわりについて
――シリーズは長く展開されていますが、初期からはどれくらいのメンバーがいるのでしょうか?
シリーズ作のすべてにかかわっているメンバーは4、5人程度で、プロジェクト初期からいるメンバーは1/4くらいだと思います。若いスタッフだとセガに入社してから、ずっと『龍が如く』シリーズを作っているということも多いですね。
――過去のシリーズで印象的だったタイトルは何ですか?
個人的な背景とリンクするので、作品だけでとらえられるものでもないのですが……『4』ですね。『4』は作った時に、このシリーズはまだ続けられると思わせてくれた作品です。シリーズの大きな分岐点だったと思います。それまで横に広げる発想でシリーズを続けてきた中で、街は同じで主人公を増やすという新たな展開に挑み、成功できたと思っています。
『4』はいろいろ悩みがある中で作りました。さらに、ずっと出したかった秋山というキャラも仕上げられました。あれでうまく行かなければシリーズは終わっていたと思います。
――個人的にも『4』は好きな作品ですね。

|
|---|
ゲームという感動体験でもっとも優れていると思っているのは『5』です。あそこまでバラエティに富んだ遊びを詰め込みながら、1つの作品としてまとめられたのは奇跡という他ありません。
雪山で遭難した後にアイドル活動をしている……アイドル文化やファッション、グルメ。思想や信仰を越え、世界中の楽しいモノすべてに手に入る“日本”という国を、もっとも詰め込んだ作品になっていると思います。
――さまざまなエンターテインメントが詰まっていると。
『5』で初めてプロデュースを担当しましたが、発売日に当時の役員からお祝いの電話をもらい「最初でこれやると後々キツイぞぉ~」と言われて、「確かに」と頭が痛くなりました。
ただ毎作そうなのですが、今考えてるすべてのネタを出しきっておかないと、次の目標もみつからないので、次のことはまた明日考えようと(笑)。
――シナリオを手がけながらプロデューサーをやると、自分が書いたものをジャッジする必要があります。簡単ではないと思うのですが、いかがですか?
まさに、さまざまなジャッジを自分で行うことになります。予算などはまさにそれです。
『4』までで言えば立場的には脚本演出なので、自分の描いたシーンはすべて作りたいという考えを持っていました。秋山でいいセリフが思いついたら全部しゃべらせたい。でもイベントシーンの尺が足りない。当時はよく名越やプロデューサーに直談判して怒られながら追加予算をもらったりしてましたね(笑)。
一方『5』では自分が“人・モノ・金”を握っています。そうなると今度は冷静に『5』という商品を見つめ直す自分がいるんですね。プロデューサーという立場になって初めて客観的に冷静に自分のシナリオを見られるようになったと思います。
――具体的にはどういう点でしょうか?

|
|---|
『4』まではいちシナリオライター、いち演出家としてとにかくいいシーンを作りたい。PVであってもネタバレを出したくないので、後半のシーンは使いたがらないなどあくまで「シナリオをどう届けるか?」を中心に考えます。
でもプロデューサーになってからは、キャラやセリフの好き嫌いではなく、PVの時にどのセリフがあったほうが商品を正しく伝えられるのかという視点でジャッジするように変わっていきました。
正直『5』の時はやりたい自分と削りたい自分がせめぎ合って、葛藤もありました(笑)。でも今は迷わなくなりましたね。自分がシナリオに費やした時間もケチケチせずにバッサリ捨てられるといった感じですかね。「あー、もったいねー、まぁ、しゃーねーか!」というノリで(笑)。もちろん大変ではありますが、兼任してよかったと思います。
――10年以上開発しているからこそ、変化するものも出てくるわけですね。
『龍が如く』は、私に「ゲームを作る仕事というのは、決して狭いものじゃない」ということを教えてくれたタイトルです。知名度がなかった11年前と今では、仕掛けるプロモーションの内容も規模も、まったく別のものになっています。自ずと私自身も“商品”というものに対しての考え方が変わったと思います。
――タイアップでも、先方の反応がまったく変わったとか。
それもシリーズの歴史ですよね。これについてもいろいろな考えがあって、開発当初に厳しい対応をされているからこそ、タイアップを相談していただいた時に冷静に吟味できるんです。当時、いろいろなタイアップやキャンペーンを実施できていたら、ここまで頑張れていないような気もします。
――他に変わったことは?
キャスティングにしてもそうで、出演したいという声を多数いただけるようになりました。1作目は話を聞いてもらえませんでしたから。
タイアップでは今を映すものを取り入れたい!
――本作でもさまざまなタイアップが行われていますが、印象的なものは?
ライザップです!
――即答されましたね。
実はライザップさんとの取り組みは流行に乗ったというよりも、ゲーム性の面から実現したかった企画です。現代の日本、2016年という時代を切り取ったいいタイアップだったと思います。
――“時代を切り取る”ですか?
かつては作品に時代性を入れれば入れるほど「不変的な文化にならない」と考えていた時もありました。時代性がない作品のほうが文化として残っていくと考えていたんですね。
ただその考えは徐々に変わり、『龍が如く 極』を作った際に、『龍が如く』は「時代性があることにこそ価値がある」と再認識できたんです。
――というのは?

|
|---|
| ▲『龍が如く 極』のイベントシーン。 |
『極』開発時に改めて『1』を遊んだところ、自分が思っていた以上に当時の街が古く、2005年の神室町が楽しかったんですね。伊達さんが「今じゃガキでも持っているんだぜ」と桐生に渡す携帯電話が、現代では考えられないほど大きいことに衝撃を覚えたり。
――アハハハハハ。
10年も経てば人も街も変わります。10年経って、ちょっとした違いが地味におもしろいこともある。今をきちんと描くと、その先にプレイしても楽しいので、今を描ききるのは大事だと思うようになりました。
――なるほど。

|
|---|
ライザップさんの場合で言うと、2016年の今を感じられるうえに、桐生というすでに最強の男を“限界を越えて”強化するシステムにも使えると考えて、タイアップ先でももっとも早いタイミングでお話しさせていただきました。
――確かにこれまで以上にゲームに絡んでいる印象でした。
今でも街の看板でロゴを借りることはあります。もちろんリアルな街づくりには必要な要素ですが、出ているだけだと、通りすがりのオブジェになります。ゲームに絡んでいるからこそ体験として印象に残るので、しっかりできてよかったと思います。
時代を切り取るという意味では、逆にキャバクラなどは、今では『1』の時のような強い魅力を感じることができなくなっていて、頭を悩ませています。
――え、そうなんですか?
2005年当時のキャバクラって“最近キテる”スポットだったんですよね。すでに都内でははやりつつあって、ハマっている人がいるものの、世間的には存在こそ知っていてもまだ行ったことがないという“未開の地”としての魅力がありました。
そこから徐々にキャバクラというものが地方都市にも広がったり、一部のキャバ嬢が有名になったり、遊び方が浸透していきました。
となると、『1』とその後の作品では、ゲームとしてのキャバクラの遊び方を変える必要があるんですね。最初はドキドキ感もあり会話だけでおもしろい。でもリアルにキャバクラというものが分かると、現実にはない別のドキドキが欲しくってきます。

|
|---|
そうなるとだんだんゲーム的なキャバクラを作るようになり、いつのまにか“リアルじゃない”ものができあがる、と。それでもキャバクラというスポットが夜の歓楽街にある限り、我々はプレイスポットとして描き続ける必要があるんです。ここ数年、頭を悩ませながら作り続けています(笑)。
一方、ライザップは『1』のころのキャバクラに近いドキドキ感もあると思うんです。
――確かにライザップを知っていますが、行ったことはありませんね。
あれだけコマーシャルをしているうえに、知り合いの知り合いくらいの距離感の人が「行って痩せたらしい」という話は聞くかと。でも実際に行ったことがないのがライザップ。久々にゲームでアクセスできるというだけでもワクワクするプレイスポットになると思ったので、なんとか実現できるよう交渉も気合が入りました。
――先方の評判はいかがでしたか?

|
|---|
非常によかったです。正直な話、桐生の背中には龍が昇ってますので、演出は一部NGになるかと思ったのですがOKでした。
――他にもさまざまなものがゲーム中に登場しますね。
ゲーム内のキャラが身につけるアイテムですと、祭汪会メンバーが着用するアクセサリーをIVXさま、秋山と染谷が着用する時計をTendenceさま、広瀬一家が身につける隠密服などをアルファインダストリーさまとやらせていただいています。
キャラが実際にあるアイテムを身につけるとすごくリアルになるだけでなく、親近感が増すんですよ。グラフィック表現が向上したので、見た目も映えるので助かりますね。
――先ほども話に出た街をシームレスにすることは、PS4ということで実施したのでしょうか?
街のシームレス化は以前からやりたいと思っていました。データさえ軽ければPS3でもできることですし、それ自体特別なことではありません。ただ、PS4の描写性能を生かしたうえで、読み込みをなくせるかがポイントになります。そうなると、ハードを研究して仕組みを用意しないと処理落ちしてしまいます。
『維新』や『0』、『極』などPS3とPS4という2ハードで開発する場合、PS3を基準にしたエンジンになるため、PS4の性能を持て余していました。本作でドラゴンエンジンにした瞬間から、どこまで盛り込み、処理をどうしていくかのがポイントになりました。
――読み込みがないからこそ、街遊びを満喫できて楽しかったです。
本作では得られる経験値の項目がわかれているので、「赤身ばかりだとパワーに偏るので、別のを食べようかな」というように食材を選ぶようになります。ライザップをしっかりやった人であれば、クイズで楽しみながらいろいろな店のメニューを覚えたと思いますね。
――考えましたね。
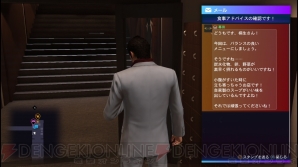
|
|---|
“丸ごとバリバリ食べられるやつ”というアドバイスに対して「刺身ではダメで……焼き魚かな? それはどこで食べれるのかな?」と考えたかと。
遊びとして好きな人がいることは知っているのですが、達成やトロフィーのためにとりあえずメニューを食べるというのは、個人的には好きではありません。街で考えて食べてほしいんですよ。
実際にゲームをしながら食事のことを考えてイメージを膨らませると、本当に腹が減って同じメニューを食べたくなります。開発中に「“いきなり!ステーキ”を食べたい」と思い、蒲田店に行って食べて、まだ仕事に戻るというのが何度もありました。
――確かに食べたくなります。今回食べた際にチェックが付かなくなったにはそういう理由があったんですね。
前々からゲーム中の飲食店というものの存在を、“達成目録”のリスト埋めのために行く場所から、ユーザーが積極的に行きたくなる場所に変えたいという思いがありました。
――今回の経験値の仕組みを含め、食べることで経験が入ることは最初から考えられていたのですか?

|
|---|
食べることが経験値に繋がることに重きをおいてほしいと、開発初期からお願いしていました。先ほども話題に出てきた「街を遊ぶということを忘れないでほしい」と何回も伝えました。
実は『極』の先行体験版から『6』で大きく変えたところがあります。先行体験版ではバトル時にできることは殴る、ぶつけるだけで、手にはコーンくらいしか持てなかったんです。
――なるほど。
開発都合になりますが、殴ったり蹴ったりという部分を作りすぎると、武器を持った時の大雑把な遊びができないので切っていたんです。でも、それは個人的にはマイナスな要素でした。
『龍が如く』のテーマは“街を楽しく遊ぶ”こと。あわせて、現代の日本の繁華街を楽しむ作品なので、街に自転車が置いてあったり、看板があったりします。だから、バトルでは街にあるものを利用してほしいと考えています。
また、本作ではバトル中に自由に移動できるので、なおさら、物を持てるようにしてほしかった。
――それほどまでにこだわっている要素だと。

|
|---|
街で遊んでいるという感触がないと『龍が如く』ではないので、システムのベース部分と整合性をとりつつ、搭載してもらえるように頑張ってもらいました。
――手にするアイテムは強力なので、アクションが苦手な人の助けにもなっている印象があります。
それもありますね。今作においてはアクションが苦手な人はボタンを連打するよりも、街をうまく利用すると進めやすくなります。でもその戦法だけだと、ボス戦でアイテムがなくなって困ることもあるのですが、それでいいかなと。
――武器といえば、シリーズでおなじみの“黄金銃”はなくなったんですね。
これまでのシリーズでは弾切れのしない“黄金銃”がありましたが、本作では常時装備できる武器がないので入れていません。スペシャルアイテムがないため、“黄金チャリ”のように、どこにでも出てくるようなアイテムを実装できないのか検討したのですが、出てきてはいけない場所に出てしまうため、泣く泣くカットしました。
サブストーリーや横の展開に迫る
――サブストーリーで、これまでのシリーズから連動したものが豊富にあったという印象でしたが、あえて用意したのでしょうか?
これにはいろいろな理由があるのですが、1つにはシリーズを遊んでいる人へのサービスという理由があります。
――ムナンチョヘペトマスは大阪でのエピソードだったため、桐生が知らなくても成立しているという細かさもツボでした。
以前のシリーズで人気があったものをなるべく選んでいます。シリーズをまたぐ要素は、過去作を遊んでいない人には伝わらないネタもありますので、数を絞ってはいます。
サブストーリーについては、毎回カテゴリー別に数量を分配するようにします。例えば、感動するもの5本、時勢を反映したもの5本という具合です。
――今回であればドローンや動画配信者ですね?
そうなります。あとは歴代キャラを感じさせるもの、過去のサブストーリーを感じられるものなどです。全部が趣味嗜好に寄ってしまってもしょうがないので、それを加味しながら決めていく。
――サブストーリーといえば、小野ミチオも印象に残りましたね。

|
|---|
最後にいい話が来たので、印象的なのかもしれません。ネタ出しの初期段階で、ユーザーの心にどこか残るような“ゆるキャラ”を作ってほしいとお願いしました。プロモーションで出す以外にも、もし可能だったらグッズを出せるようなものになってほしいという願いもあります。
――名産を集めたフォルム、適当な設定など「本当にいてもおかしくない」と思いました。
それは担当がゆるキャラの勉強をした成果ですね。あとは、桐生が中に入っているから、やりとりが余計におもしろく見えます。開発の中でも人気で「もうちょっと盛り上がってほしい!」と思っているようです(笑)。
――フォトコンテストが実施中ですが、反響や応募状況はいかがでしょうか?

|
|---|
結構な数が来ています。スマートフォンで撮影する機能があるため、ああいう取り組みはやりたいと思っていました。
本作では、街の通行人たちの反応を入れたことで、我々が想定していなかったような、奇跡の写真がとれるはず。開発メンバーもいろいろやってみたのですが、試すことが楽しいですね。
――人に寄って狙うポイントも異なりそうです。
TwitterやInstagramといったものは、この10年で生まれたきた新しいツールです。せっかくスマートフォンを入れたので、こういう時代に求められ生まれたものをゲームに入れたいと前から相談していました。バシバシとって応募してください。
開発的には絶対に撮ってほしくないものを送ってきた人にも、何かあげたいですね(笑)。
――これまでのシリーズキャラの怨念が登場するのも、撮影を促進させるためでしょうか?
写真といえば幽霊という古典的な流れはまだあるじゃないですか? 本作の心霊写真は歴史を楽しませてくれる、シリーズファンに向けたものでもあります。11年間もずっと作り続けているからこそできること。ぶっちゃけてしまうと神室町は街全体が事故物件なんですね。
――“街全体が事故物件”というのはすごい表現ですね(笑)。
「あのキャラはここで死んだ」というようなエピソードを思い返してほしくて入れました。ファンの方によっては「あのキャラが公式に死んでしまった!」とお怒りの方もいるようですが、それは生霊ということにでもしておいてください。ちなみにこの言い訳、東京ゲームショウの時にとあるファンの方から教えていただきました。「その解釈、ありですね!」と(笑)。
桐生一馬の最後を見届けほしい
――これからのシリーズはどうなっていくのでしょうか?

|
|---|
本作は『龍が如く』という遊びの最終章ではないと思っています。前々からことあるごとに言っているのですが、もしかしたら、桐生がナポレオンになるかもしれませんし、『龍が如く』を感じさせる新しい何かを作るのかもしれません。
当たり前のことですが、我々のチームはゲームを作るために存在していますから、今後も何かしらのクリエイティブを続けていきます。今年は新しい何かをやる年になる予感がしていますね。
――本作をまだプレイしていない方へメッセージをいただけますか?
昨今ではさまざまな遊びがあり、屋外に行って映画を見たり、娯楽施設に行ったり、さらには場所を選ばずスマホなどを使ってゲームや映像を楽しむこともできます。そんな中、家でやる遊びとしてはPS4で本作をプレイするのが、今もっともエキサイティングな遊びだと思っています。
いろいろなところで言っていますが、“2016年の日本”が描かれているエンターテインメント作品で、本作以上の感動体験が味わえるコンテンツはないと思っています。今の日本の遊びが詰まっていますので、ぜひ遊んでみてください。
――シリーズファンに向けてのメッセージもお願いします。

|
|---|
ストーリーの内容的に賛否両方の意見が出ることを承知で出したタイトルです。脚本が完成した1年半前に、覚悟を持って決めた“桐生一馬の最終章”であり、我々が『龍が如く』ファンの方たちに伝えたかったひとつの結末です。
起こるべきを描かないことも必要です。ですが今作では、桐生一馬と澤村遥というキャラクターを“ひとりの人間”として描ききるために、彼らの心の強さと弱さ、不条理な現実をあえてぶつけることにしました。
試練ともいうべき苦境に耐える桐生一馬の姿、そして決して利口とは言えない彼と彼らの仲間たちが立ち向かう姿を見て、ユーザーの方の心に何かひとつでも強い感動を残せたらと思っています。
ひとりでも多くのシリーズファンの方にプレイしていただいて、桐生一馬の最後の闘いについて、後々まで語りあっていただきたいというのが個人的なメッセージとなります。『龍が如く6』を末長くかわいがってくださいますよう、よろしくお願いいたします。
(C)SEGA
データ