2019年2月1日(金)
『ジャッジアイズ』開発者が語る! 読めばもう一度プレイしたくなる特別インタビュー/後編【電撃PS】
主人公・八神隆之を木村拓哉さんが演じ、ゲーマーだけでなくカジュアル層も巻き込み、今もロングセラーを続ける“龍が如くスタジオ”の最新作『JUDGE EYES(ジャッジアイズ):死神の遺言』。

|
|---|
今回は前編に続いて、10人の制作スタッフ(&プロデューサーの細川一毅氏も途中参加)が顔をそろえたロングインタビューの後編をお届けします。なお、内容はクリアしたことが前提のネタバレあり(伏字含む)となっていますので、まだクリアをされていない方はご注意ください。(インタビューは1月11日に実施)。
脚本にはなかった演出も多々追加
――イベントシーンのなかで、ぜひここが会心の演出だというのがあればぜひお聞きしたいです。ファンの間では、スケボーでのチェイスシーンがカッコイイし、某探偵マンガっぽくて人気ではありますが。

|
|---|
一同:(笑)。
吉田:あれも苦肉の策なんですけどね(笑)。

|
|---|
| ▲ディレクター 吉田幸司氏 |
上原:いや、そんなことはないですよ。あれはしっかり長尺で見せ場を作ろうとしていましたよ(笑)。

|
|---|
| ▲アクションパート企画チーフ 上原康輝氏 |
吉田:これもぶっちゃけた話をすると、チェイスがゲームとして少し盛り上がりにかけるので、ならばおもしろくするにはどうしようかと考えたときに、僕から出したオーダーが「さらにシステムを足すのではなく、カッコイイ絵がとにかく見られればいいから」というものでした。ああいう演出のシーンを追加してほしいというオーダーを、ちょうど一年くらい前から出して、作ってもらったのがあのシーンなんですよ。
安藤:最初はもっとパルクールっぽくというキーワードもありましたね。

|
|---|
| ▲キャラクター制作チーフ 安藤俊周氏 |
――塀や手すりをアクロバティックに飛び越えるヤツですね。
安藤:チェイスでも人を乗り越えたり、フェンスを乗り越えたりするアクションがありますが、ああいうものがそういう部分での名残なのかなと。
細川:もともと神室町を住み家としている、神室町の隅々まで知っていてパルクールアクションで飛び回るという主人公像がありました。じつはバトルでのアクロバティックな動きも、その設定が生きています。最初は操作キャラクターを入れ替えて、得意な分野に対応するという原案があって、それが先ほどのさおりのキャラクターチェンジとして残っていたりします。
安藤:パルクールという部分でいえば、わりと冒頭に警官に追いかけられる窃盗団が、パルクールアクションで逃げるカッコイイシーンがありますが、その直後に目玉を繰り抜かれた死体が早朝の静かなシーンで映るという、あのコントラストがイベントシーンのなかでも個人的にいいなと思いました。
――神室町で今起きている状況もわかるし、イベントの静と動の落差みたいなものも感じますね。
下原:イベントシーンでいえば、ラストの裁判から神室町に行って、創薬センターに行ってという一連の演出ですね。

|
|---|
| ▲サウンド制作チーフ 下原史義氏 |
とくに創薬センターの演出は、サウンド的にいろいろな制御をしています。例えば、爆発して渡り廊下から落ちるところとかで曲を止めるなど、ユーザーの感情の流れに合わせてシーンに没入させる試みはサウンド的にもこだわってやっている部分です。

|
|---|
演出の静と動の差が激しいうえに展開も目まぐるしく、シーンとしても非常にカッコイイ部分ですね。じつはこのシーンは古田のオーダーがけっこう細かくありました。ここはこういうエフェクト的な声にしてくれとか、裏で流れる曲の感じをこんな風にしてくれとか、最後は幻覚の音響効果がだんだん復元していくようにしてくれなどですね。それもあり、ユーザーのみなさまにも印象に残るシーンになったのではと思います。
細川:未完成の状態であのシーンをプレイしたときは、本当に鳥肌が立ったくらいだからね。
時枝:少しゲームからは離れるかもしれませんが、エンドロールも新しい試みだったと思います。

|
|---|
| ▲ゲームシステム設計 時枝浩司氏 |
――あの演出はよかったですね。ドラマのエンディングクレジットな雰囲気で、1つのドラマを見終えたんだなという感覚でした。
吉田:あれはあの短期間で作り上げたこと自体が感動的なんですよ(笑)。まあ、制作期間というよりかは時期ですよね。
時枝:「今からやるの?」的な感じでしたからね(笑)。マスターアップ寸前で。
細川:オープニングも未完成な状態でしたからね。
――え、オープニングはけっこうあとに固まった感じなのですか?
細川:最後じゃないかな。ほかの要素を作り終えたあとですね。
――たしかにいろいろなキーワードを散りばめなくてはいけないし、かといってネタバレをどこまで入れるかという調整もありますよね。
細川:みんな知っているから、「これはネタバレしすぎじゃない?」と思ったのですが、公開したときに意外とストーリーがばれてしまった、という感じではなかったですね。
上原:そうですね。クリアしたあとで振り返ると、じつはネタバレのオンパレードだよねと(笑)。
染屋:エンディングに関して言えば、最後の最後で何かおもしろいことをしたいなと思ったので「今回は変わったことをしたい」と、デザインサイドから提案させてもらいました。最初提案した演出を名越に見せたらボツをくらいまして、いろいろな経緯で最終的に猫を捜す演出になりました。

|
|---|
| ▲アートディレクション/デザイン統括 染屋直樹氏 |
――ちなみに、今回いろいろなところで猫推しなのは何か理由があるのでしょうか? 猫好きのスタッフが多いとか?(笑)
吉田:そういうのもあると思いますが、単に使いやすいんですよね。全体として猫を使おうではなく、ここに何か入れられないかとなったときに、猫が入れられるんじゃないと。
――重要な調査シーンがスタートしても、猫の声が聴こえると真っ先にそちらを調べるという(笑)。
一同:(笑)。
吉田:そこもサーチモードで何かおもしろいことができませんか、となったときに猫を捜しましょうとなったわけです。インテリアアイテムを飾りたいとなったときも「何を飾りたい?」となって「猫を置きたいんです」と(笑)。それはインテリア担当が言っているので、誰か1人が「猫が……」と言っているわけではないんです。なかでもエンディングの猫は名越が言っていたものですね。
――結果的に猫尽くしになったわけなんですね。
使いまわし感が出ない神室町を用意
――今回の舞台となる神室町ですが、『龍が如く6 命の詩。』からどう変えようとしたのでしょうか?
染屋:神室町に関しては『龍が如く』とは異なる見た目にしたかったんですよ。そこで重要視したのが、LUT(ルックアップテーブル)を使った絵作りです。例えば1つの色を少し抑えめにして、2色を強調させるような絵作りにしています。あとは今回新しくドローンレースが追加されているので、それに合わせて地形を遊びやすいものに作り替えるなどしています。

|
|---|
――そうなるとドローンレースのコースも、そのままゲーム中の地形が使われているんですね。
染屋:『龍が如く6』の神室町から、ドローンレースに合わせて街灯の位置やサイズを変えていますね。あとはアクションで壁のぼったり、車のボンネットの上に乗ったりとなどが新しい試みです。
厚:車のボンネットに登れるという話が出ましたが、プレイヤーの自由度が上がったことにより、エンジン回りも下回りが強化されていまして。ようやくミレニアムタワーのエスカレータが動いたという(笑)。

|
|---|
| ▲“ドラゴンエンジン”開発チーム統括 厚 孝氏 |
一同:(笑)。
上原:13年越しに動いたときは、開発でも盛り上がりましたね(笑)。
厚:神室町のエスカレータは全部工事中か清掃中で止まっていたのですが、ようやく動きました。しっかりあそこで敵を倒すと、一緒に運ばれていきます。ようやくエンジンとして機能したかなと。

|
|---|
下原:じつはエスカレータが動いた事に驚愕して、サウンドでも「音を付けようぜ」となったんですよ(笑)。けっこう馴染んでしまってわかりづらいのですが、しっかり音が付いています。
細川:エスカレータから音がしてたんだ!?
――それは言われないと気づかないですよね(笑)。
吉田:下りなのに敵が逆走して登って来るなど、動いたら動いたで大変なこともあるんですけどね。
細川:神室町については企画の初期段階で、神室町を使うのか使わないかと悩んだ際に、使うべきだという判断材料のほうが多かったので、使うという決断をしました。それに対して使いまわしというか、見飽きたというネガティブな反応が出てくるのは当然わかっていたんです。
そういった予想に対して、どのように解消していくのかというのは、全員と相談しました。先ほど話に出たようにLUTを使った絵作りの変化、lookという部分についても、かなり初期段階から染屋に相談しながらアプローチしていました。
また、八神は神室町で育って神室町で生活している人間なので、神室町の隅から隅まで自由に移動できる。だからこそ、今までの『龍が如く』では使わなかった裏道や、建物の中などをもっと充実させようというのが、使いまわし感を減らしていく上でのアンサーでした。
じゃあ、どこをどのように拡張していくかとなったとき、意外と『龍が如く6』の時点で行ける場所はすごく増えていたんですね。あまり使われていなかっただけで。今作で『龍が如く6』をプレイした方が「こんなところに行けるようになっている」と驚かれている場所も、じつはすでに行けていたという箇所がけっこうあるんです。
吉田:喫茶ミジョーレも『龍が如く6』の時点で入れたんですよ。

|
|---|
細川:なので、ならばしっかり全員で資産を活用しようと。それによって、見たことがない神室町をもっと感じてもらえることで、使いまわし感や飽きた感をなくせるはずだと考えました。
――たしかに八神で調査をするときに、主観視点で見まわすことが多かったので、知っているはずの神室町なのに、また新しい体験、新しい街に来た感覚を味わえました。
細川:また、何か大きな進化要素を入れれば、違うような印象を与えられるのではと開発の初期段階で考えていたものもあります。そのひとつが、リアルタイムでの時間変化だったんですが、みんなに相談したら総スカンを食らいまして、けっこう早々にあきらめました(笑)。
伊東:じつは時間の変化自体は、『龍が如く3』のときから何度もチャレンジしてきたことなんです。技術的にはできないこともないんですが、どちらかというとシナリオとの整合性をどうとるかが問題なんですよね。

|
|---|
| ▲プログラム統括 伊東 豊氏 |
――夜でないとそぐわないシーンが昼に発生してしまうとまずい、とかでしょうか?
時枝:いえ、例えば「明日来い」と言われたのに、ゲーム内で3日経ってしまったということが起こり得るんです。ならばそのタイミングだけ時間経過を無くすのか、でも進まないのは変だよねという話です。
――街といえば、ドローンでの調査は今まで見えない神室町が見えることになり、調整は大変だったではないでしょうか?
時枝:そうですね。今までは地面を走り回ることしかできませんでしたが、空中を行けるようになって、今まで作っていなかった部分まで作らないといけません。今まではいわゆる2次元で作り込んでいけば立派なものができましたが、今回は縦のものを作り込まなくてはいけない部分で、かなりデザイナーが苦労したのではと思います。
しっかり作ってくれたというのもあり、ドローンレースはそのままアドベンチャーをプレイする街を、そのままコースとして使える形になりまして、かなりの進化は遂げられたのではと思います。
――ドローンレースは膨大なレース数といい、1つのゲームですよね。
時枝:最初はドローン用のコースを作ってほしいと話をしていたのですが、名越から「生活感あふれるこの街のなかでドローンを使ってレースをしたい」と熱望されたので、これはもう避けられないなと。逆に作ってみて、神室町の今まで見ていただけなかった部分を体感してもらえたのは大きかったと思います。

|
|---|
――上から眺める神室町は新鮮で、レース中は風景も楽しんでしまいました。ただ、操作がものすごくマニアックですよね?
時枝:そうなんですよ。操作が難しくて本格的というご意見はある種うれしくて、思ったとおりというか(笑)。じつは会社でドローンを購入してもらって、実際に現物でテストをしながらそれに寄せる形で作っていきました。
本物のドローンの場合は壁に当たるとクラッシュするじゃないですか。ゲームでもそこまで再現してみたのですが、あまりに難しすぎるという意見が多かったので少しずつゲームしやすい形にしていきました。
ただ、実際にドローンを触ったことがないユーザーさんも、少しでも本物に近い体験をできるようなコンテンツにしたくて。なので、操作だけはできるだけ本物を感じてもらえるように、マニアックな操作も選べるようにしてみたわけです。
厚:じつは最初、物理エンジンでドローンをしっかり作ったんですよ。しっかりプロペラに4つ重心があって、飛ぶ原理を物理エンジンで再現してみました。これがドローンそのものですというところまで作ったんです。
時枝:実際に飛ばしたときと同じような感触を体験できたのですが、飛ばそうとするとすぐに裏返ってしまって(笑)。
細川:実際のドローンは、そんなに難しくはないよね?(笑)
厚:本物はビックリするほど安定していますし。
吉田:ドローンの音は実物から録ったの?
下原:効果音ライブラリの素材と収録した音を混ぜて使っています。収録は一定のところに飛ばしながらマイクを狙うのですが、レース用ドローンの場合は細かく調整しないと安定しないので、リアルのドローン操作の腕も上がりました。海藤さんの苦労を身をもって体験しましたね(笑)。
細川:最初はすごくうるさかったから、少し抑えようとなったよね。
下原:そうですね。そういう話もあって、ドローンの音はビーンという少し耳障りな感じもあったので、そこは調整しながら耳障りな部分を抑えたりしました。あとはドローンレースでパーツが変わるので、それに応じていろいろな音を組み合わせています。やはり値段が高いドローンのほうがいい音がするというのが、個人的な感覚ですね(笑)。
一同:(笑)。
――ゲーム中のドローンも、性能の高いドローンはいい音がするのでしょうか?
下原:高性能なパーツに高価なドローンの音素材を使用したわけではありませんが、特にドローンレースでは高性能なパーツほどスピード感を感じる音に仕上げています。かなり最後のほうでの作業で、実装できるか危なかったのですが、ギリギリ間に合いました。
――ゲーム全体のUIについては全体的にポップ寄りかなという印象を受けたのですが、このあたりはいかがですか?
冨田:今回UIデザインのメンバーは全員女性で、それをあまり感じさせないようにはしたかったのですが、UIは写実的なキャラクターやステージより変化をつけやすい部分なので、積極的に今までと変えようという意識はしていました。

|
|---|
| ▲UI制作チーフ 冨田万里江氏 |
先ほど桐生さんは強靭という話がありましたが、歴代の『龍が如く』のシリーズのUIは筆文字を使ったり、黒っぽい色をベースに使ったり、男らしいデザインが多かったんです。今回はスマホを使っている感じを出すためにも、フラットデザインに寄せたかったというのがあって。全体的にフラットな印象で明るい色を使いつつ、ストーリーや八神の持っている複雑さ、繊細さを出そうと思ったらあのようなデザインになりました。

|
|---|
上原:そういえば、最初の頃はスキルをゲットしたら、すごくかわいいキャラクターがでてきていたよね(笑)。
冨田:じつは当初、1つ1つのアプリを、それぞれ違う会社が運営しているという設定で作っていたんです。本当の携帯みたいに、1つ1つの機能で雰囲気をバラバラにしてくれというオーダーがあり、多方面にがんばったのですが、まとめるのがすごく難しくて(笑)。
それで染屋さん、吉田さん、細川さんに見てもらうなかで、もう少しまとめていこうと。それで直線的なグラデーションなどの色の使い方を、どんどん整えていった感じです。
――リアルだけどもそれだと頭のなかがこんがらがりますね(笑)。
冨田:そうですね。そこは難しかったですね。ギリギリまで修正していた部分なので、スケジュール的にかなり周りをヒヤヒヤさせたのではないかなと思います。
――ロゴについてもゲームが固まってから最後にという感じでしょうか?
冨田:ロゴについてはそうですね。
細川:じつはタイトル名が最後まで決まらなかったんですよ。開発メンバーが『JUDGE』と本作を呼んでいるのも、仮称『JUDGE』で進んでいたからです。でも、名越がイベントのときに話していたと思いますが、『JUDGE』ですと商標が取られていました。なので、変えなきゃいけないというなかで、なかなか何にするのかが決まらなくて。去年の5月、6月までは『JUDGE』だったような。
冨田:ずっと『JUDGE』でしたね。しっかりしたロゴが入ったのが、マスター直前の7月とかですね。
――ちなみにUIのデザインを決められるときは、周りが形になってから、それを表現するには? と考えてデザインするやり方なのでしょうか?
冨田:最初に仕様書を作ってもらうのですが、ほかの人が話しているように『JUDGE EYES』はみんなで模索しながら、要素を足したり削ったりしながら作っていったので、その通りにはいかないことも多くて。
バトルもスキルの部分は最初、別の人が仕様を切っていたのですが、あとから上原が参入したタイミングで「変えよう」となって、あとからガッツリ変更が入りました。

|
|---|
上原:ごめんね(笑)。
吉田:調査アクションの数がすごく多くて。違うんだけども似ているものや、サーチモードだけでも何種類あるんだと。いろいろなことで、こっちはこう、ボタン配置はこうとなっていたものを統一した方がいいのではと、ギリギリまでやっていたので、UIの作り直しは本当に多かったです。
――そこも新しい作品ならではの苦労ですね。
吉田:調査アクションが全部で何種類入れるのか、最初から全部カッチリ決まっていたわけではないんです。ストーリーがあって、これを実現するためにどんな調査アクションが必要かというのは最終的に決まっていきました。
スクープミッションも最初はなかったんですよ。あと付けでどんどん作って行って、調査アクションが増えていったので、最後にたたむとき“これとこれをまとめよう”というプロセスが発生したわけです。
――探偵だったらこれがあるよね、という作り方ではないと?
吉田:最初はそれもあったのですが、システムだけを先に作ってしまうとお話に合わなくなるんですね。
――そういった調査アクションがふんだんに盛り込まれたサイドケースですが、今回はフレンドのイベントを含めるとかなりの数になりますよね?
福田:ガールフレンドイベントも含めると104個です。サブストーリーについては、執筆に入る段階で調査アクションの仕様がある程度固まっていました。ですので、脚本としての面白さを押さえつつ、それぞれの調査アクションを活かすシナリオを作成するという流れでした。そのため、調査アクションはけっこう入っていると思います。

|
|---|
| ▲サイドコンテンツ脚本・演出 福田弘直氏 |
――そんなサイドケースですが、スタッフのなかで話題になったものはありますか?
福田:変態三銃士ですかね? キャラ班がざわついていたような気がします。
一同:(笑)。
安藤:木村さんとあの絵を並べていいものかと(笑)。
福田:あれはけっこう紛糾しましたよね。
細川:「これ、俺が事務所に確認を取らなきゃいけないのか」と頭を抱えましたね(笑)。
安藤:作る方は楽しんで作って、あとは細川が監修に出すだけでしたし(笑)。やはり変態らしさを出すのに苦労はしました。
福田:例えばデバガメ判事の望遠レンズのようなものは、あれだけでキャラ性が強く出たと思います(笑)。
――シナリオ側から、ここをもっと変態にしてくれという要望を出されることなどはあったのでしょうか?
福田:はい。じつはサブストーリーは基本、ありものでどうにかしようというという流れでしたが、作っていくなかで、やはりキャラ性の強化が必要だという話になり、追加で要望を出させていただきました。
安藤:デバガメ判事さんも、モデルはうちのスタッフですけどね(笑)。あの眼鏡を付けることになって、一気に変態度が増しました。あとは壁を張っている絵を見て「こんなの見たことがない」と。気持ちが悪いけれども、もう少し服をテカらせてみようかな、とも。
一同:(笑)。
上原:バトルの真面目な仕様を書いているときに、その横で「もっと変態がさ」とか「パンティがさ」という話が聴こえてくるのは、ゲームを作ってきたなかでなかなかない体験でした(笑)。
安藤:最初にパンティ教授って名前を出すのにはちょっと抵抗ありますよね。

|
|---|
福田:パンティ教授の名前は最初“パンツ教授”でした。ですが、「パンツで伝わるのか?」という話が出まして……。名越もいる場で真剣に議論されました。大の大人が真剣な顔で「パンツか、パンティか、どっちだ?」と議論するんです。
一同:(笑)。
福田:最後は名越がジャッジし、“パンティ”で統一することになりました。
――一切の妥協がないんですね(笑)。
福田:はい。決してふざけていたわけではなく……。キャラクターの呼称は大事ですから。
――何気に変態三銃士のサイドケースは、早乙女陽介のフレンドイベントや早乙女月乃のガールフレンドイベントにもつながってきて、かなり重要なサイドケースですよね。
福田:1人のキャラクターが、さまざまなサブストーリーで登場するという流れは、じつはキャラクター制作コストを抑えなければならないという事情からだったんです。しかし、結果としてそれがサイドケース、フレンドイベント、ガールフレンドイベント、それぞれのキャラクターが絡み合いながら、話が膨らんでいく……八神の世界が広がっていくという印象につながったかと思います。
例えばサイドケースで知り合ったキャラクターが、フレンドイベントで再登場し、そこでそのキャラの先のお話が展開していくという感じです。
――たしかにキャラクター性が色濃くなるというか、こんな側面があるのかというのが見えてきます。
福田:キャラクター性の深掘りになりましたし、キャラクターに愛着をもってもらえるようになったなら、よかったと思います。
――なかでも陽介はいいキャラですよね。あんな顔をしてセクハラ単語をバンバン言いますし(笑)。

|
|---|
一同:(笑)。
安藤:じつは陽介が一番変態なんじゃないかと(笑)。
吉田:あいつがもともと変態だったからだね(笑)。
福田:はい。当初は陽介が、変態三銃士シナリオの最後の1人、ジャイアント・インパクトだったんです。
細川:この前ネットを見ていたら、「陽介が変態三銃士シリーズのラスボスかと思った」とコメントしている人がいて、その方の洞察はすごいなと感心しました(笑)。
福田:ただ、月乃を守るためにいろいろがんばってきたのに、最後陽介が捕まっちゃったらすごく悲しい気持ちになってしまうということもあり、設定を変更しました。それに匹敵するインパクトがある正体を考えていたときに、あのキャラクターが生まれました。
――あれはインパクトありましたよね。
吉田:ちなみに今回は街中のポップアップで聞こえてくる会話もあるじゃないですか。あれも福田が書いています。
――とてもバリエーションが豊かですよね。
福田:ほかのプレイスポットへの誘導になっていたり、サイドケースに出てくるあるブラック企業の話が聞けたりなど、世界の広がりが感じられるようなものなどが用意されています。たとえば『KAMURO OF THE DEAD』を楽しむ住人の会話で、プレイスポットに興味をもってもらうようなテキストです。

|
|---|
――「小野ミチオ、東京進出したってよ」という会話もありましたね。
狭さをメリットに変えた本作のバトル
――『龍が如く』とはまた違う爽快感が本作のバトルの魅力ですが、なかでも発勁と三角飛びは際だった要素です。こちらはどういったところから入れたアクションでしょうか?
上原:やはり身軽でスタイリッシュというキャラクター性が根底にあったので、じゃあ今までパワフルだったキャラクターたちが多かったなか、どうやったら新しく、カッコよく楽しく遊べるだろうと考えたんです。
“龍が如くスタジオ”のゲームは、街をテーマにしていることもあって、狭い場所がけっこう多いのですが、壁は邪魔になることが多いんです。でも逆にそういうところを使えたらおもろくなるかなというところから、最初は入った感じですね。
――たしかに今回は壁を探したくなりますよね。
上原:そうですね。壁が近いから使ってみようと。それで、今までにないアクションも生まれるということで入れてみました。ただ、これもだいぶ揉めましたね(笑)。
――それはどこを壁にするかということでしょうか?
上原:それもあります。
細川:暴発が多かったんですよ。
伊東:カンタンな操作じゃないと、アクションゲーム初心者が多い『龍が如く』シリーズでは、なかなか使ってもらえないんですよね。ただ、あまり暴発してしまうとそれがストレスになるので、三角飛びや馬跳びの操作方法や出る条件については相当揉めました。

|
|---|
個人的には、たとえ偶然でも今回新しく入ったアクションが出ることで、プレイヤーにとっては「あ、なんだこれ」「これはどう出すんだろう」という驚きがあると思ったので、多少暴発してもいいのでは、と言った覚えがあります。
上原:途中は開発スタッフから文句が出るほど、暴発していた時期があったんです。敵から逃げようと階段を走るだけで暴発して、殴られて倒されてしまったとか。ほかのゲームですと、ジャンプはボタン入力でということが多いと思いますが、それはやらないという方向性だったので苦労しました。
――発勁は使ってとても気持ちがイイアクションですが、いろいろな意味で『龍が如く』にはない技だったなと。
細川:上原は『北斗が如く』のバトルも担当していたんですよ。
――なるほど。たしかに『北斗が如く』のバトルに近い感覚ですね。
上原:『北斗が如く』の制作が終わってから「入れたい」と、ムチャを言って入れてもらっいました。ずっと『龍が如く』のバトルを担当していた折原(純氏)が『北斗が如く』のディレクターを担当していたのですが、『北斗が如く』の開発をしているときに「今『JUDGE EYES』でこういうことをやっていて」と話したんです。
そのときに「やはり夢のあるアクションを入れていきたいよね」となって、今『北斗が如く』でこんなアクションを入れているし、ちょうどいいのではと発勁のアイデアを揉んでいたら、楽しそうだなと。で、ちょっとお願いして入れてみました(笑)。少し操作が難しいかなと思っていたのですが、想像以上にみなさんに使っていただけているのでよかったなと。

|
|---|
伊東:やはり動画配信がOKなことも大きいと思うんですね。実況プレイのなかで、誰かがこれを使っているのを見て「あ、これはすごい」と。で、じゃあ自分もやってみようと。
――そういう要素は今回ありますよね。
伊東:そもそもスキルの存在に気づかなかったり、覚えたとしてもタイミングや出し方がわからなかったりした人も多いと思うんです。動画の力はけっこう大きいですね。
――そういう意味では発売後のDLCの仙薬については、"フル課金キムタク"というすごいパワーワードが話題になりましたよね(笑)。
一同:(笑)。

|
|---|
――あれは課金要素だからこそあそこまではっちゃけたという感じでしょうか?
吉田:それくらいのものでないと欲しくならないかなと。1つはお助け要素ですね。ドラマ重視のゲームで木村さんが主演なので、これまでゲームをやってこなかった方にもさわってもらいたいという思いがあったので、まずお助けアイテムを作ろうと。
しかし結局バトルで強くなるだけだったら、バトルが本当に苦手な方しか買わないだろうと。そうでなくて、見て楽しむ、使って楽しむがあって、それが強かったら文句なしですよね。あのへんのアイデアは迷わず出てきたよね。
上原:3日かかってないですね(笑)。伊東のほかにバトルの中核に携わっているプログラマーがいるのですが、彼はああいうのが大好きで、ずっとやりたいやりたいとシリーズを通して話していたのですが、「これ、チャンス到来じゃない?」と盛り上がって(笑)。
一同:(笑)。
伊東:今までずっと亜門を作ってきたプログラマーなんですよ。亜門だけは悪ノリしてもいい枠だったのですが、今回は仙薬で「じゃあやるぞ!」と。
上原:吉田が言ったように、実利を兼ねてまさにこのタイミングならという感じでした。
細川:DLCの発売タイミング自体もじつはしっかり考えているんですよ。発売直後での配信もスケジュール的にできたのですが、やはり木村拓哉さんが主演の本格サスペンスアクションと言う部分で最初は盛り上がってほしい。最初からバカバカしい映像で盛り上がってしまうことで、最も商品力として捉えている部分がかすんでしまうのを避けたかったんです。
――たしかにいいタイミングだったと思います。
細川:シェア配信の範囲を少しずつ解放していくのも、『龍が如く』ではやっていなかった試みで、けっこう発売直前直後からずっと市場の反応を見ながら、じゃあいつDLCを配信しようとか、シェア配信の章を解放しようかなど考えていましたね。
――シェア配信の範囲は、今後も解放されていくのでしょうか?
細川:どこかで止めます。基本的にはストーリーの前半分は最終的に開放され、うしろ半分はぜひゲームで楽しんでくださいとなったらいいなと。まだもう少し解放はします(2019年1月24日時点では七章まで)。
――あとはバトルでは海藤との協力アクションなども見どころの1つですが、こちらは参考にされたものなどはあるのでしょうか?
上原:参考にしているというのは難しいのですが、正直なところ長いことやっているのでネタがなくなってきているということもあります。それで、よくやるのが、スタントマンの方たちと一緒に体を動かしながら「こういう風に動いたらカッコイイじゃん」とか。そこに演出を付ける担当も同席しているので、こういう流れのときにこういうカメラで撮りたいからなどと、話し合いながら作ることが多いですね。
新規IPだからこそ採用しなかったプレイスポットもある
――ドローンレースについては先ほどうかがいましたが、もう1つの大型のプレイスポットとしては“VRすごろく:ダイキュー”がありますが、こちらはドローンレースと同じく神室町全体を使った遊びの提供を考えて作られたのでしょうか?
吉田:そうですね。いわゆる店のなかでダーツやビリヤードのようなミニゲームではなく、街全体を使ってミニゲームを、というコンセプトにしたということですね。もう1つが、VRという今風のものにしたかったということもあります。
やっていることはわりとシンプルですが、VR空間ならではのハチャメチャなお題のミッションが次から次へと出てきて、しかもメチャクチャ金も稼げると。
――しかもあのなかであれば虎と戦えるし、レーザーバズ―カを撃てたりしますよね。
吉田:なんか知らない間にムナンチョ赤松がいるんですよね(笑)。なんか誰かがシレっと配置していて。
伊東:けっこう悪ノリですよね。エフェクトもすごくギラギラしているじゃないですか。あれで処理落ちしそうなくらいデザイナーがノリノリで作っているんですよ。『龍が如く』シリーズでもよくあるのですが、この枠内だったらそれぞれの担当者が自分たちでやりたいこと、試したいことを入れていいという流れで。
あとは過去のリソースで虎とかおもしろいものがあれば入れてしまえと。名越もミニゲームだったりそういう空間であればもっとやってもいいじゃないと言ってくれるので。
伊東:『龍が如く』も『JUDGE EYES』も、基本的にミニゲームの担当プログラマーは1人なのですが、この“VRすごろく:ダイキュー”も新人プログラマーが1人で作りました。1人でプランナーやデザイナーと打ち合わせをしながら、モチベーションが高い状態でやってくれて、完成したらすごいものに。
――あとはゲームセンターだと『ファイティングバイパーズ』ですが、当時はかなり遊ばせていただいたタイトルです。
厚:でも悲しいことにチーム内で知名度が低かったんですよね(苦笑)。
伊東:ゲームセンターに何を入れるかは、過去のアーケードゲームのリストを見ながら「これはライセンスが絡むから難しいよね」「これは移植されているよね」などと検討して決めています。『ファイティングバイパーズ』は今までPS4には移植されていなくて、しかもセガ・インタラクティブで過去にPS3などの機種に移植したノウハウがあったので、これはもう使うしかないと。

|
|---|
また、過去の『龍が如く』には『バーチャファイター』シリーズを入れてきたのですが、当時は『バーチャファイター』に対しての『ファイティングバイパーズ』みたいなところもあったので、じゃあ『龍が如く』に対しての『JUDGE EYES』ということであればピッタリのタイトルなんじゃないかなと。
じつは私が入社して最初に配属されたのが『ファイティングバイパーズ』のチームで、個人的にもすごく思い入れがあったので、かなり強くプッシュさせてもらいました。ちなみに、PS4への移植はいつものように厚が1人で手掛けてくれました。そういえば、先日細川がMCUさんと対戦していましたけど。
細川:けちょんけちょんにやられましたけどね(笑)。操作系があまりにも違い過ぎて、パッと入っていけないんですよ。
伊東:当時格闘ゲームをプレイしていた40代くらいの方であれば知っているゲームだと思うんですが、なかなか操作になじめない方も多いみたいですね。“うしろに入力してもガードができない”と言われるとか。
吉田:じつは『龍が如く 極2』で採用した“トイレッツ”を『JUDGE EYES』にという話があったんですよ。でも作品的に合わず、1作目でやるのはすごくバカゲーになってしまうと。ならば『龍が如く』でやればいいんじゃないとなって。
細川:シリアスとユーモアのハイブリットなのが我々のよさだと思う部分もあるので、これくらいのゲームがあってもいいじゃんと思いつつも、新しいタイトルにおいては全体の枠に収まるかわからないので、ちょっときわどいねと。ではせっかくだから裏で動いている『龍が如く 極2』で使いますかと考え、『龍が如く』ならばいいんじゃないと。
――たしかに桐生だったらありですね。全然違和感はありませんでした(笑)。ちなみにカラオケはやはりいろいろな意味で採用が難しかったのでしょうか?
吉田:それは完全に誤解でして。先ほどのトイレッツと同じで、1作目から入れたとしてもなじまないんですね。カラオケは桐生が『龍が如く』と『龍が如く2』でいろいろと真面目に培ってきたイメージがありながら、突然はっちゃけたというところにギャップがあっておもしろかったんです。1作目で八神が歌って踊っても、単にカッコイイだけなんですよ。
――では木村さんに決まる前からやるつもりはなかったと?
吉田:初めからなかったですね。交渉もありませんでしたし、NGをいただいたというわけでもありません。
――もし続編があるとしたら、入る可能性はあると?
細川:もちろん、我々がすべて決められるわけではないですが(笑)。
譜面にできないような楽曲でドラマを演出
――リーガルサスペンスというジャンルでの曲作りはやってみていかがでしたか?
下原:コンポーザー陣は、今回ストーリーに寄り添った楽曲に関して、より重点的に力を入れていたようです。とくにストーリー上、重要であったり、ショッキングなシーンについては、名越から譜面に出来ないような楽曲を作ってくれないか、というようなオーダーがありまして。
リーガルサスペンスという点でいえば、正義と悪の対比を楽曲で表現したり、シナリオ上の場面転換、急な展開ではガラッと変えたりです。あとは繊細な人物の心情に寄り添ったシーンなど、そういった点に対しては『龍が如く』以上に気を使って作業していました。
――八神がふと「これって……」と考えるときに、一瞬効果音が鳴って曲が止まる演出もいいですよね。

|
|---|
下原:あれは名越の肝入りです。最初は何も用意していなくて、何かしらハッと気づいたときの演出として入れてくれと、名越からオーダーがありました。
――あとは効果音周りも本作ならではの付け方でしょうか?
下原:効果音はサウンド側が最初から意識して変えようとしたというよりも、実際のゲームの内容や、リーガルサスペンスという部分での映像のテイストに合わせ、作るものが変わったという部分が大きいです。
バトルならば、桐生から八神になったことで力強さからよりスタイリッシュな方向になり、演出に関してはより重厚な感じの音になり、UIならばフラットデザインに合わせてよりシャープな音になりました。
ただ、「何だかんだと言いながら『龍が如く』っぽいよね」と、企画に言われたことも(笑)。やはり10年以上『龍が如く』をやってきていて、なかなか抜け出せないという。
細川:“龍脳”だよね(笑)。
下原:「あれ、おかしいな。けっこうがんばって変えたのにな」と(笑)。でも、もはやそれは“味”ということでお願いします。
細川:いったん仮素材として『龍が如く』の音を当てていて、ゲームが完成に近づくにつれて、より合った音に作り替えていくみたいなことをやっていました。出来上がっていくゲームや絵に対して、随時アジャストさせていく作り方です。
下原:音の場合は映像の意味を高めることが一番重要なので、ある程度絵作りが進んでいかないと最終的にフィットする音は作りにくいですね。何度も試行錯誤して、最終的な実装がギリギリになってしまいがちです。
“龍が如くスタジオ”の柱にしたいタイトルへ!
――エンディングを見る限り、続編はアリだろうなという終わり方でした。プレイした方からは八神の別の活躍を見たいという声も多いと思いますが、そちらについて可能性はいかがでしょうか?
細川:もちろん名越も再三言っているように、我々がもともと3年前にこのゲームを立ち上げたときは、スタジオの『龍が如く』シリーズで1本かぶりの状況から、もう1本柱を作りたい。ならばどういったゲームを作れるのかということを、いろいろと検討して実現してなんとか発売までこぎつけられたのがこの『JUDGE EYES』なので、当然続編は作りたいとは思ってはいます。
ただ、まだ現状で発売1カ月くらいしか経っていない状況で、どこまでユーザーさんに受け入れられるかを、もう少し時間をかけて見極めてから、じゃあ次をどうするとなってくると思います。だから、ここで続編を作りますとは言えませんが、作りたいとは思っています。
――最後に『JUDGE EYES』をプレイしている方に向けて、とくに注目してほしい部分、楽しんでほしい部分などのメッセージをひと言ずつお願いします。
吉田:僕は3章のサイドケースでも出てくる窃盗団ですね。じつはあのサイドケースだけは僕が書いているので、アイツらのその後とか自分でも書きたいなと思いつつ。アイツらの周辺を楽しんでいただけたらうれしいです。
――たしかに窃盗団を組んだ理由とか、もう少し知りたかったです。
吉田:本当はもう少しメインストーリーで展開させる予定があったのですが、もう少しそのあたりを膨らませられる余地があるかなと。
――杉浦の話が今後もっと語られる機会があるならば見たいですね。
伊東:今作では、『龍が如く』にはなかったようなアクションがかなり入っているので、たくさんスキルを覚えて、いろいろな技を使ってもらいたいです。また、アップデートで“EXTRA EASY”というモードが追加されて、これはボタンを連打するだけでいろいろな技が出るようになっています。
アクションが苦手な方はもちろん、ゲームが得意な方も、あのモードで遊ぶと普段あまり使わないEXアクションに気づいたりすることもあると思うので、ぜひ一度はプレイしてもらいたいですね。
――たしかに普通にゲームがうまい方ならば、選ぶ機会がないです。
伊東:カッコイイアクションが次々につながって出るのは気持ちがいいので、そのあたりを楽しんでいただけたらうれしいです。
染屋:注目してほしい部分としては、自分はエンドロールですかね。けっこうエンドロールは飛ばしてしまう方も多いので、そこはこのタイトルを作るうえでかかわった、関係各所の方のお名前を見ながら楽しんでいただけたらと思います。
時枝:カメラが動きますしね。
吉田:コントローラで少しだけ動かせます。
厚:一応“ドラゴンエンジン”タイトルでは3本目ということで、あい変らず神室町ではあるのですが、細かいところをいろいろと改良してよくしていっていますので、ぜひ昔とちょっとずつ見比べていただいて“あ、こんなところも変わっているんだ”ということを見ていただいたりする楽しみもありますので、そういう見方もしてもらえるとうれしいです。
時枝:もう私が言わなきゃ誰が言うということなので、ぜひ“Dリーグ”の優勝を目指してがんばってください。
――あれはけっこう難しいですよね。上達するコツなどありますか?
時枝:ひと言では難しいのですが、少し裏技的なものがありまして、マップを見ていただくと分かると思いますが、CPUがコースじゃないところをふわふわ走っている場合があります。じつはそこはショートカットになっているので、そこをうまく使うとかなり有利になるんじゃないかなと思います。
――アクセルは常に全開でなく、抑えるところは抑えたほうがいいですよね?
時枝:はい、安全第一です(笑)。パーツも最速重視よりは、少し耐久度がある、一段下のやつを選ぶとクリアしやすいかもしれません。
安藤:今作は木村さんやキャストの方も含め、キャラクター全員が躍動しているというか、ゲームのなかでお互いが響き合いながら生きている感じで作れたと思っています。これってじつはうちのキャラクター班内でも同じような現象が起きていて、お互いが刺激し合いながら響き合って、生き生きと個性を発揮して作っていった結果が、絵にそのまま表れていると個人的には思っています。そのあたりも遊んでもらいながら感じていただけるとうれしいです。
冨田:新規のミニゲームでゲームセンターの『KAMURO OF THE DEAD』があります。『龍が如く OF THE END』をプレイしていた方からすると、ちょっと懐かしくて楽しくなるゲームになっていますので、ぜひプレイしてみてください。

|
|---|
――『ハウス・オブ・ザ・デッド』をプレイしていた世代としては、ちょっとなつかしくもありますよね。ドリームキャスト・ガンが欲しくなる、みたいな(笑)。
冨田:あとは“VRすごろく:ダイキュー”で、ころにゃんというキャラクターがいますが、じつはあれは仕様書にはなかったんです。ゲームだったらナビゲーションキャラクターがいるでしょうと、UI班が勝手に作ったキャラクターなんです(笑)。
プログラマーや企画の方も悪ノリして、どんどん肉付けしていったキャラクターで、最終的にはゲーム内のUFOキャッチャーのプライズにもなっています。

|
|---|
――ころにゃんができて、クロにゃんができて、最終的にはマスコット化してということなんですね。
冨田:そうなんですよ。
細川:カスタムテーマにもころにゃんが使われていますね。
冨田:思ったよりも展開してもらえたキャラクターなので、「あ、こんなところにもいる」という感じで楽しんでいただきたいですね。
――ぜひ現実でもプライズ化してほしいですね。ぬいぐるみならば抱き心地がよさそうですし(笑)。
上原:『龍が如く』でもそうでしたが、やはりボス戦はしっかり力を注いで作っています。演出もかっこよく仕上がっていると思うので、ぜひ最後までラスボスが誰なのかをご自身の目でたしかめて、倒してほしいです。
あとは今回もいろいろな要素が絡み合っていますが、全部クリアすると『龍が如く』でもおなじみの亜門が出てきます。今回はしっかり謎を解き明かせば、けっこうカンタンに倒せるようにしました。今のところ解いている方はあまり多くないようですが、亜門の最後のバリアは解くことができます。
――バトルとして単純にゴリ押しではなく、やはり八神らしくしっかり謎を解けば倒せるということなんですね。
上原:そうですね。そのひと工夫だけで、あまり長い時間亜門を殴らなくてもよくなります。もし記事を読んでくださった方で、まだその謎を解いていない方は挑戦してみてください。
――それはぜひチャレンジしたいですね。でも、その前にフレンド50人の達成が難しくて、まだ亜門が出せていないという(笑)。
福田:はい。おっしゃる通り、フレンドの50人達成はすごく難しいのですが、じつは達成すると、サブストーリー全体のクライマックスともいえるようなサイドケースが遊べるようになるんです。内容もとても豪華に作り込んでいて、サイドケースのなかでは一番長く、遊びごたえもあるものです。大変だとは思いますが、ぜひ見ていただきたいと思います。
――ちなみに余談ですが、“さおりさんの生ケーキ裁判”のサイドケースは、某裁判ゲームのパロディ・オマージュのような印象を受けましたが、これは福田さんの前職が影響していますか?(笑)
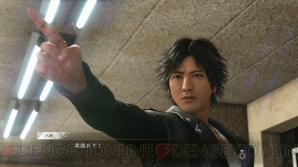
|
|---|
福田:どうでしょう(笑)。内容がコメディ裁判なもので、どうしても似てしまうというか……。ただ決め台詞など、ついクセが出てしまったということはあるかもしれません。
一同:(笑)。
下原:今回はメインのストーリーではリーガルサスペンスを盛り上げる、重厚なサウンドを目指しました。その一方でミニゲームやサイドケースでは、軽快で笑いを誘うようなサウンドもあります。そういったバリエーションもぜひ楽しんでいただきたいので、ぜひメインだけでなくサイドケースなど幅広いプレイをしていただきたいと思います。
あとはサウンドトラックが絶賛発売中ですので、ぜひチェックしてほしいなと(笑)。クリアしてから聴くと、八神たちの物語が自分のなかにまたよみがえってくると思いますので、ぜひ音楽にもハマっていただけたらうれしいです。

|
|---|
(C)SEGA
データ