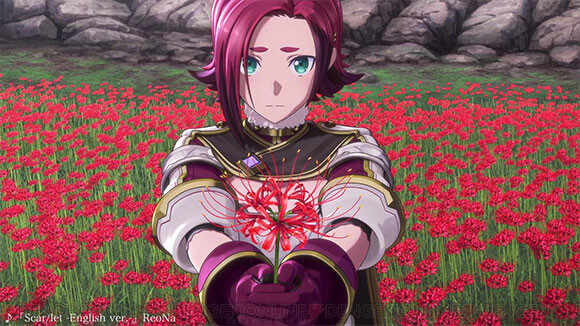『SAO』ゲームシリーズがもうすぐ10周年! 川原礫先生や二見Pたちキーマン4人の対談をお届け【その1】
- 文
- 電撃オンライン
- 公開日時
- 最終更新
2022年にアニメが10周年を迎え、来年2023年にはゲームシリーズが10周年を迎える『ソードアート・オンライン』。今回はおもにゲームの面にフォーカスして、ずっと支え続けてきた4人のキーマンによる対談をお届けします。
対談に参加していただいたのは、電撃文庫『ソードアート・オンライン』シリーズの著者・川原礫先生、川原先生の担当編集にしてストレートエッジの代表・三木一馬さん、『ソードアート・オンライン』ゲームシリーズの総合プロデューサーである二見鷹介さん、『ソードアート・オンライン インテグラル・ファクター』および『ソードアート・オンライン ヴァリアント・ショウダウン』のプロデューサーを担当する竹内智彦さんの4人です。
この対談は、複数回にわけてお届けする予定となっています。以降順次掲載予定ですのでお楽しみに!
アニメに続いて10周年を迎えるSAOのゲーム
――アニメが今年10周年を迎え、そして来年ゲームが10周年を迎えます。まずはそのことについて率直な思いをお聞かせください。
二見P:『SAO』のゲーム企画自体は2010年くらいからご相談させていただいていました。家庭用では6タイトル+1作(『アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏』)を作らせていただいておりますが、今思うとよくこんなハイペースで作れたなあ……と。2014年リリースの『ホロウ・フラグメント』のインタビューでは《アリシゼーション》編まで作りたいと言いましたが、実際に『アリシゼーション リコリス』までたどり着けてよかったなと思っています。10年続いたIPに携われて非常に嬉しく思っています。
竹内P:僕は2014年にサービス開始したアプリゲーム『コード・レジスタ』の運営開始後からプロジェクトに参加していて、主にアプリのゲーム制作をしています。『インテグラル・ファクター』からは海外向けにも展開しており、国内外問わず大きな反響があったので、世界中で人気のコンテンツに参加したという実感したことを覚えています。
三木さん:マーチャンダイズ的に言うと原作のあるゲームってファンアイテム的な側面もあるんです。その市場は当時から縮小傾向が垣間見えていたのですが、にもかかわらずヒットして来年で10年と話していられることが相当レアで、他にこういう作品はあまりない。原作付きのゲームってともすればゲームとして楽しいから買うのではなく、グッズとして買う人を狙っているタイトルでもあると思うんです。なのに『SAO』ゲームは、『SAO』が好きなだけではなく、バンダイナムコエンターテインメントさんのゲームが好きな人が支えているから10年も続いているんだと思います。
川原先生:アニメの第1期、そして家庭用ゲームの第1作目である『インフィニティ・モーメント』がうまくいかなければ『SAO』のアニメやゲームは10年も続かなかったと思います。この場をお借りして、改めて両方のスタッフさんに感謝を申し上げます。10年前のラノベ原作のゲームは、ほとんどがアドベンチャーでした。そんな中、ガチのRPGを出そうとしたことには驚きますし、あのボリュームのゲームをちゃんと作り上げたことにも驚きます。なぜあんなゲームを作れたのか、今思うと不思議ですらあります。
二見P:おっしゃるとおり当時ラノベ原作のゲームは大抵アドベンチャーで、だいたい2~3万本程度。10万~15万本で大ヒットでした。ところが『インフィニティ・モーメント』は25万本くらい売れています。なぜ3DのRPGにしたかというと、原作の魅力を最大限引き出すにはどうすればいいかと考えた結果ですね。
伊藤智彦監督が手掛けた1期のアニメがとても素晴らしい出来でしたので、ゲームもほぼアニメ設定がない状態で、それに負けないタイトルにしなくては、という若さゆえのチャレンジをしたのがいい結果に結びついたのかなと思っています。
川原先生:『インフィニティ・モーメント』ってPSP専売だったんですか?
二見P:専売でした。
川原先生:それでその販売本数はスゴイですね。
二見P:そうですね。国内だけだったのでスゴい本数だったなと思っています。
川原先生:実際、私PSPでプレイしていたんですけど、ゲームとしておもしろくて。フィールドでイノシシを狩ってるだけで楽しかったです。RPGとして土台のところがとてもよくできていると思いました。たくさんのプレイヤーが楽しんでくださって、『インフィニティ・モーメント』があったからこそ、その後の10年があったんだと思います。
二見P:当時は今ほど規模が大きくなくて、一本作るのに4年、5年もかからなかったんですよ。『インフィニティ・モーメント』の翌年には『ホロウ・フラグメント』を、その翌年には『ロスト・ソング』を出させていただいて、あまり間を置かず出せたのがよかったのかも知れないですね。
――当時『SAO』をRPGにしようと提案したとき、社内の反応はどうでしたか?
二見P:当時は社内からずっと「売れるのか?」と言われていました。『インフィニティ・モーメント』の限定版がすぐに売り切れてしまったとき、川原先生がTwitterで「限定版を再販できないか二見さんに聞いてみる」と無邪気なツイートをされていたのもいまとなっては懐かしいです(笑)。
川原先生:限定版は増やせないですよね(笑)。
二見P:そうなんですよ(笑)。つらかったんですけど何とか増やしたところ、好評をいただいたことで予約の数が増えたので、その数字を見て社内の風向きも変わりました。
川原先生:当時の僕は二見さんがひとこと言えば1万本くらいどこからかぴゅっと湧いてくるもんだと思ってましたよ(笑)。
ゲームオリジナルキャラクターを生みだす苦労とは
――ゲームのオリジナルキャラクターを作るとき、どのような考えで作られているのですか?
二見P:家庭用ゲームで一番大事にしているのは、“今回は誰をヒロインにして、どう助けるのか”です。ゲームでプレイヤーはキリトになるわけですから、プレイヤーだったらどんなヒロインを助けたいかを、お話のテーマと合わせて考えて提案させていただいている感じですね。もちろん『フェイタル・バレット』のように、例外的に自分が主人公のものもあります。
――お話のテーマと合わせるというのは、具体的にどういうことですか?
二見P:例えば最新作の『アリシゼーション リコリス』でいうと、“承認欲求”がテーマだったので、承認欲求が一番表われるようなヒロイン像を考えました。三木さんや川原先生とも相談して、最初は整合騎士がいいんじゃないかと言っていたんですが、メディナというキャラクターを提案させていただきました。
メディナはわかりやすくいうと、ユージオの代わりを務めてもらう役です。ユージオは幼少期からキリトやアリスがいましたが、いなくなった後は結構つらい体験していましたしね。それも踏まえたうえでメディナというキャラクターのベースは作っています。最初からキリトに出会えなかったユージオ役として。
もし、違った形で3人とあっていたらまた彼女も違う成長をしていたと思います
――その際に原作チームとはどのようなお話をされますか?
二見P:三木さんとはいつもヒロイン被りが起きないように話し合っていて、髪の色も本編のキャラとは一緒にならないように気をつけています。『インフィニティ・モーメント』のヒロインであるストレアを考えたときのことは特によく覚えているんですが、当時は『SAO』に年上キャラがそんなにいなかったのでお姉さんキャラになりました。フィリアはレッドプレイヤー(犯罪者)的なところから始まる感じですし、レイン・セブンは姉妹などなど。なるべく原作ではできない体験を目指してます。
三木さん:二見さんのこだわりポイントがニッチなんですよね。「これ大丈夫ですか、二見さん?」「大丈夫です、絶対受けます!」という攻防を日々やっています(笑)。
竹内P:僕も二見とそんなに考え方は変わらないんですけど、まずはキャラクターの立ち振る舞いから考え、続いて容姿を考えて提案をさせていただいています。たとえば『インテグラル・ファクター』のオリジナルキャラクターであるコハルは、アインクラッドを攻略する自分(プレイヤー)のパートナーとして作られています。ずっと自分に寄り添ってくれるキャラクターとして感情移入してもらうためには、あまり派手な要素を入れないほうがいいだろうと考えて、黒髪で、目立ちすぎる特徴は敢えて排除した感じに落ち着かせています。
――オリジナルキャラクターの中で完成までに苦労したキャラクターはいますか?
三木さん:僕はキャラクターよりも設定のほうにうるさかったですね。オリジナルキャラクターってゲーム側でその生い立ちから作られるものだから、あまりにも原作の設定にそぐわないものでない限りはNGにはならないんですよ。どちらかというと「『SAO』の作中における技術レベルではこういう設定は難しいです」ということにNGを出すことが多いですね。
あとは原作で本来登場しない人物を登場させるために時系列をアレンジしたりもするんですけど、その時系列のアレンジをきちんと納得できるものにしてほしいとか。例えば《アインクラッド》にリーファやシノンを出す場合、納得できる理由を作ってほしいとお願いしました。そういう部分のほうが紛糾した覚えはありますね。
――ではそういう設定部分でなかなかまとまらなかったタイトルはどれでしょうか。
二見P:一番となると『アリシゼーション リコリス』じゃないでしょうか。
三木さん:『アリシゼーション リコリス』か『インフィニティ・モーメント』のどちらかですね。『インフィニティ・モーメント』は《アインクラッド》に出てこないキャラを登場させようというところで紛糾したんですが、そういうキャラを出す仕組みさえ作ってしまえば、以降のタイトルでも同じ方法で登場させられたんですね。
ところが『アリシゼーション リコリス』の舞台である《アンダーワールド》はこれまでのようなゲーム世界ではなく、国による計画が絡んで作られた仮想世界でした。なのでこれまでのようなゲームライクな方法が使えなかったんです。そこで改めて本来は登場しないキャラクターを登場させるやりかたを考えるときに苦労しました。
二見P:『ホロウ・リアリゼーション』もなかなか大変でしたね。こっちは一度企画をやり直しました。本当は《アインクラッド》の1層からずっとやっていこうと思ったんですけど、無理だとなって新しいゲームを作ったんです。あとは『インテグラル・ファクター』の企画がすんなり通ったときは、「なんで竹内プロデューサーには優しいんですか!?」とクレームを入れたこともありました(笑)。
竹内P:ありましたね(笑)。
三木さん:また悪者になりそうなんでちゃんと説明しますね(笑)。それは最初にお金を掛けるコンシューマのビジネススタイルと、最初に無料でプレイをして運営を継続できるかどうかで考えているアプリゲームのビジネススタイルが違うからなんです。またどれくらいプレイヤーが腰を据えてプレイをするかというプレイスタイルの問題もコンシューマとアプリゲーで大きく違っていると思うんです。しっかりと掘り下げたものを作らないとコンシューマのプレイヤーの期待に添えないと思うので、対応を変えています。
二見P:『ホロウ・フラグメント』でサチを登場させようとしたときも大変でした。現場のスタッフがみんな「できません」て言ったんです。なぜかというと、サチが生きてたらキリトは絶対攻略をやめてサチを守り続けるよね……と思ったからです。
すると三木さんがメールで、『SAO』アニメ1期のパッケージ9巻の特典小説『ザ・デイ・アフター』をベースにしようと提案いただいて。この特典小説は新生《アインクラッド》でアスナがサチの亡霊と出会うという内容なんですけど、「これに近いシナリオで二見さん書いてください。」って言われて、思わず「自分?」と思いました。あのときは本当に大変でしたね。シナリオを深夜2時くらいに三木さんと2人で作ってました。
アニメ制作サイドとは持ちつ持たれつの関係
――アニメ制作サイドとはどのような連携をされていますか?
二見P:ワールドについてはゲームのほうでかなり自由にやらせていただいていますが、オリジナルの衣装や設定などはアニメ制作サイドと共有させていただいて、使えるところは使うといった感じです。もちろんアニメのほうで僕たちの作った設定を使ってもらうこともあります。
――制作の都合上、どちらかが先行して設定を作らなければならない状況もあると思いますが、その場合はどのように対処されているんですか?
二見P:例えばアニメ1期、2期のゲーム内UIの制作には僕らがアドバイザーとして入っていました。映画『オーディナル・スケール』に登場したアインクラッド91層のボス、《カオス・ドレイク》は『インフィニティ・モーメント』92層のモンスターを伊藤監督がモデルにされたそうです。マップに関してはオリジナルでやらせていただいていますね。その場合でも資料は共有しています。あとは2019年に行なわれたイベント“SAO -エクスクロニクル-”でソードスキルを体験するアトラクションのキャラクターモデリングや、『オーディナル・スケール』に登場するユナのイベントで行われたライブに使われているモデリングなども提供しています。
――アニメに先行してアフレコを行なう場合、キャスティングはどのように決められているのでしょうか?
二見P:ゲーム先行で世に出たユージオとアリスに関しては、裏でアニメの収録も行なわれていて、川原先生にもチェックしていただきながら同時並行で進めていました。『インフィニティ・モーメント』には《GGO》に登場するシノンが登場していますが、その時点でシノン役に沢城みゆきさんが決まっていて、ドラマCDも収録されていましたから、特に困ることはなかったです。
――オリジナルキャラクターの声優さんについてはゲームサイドで決められているんですか?
二見P:ゲームサイドで音響と相談して決めています。『インフィニティ・モーメント』のストレア役に三澤(紗千香)さんを起用したのは、三木さんが関わっている『とある魔術の禁書目録』や『アクセルワールド』に登場するキャラクターを三澤(紗千香)さんが演じていたからですね。『SAO』と同じタイミングで登場するので起用したらおもしろいんじゃないかという話をさせていただきました。『ホロウ・フラグメント』のフィリア役には石川由依さんを起用しています。これは僕が『進撃の巨人』が好きでミカサのファンだったこともあり、ミカサを演じられている石川さんと仕事をしたくてお願いしました(笑)。その他、ゲームの制作現場から上がってきた意見を反映したこともあるといった感じですね。
――ゲームのオリジナルキャラクターで好きなキャラは誰ですか?
竹内P:『インテグラル・ファクター』のコハルは殿堂入りですね。おかげさまでプレイヤーさんにもすごく受け入れられているキャラクターになって、コハルが涙を流したり、危機に陥ったりするシーンがあると一部のプレイヤーさんからお怒りのコメントをいただいたりもします。
あとは『ヴァリアント・ショウダウン』のライラですね。彼女についてはあまり多くの事前情報をお伝えしないようにしていて、実際に敵か味方か分からない登場の仕方をします。彼女の人となりについてはプレイヤーさんと一緒に紐解いていく形になるので、今後どのように育って受け入れられていくのか楽しみにしています。
二見P:みんな好きですが、特に印象に残っているのは『ホロウ・フラグメント』のフィリアですね。先ほど申し上げたとおり、声を石川由依さんにお願いして収録にも立ち会いましたがとても素晴らしい演技をしていただきました。フィリアのセリフやアクションの内容も僕のほうでかなり修正を入れたこともあって、かなり印象に残っています。
原作の設定をゲームシステムとして翻訳する難しさ
――原作設定をゲームシステムに落とし込む際にはどのようなことを考えられていますか?
竹内P:ゲーム的な制約があるのでそのままというわけにはいかないんですけど、気をつけているのは原作と名前は同じだけど別物になってしまわないように……というところですね。『ヴァリアント・ショウダウン』では原作でおなじみのスイッチという機能が入っていますが、あれは『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア(以下、星なき夜のアリア)』に登場するスイッチに関する川原先生の解説ツイートを元にして仕様を決めました。
あの時先生は攻撃的なスイッチと防御的なスイッチについて説明されていたのですが、それを参考にして『ヴァリアント・ショウダウン』のスイッチに落とし込んでいます。味方の操作キャラを入れ替えて連続攻撃を繰り返していくことが攻略法の一つになっているんですが、それとスイッチを結びつけて、普段は起こりえないソードスキルの連続攻撃が可能になっているんです。また敵の攻撃を弾き返す挙動は防御的なスイッチとして落とし込んでいます。このスイッチの解釈をキチンとすることをチームとして意識しています。
二見P:僕は原作のSAOを読んだ経験を大事にしてゲーム作りをしています。ただ、設定通りやりすぎるとお客さんから怒られたりするんですよ。『インフィニティ・モーメント』をやっているときに川原先生から「ソードスキルの硬直時間をなくしてほしいんです」と言われました。
川原先生:ゲームやってるとソードスキルを連発したくなるんです(笑)。
二見P:それで『ホロウ・フラグメント』や《ALO》を舞台にした『ロスト・ソング』では、ソードスキルがキャンセル可能でコネクトできるシステムを実装しました。設定を守りすぎるとゲームプレイとして気持ちよくないという川原先生のご指摘を生かした形です。
川原先生:ソードスキル後の硬直時間のいらだたしさ。原作のキリトたちが感じていることを追体験できたのはすごくよかったと思います。でも実際のゲームでは本当につらい……。私が想像して書いていた以上のつらさを味わいました。
二見P:あと『インフィニティ・モーメント』は戦闘がオートアタック方式で、MMOをやったことがあるプレイヤーは普通に受け入れてくれたんですけど、アニメから入ったプレイヤーからは「これは『SAO』じゃない」と言われました。『SAO』に登場するゲームのシステムを現実のゲームに落とし込むときにはどう翻訳すればいいのか、毎回苦労しています。
川原先生:あの頃のMMOをずっとやってきている人からすると、オートアタックはむしろ標準で通常攻撃は自分ではできないものという認識でしたね。でもあのゲームから入った人は通常攻撃を自分でやりたいとは思うだろうなとは感じました。
二見P:そもそも『SAO』はフルダイブのゲームですからね。フルダイブですらなく擬似MMOの時点でなにか言われるなと想定していましたし、実際言われました(笑)。リーファやシノンを出すことについても批判があることを覚悟して出していました。ただ10年続けていくうちに、ようやく技術が表現したいことに追いついてきたかなという実感はあります。
――ゲームだからできること、ゲームだからこそ表現できる『SAO』の魅力はなんだと思いますか?
竹内P:アニメでは描かれないキャラクターの側面が描けることだと思います。ゲームならではの組み合わせで会話が発生することもありますが、アニメで会話が発生していない人物同士の会話が見られるのはおもしろいのかな、と思います。
――アニメでは尺の関係上、サブキャラ同士の会話をするのは難しいんですが、ゲームだとそこまで拾い上げられるのがいいですね。
竹内P:例えばキバオウがメインで話が進むシナリオイベントもあったりします。キバオウが好きという方もいらっしゃるので、そういう部分を楽しんでいただけているのかなと思います。
二見P:キリトがその話のヒロインたちを助けていくという物語を、プレイヤーが追体験できることじゃないでしょうか。しかも原作通りではなく自分がキリトとして、それぞれのヒロインと関わっていける。それはゲームだけの魅力だと思います。
――二見さんと竹内さんにお伺いします。『SAO』に限らず原作のある作品をゲーム化するうえで「これだけは守っている」ことは何でしょうか?
竹内P:先ほど色々なキャラクターを登場させられるのがゲームの魅力だと言いましたけど、ゲームならではの表現をさせていただくうえで、原作のイメージを崩しすぎないようにすることには気をつけていますし、特定のキャラクターを意図的に貶めることはやってはならないと思います。
――キャラクターの扱いは難しいですよね。解釈が違うことで不満を抱く人もいますし。
竹内P:他には、アニメでの登場頻度が少ないキャラクターでも積極的に登場させるようにはしています。例えば、『インテグラル・ファクター』では1回のシナリオに登場するキャラクターも多いので、色々なキャラクターを登場させたり、さらにはシナリオのメインキャラクターに据えたりもしています。
二見P:僕は小説を読んだときの体験と、ゲームでしかできない体験を大切にしています。プレイヤーにキリトになったような体験をいかに与えられるかを重要視しています。たとえば『インフィニティ・モーメント』では誰と一緒にアインクラッドをクリアしたかによって、エンディングが変わります。キリトとして誰を選ぶかはプレイヤー次第ということです。
また『アリシゼーション リコリス』では誰をパーティに入れるかをプレイヤーが自分で選ぶことができるんですが、それもまた自分の物語を誰と一緒に紡いでいくのかを選ぶことになります。そういうゲームとしての自由度は意識しています。また、自分がファンだったら何が見たいのか? 体験したいのか? 原作通りなのか、バトル体験なのか、新しい物語なのか……などなど。作品によって提供方法は変わりますが、ここでしかできない体験を目指しています。
ゲーム10周年の今だから言えること
――『SAO』のゲームを作る際に影響を受けた、もしくは参考にしたゲームはありますか?
二見P:『インフィニティ・モーメント』を作る際には『ファイナルファンタジー XI』や『ファイナルファンタジー XIV』を参考にしました。弊社のタイトルでいうなら『.hack』も参考にしています。あと『フェイタル・バレット』を作る際は、『ボーダーランズ』や『ロストプラネット』の影響を受けています。もちろん、ゲーム設計を参考にするという意味ではなく、プレイフィールのイメージの話です。あとはハクスラ要素として『Diablo』も参考にしています。
竹内P:僕の場合は特定のタイトルを参考にするということはなく、類似するアプリタイトルのトレンドを参考にすることが多いですね。普遍的にあるとすればBGMや楽曲のほうは参考にしたタイトルはあります。『ヴァリアント・ショウダウン』のバトル曲を作る際には、『SaGa』シリーズなどの熱い戦闘音楽をたくさん聴きました。あとは二見が担当しているコンシューマの『SAO』ゲームシリーズを参考にしていて、キャラクター同士の関係性や描き方は取り入れることがあります。
――入れたかったけどできなかった要素や、ボツ案などはありますか?
竹内P:『インテグラル・ファクター』はMMORPGなので周囲に他のプレイヤーさんもいるわけですが、そのプレイヤーさんとスイッチさせようというアイデアがあったんですけど、技術的な問題から諦めました。モバイルだと通信環境が一定じゃないですし、プレイヤーによって端末の環境が違うため同期を取るのが難しく、自分がスイッチしたつもりでも、相手のプレイヤーさんからの表示が追い付かない可能性がありました。そこでコハルとのスイッチに限定しました。
二見P:『インフィニティ・モーメント』のシナリオですね。実は、ラスボスがキリトの想定だったんですけど、ボツになりました。“アスナを救えなかったキリトが作った《アインクラッド》”というアイデアをベースに、最後にキリトが待ち受けているという提案をさせていただいたんですけど、川原先生と三木さんに「キリトにこれ以上つらい思いをさせないでほしい」と言われました。
――来年で『SAO』のゲームも10周年を向かえますが、10年の間にはさまざまな出来事があったと思います。今だから言えることや、ゲーム制作にまつわるこぼれ話はありますか?
竹内P:二見との会話で、コハルを闇落ちさせるという話をした記憶があります。何かすごくつらいことに遭って金髪になって帰ってくるというネタです(笑)。そのときは「それもありかな」と考えていたのですが、結局やらずにいます。それをやって一定数の人が悲しむ結果になるのは嫌だなと思ったので封印したのですが、いつかやるかもしれないです(笑)。
二見P:『オーディナル・スケール』をどうゲーム化するのかについてはずっと考えています。でも難しいんですよね……。《アリシゼーション》編までゲーム化できてすごく幸せな10年だったなと思いつつも、『オーディナル・スケール』というタイトルをどうゲーム化するかについては難しく、もう5~6年経っているという状況です。
――ゲーム制作サイドから原作チームに聞いてみたいことはありますか?
二見P:川原先生にお聞きしたいのですが、『SAO』シリーズでのキリトは何歳まで登場させるおつもりですか? 最近のシリーズでは随分大人びてきていますが、冒険心溢れるいちプレイヤーとしてのキリトは、読者はいつまで楽しめるのでしょうか?
川原先生:『SAO』というタイトルの中では、キリトが10代のうちに書きたいことを書き切りたいと思っていますね。
二見P:じゃあ22歳くらいになったキリトは?
川原先生:それはどこかで書くかも知れませんが、『SAO』というタイトルの作品ではないんじゃないかなあ……。あんまり現実的なことに踏み込ませたくないので。進学をどうするかくらいは書けても、就職みたいな現実的なことはあまり書きたくないですね。
竹内P:キリトにとって茅場晶彦は結局どのような存在なんでしょうか? 茅場はキリトをデスゲームに閉じ込めた張本人ではありますが、一方でキリトにとって大きな存在として位置づけられていますので、実際のところどうなのかお聞きしたいと思っていました。
川原先生:それについては原作でもまだはっきりしたことは出ていませんし、私もそれを正面切って書くときまでは明確な答えは出せないですね。ただ現段階で私の感触からすると、キリトにとって大切な人が《SAO》の中でたくさん死んでしまったわけですから、茅場への憎しみはあると思います。
同時にキリトの中では、自分がもっと上手くできれば全員助けられたのではないかという思いもあるんです。まあヒロイックな思い上がりではあるんですけど。茅場を憎むことによって自分の責任を薄めてしまうのではという意識も多分あると思います。
そしてもうひとつ、状況が違えば自分も茅場と同じことをやっていたのではないか、茅場のやりたかったことは理解できるという思いも多少はあるんじゃないかと。真の異世界を創造してそこで最終的に自分も死ぬというのは、ゲーム制作者としては誰もなしえたことのない究極のゲーム創造ですから、もちろん、倫理的には許されない犯罪行為ですけど。
現段階で言えば、憎みたいけど憎みきれない存在ですね。しかし今後、原作でキリトと茅場が直接対決することになった場合は、私にもどうなるかわかりません。
――少し気の早い話ですが、『プログレッシブ』をゲーム化する予定はありますか? もしゲーム化するとしたらどんなことをしてみたいですか?
二見P:『プログレッシブ』のゲーム化ですか……なるほど。原作の隙間のところでどうキリトとアスナを描いていくのか。何があったのかを描いていただくのは1ファンとしてとても楽しみです。
ゲームが来年10周年ということで、当時アニメ・ゲームを見ていた中高生が24~28歳ぐらいになります。私が『SAO』のゲームを企画したころは同じ年齢ぐらいだったので、これからは若い世代が考える“僕の! 私の!”『SAO』を企画して進められる土台を作って、応援するだけにしたいです!
竹内P:『プログレッシブ』については一部『インテグラル・ファクター』で再現しようと試みていましたので、その中で『プログレッシブ』の要素を強めていく可能性はあるかも知れないです。ただ現時点で『インテグラル・ファクター』は『プログレッシブ』より相当先の階層を進んでいるので、その要素をどう落とし込むかについてはこれから考えていきます。今までなかなか再現できなかった『プログレッシブ』要素についてはできるだけ取り込んでいきたいですね。
■『ソードアート・オンライン 10th Anniversary Box』を購入する
■『ソードアート・オンライン ヴァリアント・ショウダウン』の予約・事前登録をする
(C)川原 礫/アスキー・メディアワークス/SAO Project
(C)2014 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/SAOⅡ Project
(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
(C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります