2009年9月3日(木)
【CEDEC 2009】『ドラクエ』は藤子さんになれたらいい――堀井氏が基調講演
2.ドラゴンクエストIXのゲームデザイン
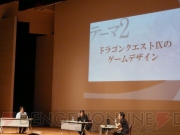
|
|---|
このテーマについては、『ドラクエIX』でディレクターを務めた藤澤氏が主に説明を行った。まず開発当初の決定事項としてあったのが、“DSでマルチプレイのできる『ドラクエ』を作る”ことであったという。これを開発のコンセプトにシフトすると、“ずっと遊べる”、“みんな遊べる”であり、『ドラクエIX』はこれを柱として制作されたとのこと。
しかし、このコンセプトの上に『ドラクエ』を制作するにあたって、藤澤氏は大きな懸念があったという。これまで多くの人にとって『ドラクエ』は、“エンディングまで50時間くらいで遊ぶもの”であり、“1人でも攻略する”ものであったと語る藤澤氏は、「これまでのファンに、『ドラクエIX』のコンセプト受け入れてもらうにはどうしたらいいか?」を非常に意識したとのこと。
“ずっと遊べる”ことのため考えられたのは、エンディング後も遊べるゲームデザイン。このゲームデザインを完成させるため、藤澤氏は、“エンディング後の世界を描くこと”、“移動手段が増えること”、“強くなるモチベーションを失わせないこと”の3つを重視したそう。3つ目の“強くなるモチベーションを失わせないこと”については、宝の地図の導入であり、これはみんなで遊べるためのゲームデザインにも密に連結することが話された。

|
|---|
| ▲また『ドラクエIX』は、ハードをDSにしたこともあって、シナリオを削らざるえない状況になったそう。堀井氏も「ずっと遊べるゲームというのは、システムで作るしかないなと思った」と話す。藤井氏の話では、一時はかなりシナリオを削るという選択も浮かんだそうだが、ストーリーがあまりに少ないのは『ドラクエ』でなくなるという危機感を覚えて、今の形に落ち着いたようだ。 |
また藤澤氏は、プレイヤーが電源を入れるきっかけとして、“Wi-Fiショッピング”、“すれちがい通信”といった要素を用意した。“みんなで遊べる”というコンセプトとも密接なシステムである“すれちがい通信”については、「まさかこんなに(流行ることに)なるとは思わなかった」と市村氏も藤澤氏も口をそろえる。市村氏らはもともと、コミュニケーション促進の一助として“すれちがい通信”を採り入れたようで、現在のような大流行はうれしい誤算でもあったようだ。
“みんなで遊べる”を実現するゲームデザインとしては、“すれちがい通信”の他にも、クエストや錬金などの難易度が高いゲームシステムを入れたことが挙げられた。これまで“ゲーム外で情報を仕入れないと攻略できないことは、極力入れない”という方針で作られてきた『ドラクエ』シリーズに対し、『ドラクエIX』では難易度の高い要素を入れることで、先行している人の情報が必要になる状況をあえて作ったと藤澤氏は話している。これにより、みんなで遊ぶ感覚を作り出すことを図っているとのこと。
藤澤氏は、以上のことから『ドラクエIX』が、これまでのスタートダッシュ型ゲームから、ロングラン型ゲームへの質的変換を行ったと話す。この理由を、従来のシリーズ作では初期の売り上げが全体の9割を占める状況にあり、『ドラクエIX』では1年経っても売れるゲームにしたかったのだと説明している。これについて藤井氏は、まだ発売後2カ月弱で結論はでないが、今のところうまくいっていると考えているようだ。
![]()
- ▼『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』
- ■メーカー:スクウェア・エニックス
- ■対応機種:DS
- ■ジャンル:RPG
- ■発売日:2009年7月11日
- ■価格:5,980円(税込)
- ■『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』の購入はこちら
-


