2019年5月3日(金)
『FFXIV』リターン・トゥ・イヴァリース完結記念! 秘話満載で贈る松野泰己氏&吉田直樹氏特別対談【電撃PS】
『ファイナルファンタジーXIV(以下、『FFXIV』)』のアライアンスレイドシリーズ“リターン・トゥ・イヴァリース(以下、RTI)”――。『ファイナルファンタジータクティクス(以下、FFT)』や『ファイナルファンタジーXII(以下、FFXII)』の舞台である“イヴァリース”を『FFXIV』の世界観にマッチさせたRTIは、物語やバトル、景観などなどひっくるめた総合的なクオリティの高さが話題を呼び、世界中で大きな反響を生みました。

|
|---|
これまで電撃オンラインでもいくつかの記事を掲載してきましたが、今回はある意味、RTIの締めくくりとも言える企画。ゲストクリエイターとしてRTIの制作にかかわった、“イヴァリース”世界の産みの親である松野泰己さんと、『FFXIV』プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹さんによるスペシャル対談――リターン・トゥ・イヴァリースの制作秘話をふんだんに盛り込んだ、ファン必見のインタビューをお届けします!

|
|---|
なお、本記事は電撃PS4月27日号に掲載した対談企画の全文バージョンとなります。誌面掲載時のじつに2倍以上の内容が詰まっておりますので、どうぞごゆっくりご堪能ください。
リターン・トゥ・イヴァリースの魅せ方――松野さんによるシナリオ構築の考え方とは
――2年にも及ぶ“リターン・トゥ・イヴァリース(以下、RTI)”が、パッチ4.5でついに完結しました。ファンとしてはかなり見どころたっぷりのシリーズでしたが、松野さん・吉田さんの手応えや、プレイヤーさんの反応に対する感想をぜひお聞かせください。
松野泰己氏(以下、敬称略):おおむねプレイヤーさんの反応は予想どおりでしたが、やはり『ファイナルファンタジータクティクス(以下、FFT)』を遊んだことがない人には、シナリオが伝わりにくい部分もあったかなと思っています。もちろん、『FFT』をそのまま伝説として取り込んだわけではなく、未プレイの方のためにもテキストをふんだんに用意し、NPCのセリフを読んでもらえばガレマール帝国に伝わるゾディアックブレイブストーリー伝説のおおよその流れがわかるようにはしていました。ですが、予想以上に『FFT』ファンの方たちが盛り上がってしまったがゆえに、話は理解しているけれど“置いてきぼり感”に遭遇しているというプレイヤーさんも少なくなかったのかなと。
吉田直樹氏(以下、敬称略):最終章を仕上げる直前に、ちょっと悩まれていましたよね。じつは、長いシナリオに『FFT』を知らない人がついていけないかもしれないという懸念から、シナリオをもっと短くした案もありましたよね?
松野:そうですね。その短いバージョンを作ったのには2つ理由があって。1つは吉田さんがさきほどお話しされた“『FFT』を知らない人がついてこられるか”という懸念。もう1つは、“そこを差し引いても単純に長過ぎた”というところです。最終章を執筆している最中も、自分でも「これは長いな」と思いました。『FFXIV』とはいえ開発のコストには限りがありますし、織田(※1)さんも悲鳴をあげていましたから(笑)。「これは縮めなきゃいけないな」と。なので、一度バッサリと短くしたんですよ。
吉田:しましたね。どんどんカットしていって……。
松野:「フランも登場なしで!」とか言ったこともあります。そうしたら、吉田さんと織田さんから、「さすがにマズイですよ!」とストップがかかりました(笑)。
――ひょっとしたらフランが出てこない可能性もあったわけですね……!
吉田:それは大丈夫です。僕が大反対しましたから(笑)。5.0で“ヴィエラを出す”と決まった段階で、RTIと噛み合わせないともったいないですし。フランのキャラクターモデルも全部用意していたのですけど……そんな状況で「バッサリいこう」と言われて、さすがに「ちょっと待ってください!?」と焦りました。
一同:(笑)。
松野:じつは、吉田さんに言う前に鈴木(※2)くんには相談していたんです。「ここバッサリ切っていい?」と言ったら、「えぇ~」と言いながらも「松野さんがそう判断されるのでしたら、しょうがないですよ」と言ってくれましたよ?(笑)
吉田:その話、僕知らないですよ(苦笑)。
松野:逆に、開発チームが自発的に盛ってくれている部分も多いんですけどね。“楽欲の僧院 オーボンヌ”は、森から修道院に入ってミュロンドに行く……という3つのステージで構成されていますよね。「これはボリュームが多すぎない? 森は背景にして修道院からスタートでもいいよ?」と提案したんですけど、「いえ、森からやらせてください」と返ってきて。
吉田:それは、僕が“長いのに画が変わらないマップ”というのが嫌いだからですね。奥へ進んでいったら、体験とともに画も変わるというのがゲームのいいところだと思っていまして。通常ダンジョンでも前半・中盤・後半で環境が変わるようにお願いしています。RTIのその部分に関して僕は何も言っていませんが、彼ら自身が「やるんだったらそこまでやらないと」と考えてくれたのだと思います。
――クリスタルタワーやシャドウ・オブ・マハといった過去のアライアンスレイドシリーズと比べても、RTIの画変わりは本当に劇的ですね。
松野:たぶん、これまでの倍ぐらい手間がかかっていると思います。
吉田:スタッフたちも『FFT』や『ファイナルファンタジーXII(以下、『FFXII』)』が大好きなんです。今回、ある程度できた段階で松野さんに、メールで“楽欲の僧院 オーボンヌ”の入口付近のスクリーンショットを送ったんですよ。「デキがいいんですよ!」って(笑)。
松野:ちなみにこれ(下の写真)は、私が最初に送った“楽欲の僧院 オーボンヌ”のイメージ資料(コラージュ)です。ざっくりとしたものではありますが、「こんな感じで作って」という見本ですね。

|
|---|
オーボンヌ修道院のビジュアルは、やはり『FFT』のイメージがとても強いんですよ。『DISSIDIA FINAL FANTASY NT』でも“教会”を再現していますよね。だから、私が言わないと、スタッフはきっとそのままのイメージで作ろうとしてしまうと思ったんです。「RTIはオリジナルとは別物なので、変えていいんだよ。むしろ変えてほしい」みたいな意味で、このビジュアルを出しました。そうしたら、実際に出来上がったグラフィックがあの美しさですよ。開発の人たちは本当に上手く解釈して作ってくれているなと思いました。
吉田:僕も今回はとくにイヴァリースの雰囲気を感じさせるデザインが息づいていると思いました。好きな人にしかわからないかもしれないですけど、クオリティが高いだけではなくしっかりリスペクトされていて。元の作品の世界の中にいると勘違いできるぐらいのレベルで、本当によくできています。
ちなみに『FFXII』は、もともと影の部分まで細かくテクスチャを描き込んでいます。それを『FFXIV』のライティングで再現するとなると、それを意識して調整しないと似ないんです。ゲームが好きなスタッフがいて、そこにゲームが好きな松野さんに参加してもらって、みんなで好きなゲームを作ろうと進んでいったのがよかったんだと思います。
――こだわりという部分では、死都ミュロンドは“ディープダンジョン「死者の宮殿」”の最下層と似た雰囲気だなと感じていたのですが、何かつながりはあるのでしょうか?
松野:「ミュロンドを死者の宮殿の最下層に似せてくれ」と、私がお願いしました。「ひょっとしたら、死者の宮殿を潜っていくとミュロンドに行けるんじゃないか」と想像してもらえたらいいかなと。

|
|---|
これは本当に小ネタなんですけど “楽欲の僧院 オーボンヌ”で聖騎士アグリアスを倒したあとに、魔法陣が開いてミュロンドにワープしますよね。そのとき、フランに“カオスゲート”という言葉を言わせています。これは、『タクティクスオウガ』に登場するゲートの名前で、あの魔法陣の画も『タクティクスオウガ 運命の輪』での紋様そのままなんです。『オウガ』好きなら気づくかなと。“そのゲートをくぐると死者の宮殿の地下に行ける”というのが、余韻の1つになればいいなと思って用意しました。もちろん、それを公式設定というつもりはないですが、想像できる幅は残しておきたかったんです。これも含めて、私の意をよく汲んでいただいて……グラフィックは本当にがんばってくれたと思います。
――イヴァリースアライアンスの世界観にはいろいろな可能性があって、まだまだ機会があればその先を見てみたいと思いました。
松野:私は、基本的に飽きっぽくて新しいもの好きなので、あまり過去のものを振り返るよりも、新しいものを作りたいと思っちゃうんです。ただ、その一方で、この歳になってくると「あと何年働けるだろうか」と考えるようになってくるんですね。引き際とかいう話ではなくて、この歳になると結婚式よりも葬式に参列する機会が増えまして、「あと何年モノを作っていられるのかな」と死を意識するようになりました。Twitterとかで、ときどき「『オウガ』や『FFT』等の新作待っています!」なんて言われちゃうと、「死ぬ前に作らないといけないかな」とか思っちゃう自分もどこかにいるんです。
――吉田さんとしては、RTIを終えた感想はいかがですか?
吉田:まず前提として、僕は濃い『FFT』ファンです。そんな僕にとって、最初にいただいた“ラムザたちがアルテマに勝てなかった世界”という原稿は、いちプレイヤーとしてファンとして、とても痺れました。
それと同時に、本当に『FFT』を好きであるがゆえに“原作以外認めない”と思っている方や、「今回のRTIを見て『FFT』の真相だ」と解釈される方もいるはずです。この辺りには、気を遣う必要があるだろうと考えていましたが、蓋を開けてみれば、否定的な声は、驚くほどありませんでした。
松野:これは以前から公言しているんですが、『FFT』の物語はオリジナル版で完結しています。『ロード オブ ヴァーミリオンIII』のテキストで、その後の話に少し触れたことはありますが、ラムザたちは『FFT』での戦いで生き残りイヴァリースから離れて別の場所で冒険している……というのが正史なんです。なので、あくまで『RTI』の物語は別物であるというのが前提です。
少し話が逸れますが、スクウェア・エニックスの執行役員だったころに株主総会の質疑応答で「ラムザたちは生き残ったんですか?」という質問を受けたことがありました。答えは、もちろん「生き残りました」なんですが、それが世間に伝わっていなかったのは作り手としてはまだまだ未熟だったなぁと深く反省させられました。
吉田:そんな出来事が……。
松野:アンケートを取ったわけではなく、ネットなどを見ての想像ですが、おそらく半分ぐらいのプレイヤーさんは“ラムザたちは最後に死んだ”と思っているんですよ。正史として“生き残って別の場所で冒険している”ということは公言していますが……。それでも全滅したと思っているプレイヤーさんが多かったので、せっかく『FFXIV』で新しくやるんだったら、“全滅を前提とした場合の物語を作ってみよう”と。パラレルではあるけれど、心の中で完結していない方たち向けに、もう一度ラムザたちの最期を描いてあげようというアイデアがありました。
――松野さんに仕事をお願いすると決まったときに、『FFT』をモチーフにするか、『FFXII』をモチーフにするか、完全オリジナルでいくかという3つの案が用意されていたとうかがいました。吉田さんは即答で『FFT』を選ばれたとのことですが、吉田さんにとって『FFT』はどういう作品なのでしょうか?
吉田:“衝撃”でした。そもそも『伝説のオウガバトル』で痺れ、『タクティクスオウガ』で打ちのめされて、「こんなにすごいゲームを作れる人がいるのか……、俺ゲーム業界で生きていけるんだろうか……」とショックを受けました(笑)。それから松野さんが当時のスクウェアに移籍されて、『ファイナルファンタジー』のシミュレーションRPGである『FFT』を生み出したわけですが、演出と遊びの融合がすごすぎて、さらなる衝撃を受けたのを覚えています。
そして、今回ゲストクリエイターとして参加していただけることになったわけですが、さきほど松野さんが“プレイヤーさんのエンディングの解釈が2つに割れている”とお話されていましたよね。僕は感覚的に“松野さんが新しくそこを深掘りすれば、松野さんなりの新しい答えがまた出てくるんじゃないか”と感じたのだと思います。ちょうど『FFT』20周年でもありましたし、迷わずにお願いさせていただきました。
松野:そもそも、吉田さんはエンディングでラムザの生死はどう捉えていました?
吉田:僕は、生きていると思っていました。ラムザとアルマがチョコボに乗って出てきたところで、僕はストレートに生きていたんだと受け取りましたよ。
松野:あれを幻覚と思っている方が意外と多いんですよね。
吉田:僕はむしろ、ディリータのラストシーンが正史なのかどうかが気になりました。
松野:それも昔どこかのインタビューか何かで答えた気がしますが、ディリータもオヴェリアも、あのときあの場所では死んでいません。ただ、その後にオヴェリアは死に、ディリータは孤独に治世をしていくことになります。
そうした誤解もあってRTIでは、“ディリータをちゃんと描く”という裏テーマがありました。特に、ディリータはラムザをどう考えていたのか。やはり利用するべき対象だったのか、それとも計算無しで助けようとする文字通りの親友なのか。私のなかでのディリータは、もともとRTIのような情に厚いキャラクターというイメージだったんですけど、そう思ってない方もいらしたようでして。「自分が知っているディリータは、もっとイヤなやつだった」みたいな。
吉田:そうなんですね。僕はディリータをイヤなやつだと思ったことはないですけど……。
松野:それはプレイした時が大人だったからでしょうね(笑)。当時、中学生や高校生だった方からすると、利己的なイヤなやつという印象のようです。
吉田:あぁ、なるほど! だとすると、大人になって再プレイしたら、見方がだいぶ変わりそうですね。
松野:ということで、『FFT』をモチーフとするにあたって、自分の中の命題として“エンディングの解釈と、ディリータの描き方”は追求していこうと思っていました。
ただし、イヴァリースの世界を『FFXIV』に持ち込むにあたって、織田さんや石川(※3)さん、前廣(※4)くんたちが作り上げてきた『FFXIV』という世界観を崩さないことが絶対的な前提です。「世界観が合わない」と言われてしまうような、いかにもなコラボレーションは絶対にしたくありませんでした。そこを踏まえて、“『FFXIV』にどうイヴァリースを取り込もうか”という部分を、すごく真剣に考えました。そのために、織田さんとは密に連絡を取り合って、“やっていいことと悪いこと”の判断確認を徹底していましたね。

|
|---|
吉田:そこは、本当にものすごい手間をかけていただいたと思います。
松野:例えば、ハイデリンでは、人が死ぬと魂、すなわちエーテルがエーテル界に還っていきます。ですが、“切なる願い”という形でラムザやアグリアスたちは魂の一部を地上に残してしまった。本来ならエーテルとしてハイデリンに還っていくはずなのですが、一部だけが聖石に残ってしまっている。仏教的に言うと“成仏できない”状態のままなわけです。こうした設定を織田さんに提案し、OKかどうかを議論して固めていきました。
吉田:RTIが始まる前から、『FFXIV』には前廣が入れた“ダルマスカ”などの言葉があったんですが、それをちゃんと、存在するものに昇華していただいたんです。“イヴァリース”を溶け込ませてもらった以上に、“ハイデリン”という世界を広げてもらった印象ですね。
また、織田とすり合わせていくなかで、「世界に溶け込ませるために必要な歴史があるなら、改めてそれを作ろう」という方針を話し合いました。白紙だった地図が違和感なく埋まっていった感じがあって、まるで最初からそう決まっていたかのように世界が広がっていって……。その手腕は、本当にお見事だと思っています。
松野:企画自体のスタートは『FFXIV』の設定資料集(※5)の1巻が出る前だったのですが、出たと同時に、ガッと読み込みました。別の世界に新しい歴史を組み込む場合、書かれていない部分というか、隙間をいかに見つけるかが重要なんです。書かれたことはもうその時点で事実になってしまうので、そこには手出しができないじゃないですか。その隙間を読み取って、「ここをいじっていい?」と聞いていきました。ハイデリンの地図も、各所が雲で覆われていることをいいことに「ここもらっていい?」「ここダルマスカにしていい?」みたいな(笑)。
吉田:「大丈夫です、その下は何も決まってないんで」とか話していましたね。
一同:(笑)。
――その結果、『FFT』だけでなく、『FFXII』も含めたイヴァリースアライアンスの世界が見事に『FFXIV』に溶け込んでいると感じます。それを象徴するのが新種族ヴィエラの実装だと思いますが、これはもともとRTIがきっかけになって“導入しよう”と動いたのでしょうか?
吉田:そもそも、次の拡張パッケージが、プレイヤー側に種族を追加する最後のチャンスかなと思っていました。その種族をどうしようと考えた際、コスト的・技術的に実装することが可能かを検証する必要があります。
例えばヴィエラ族は耳が特徴的ですが、“兜をかぶったら耳が消えてしまう。しかしヘルムの数が多すぎて全部に耳を表示するのが拡張開発のコスト内では厳しすぎる……。はたしていけるかどうか”みたいなことですね。もしかしたらヴィエラ族ではないものにする必要があるかもしれないので、その検証をギリギリのギリギリまで行っていました。
ただ、世界中からヴィエラ実装を望む声を多数いただいていましたし、検証の結果、実装の見通しが立ちました。それならばと“ゲーム体験としてフランを登場させ、その後、ファンフェスでの発表につなげる”というやり方ができることも含めて、ヴィエラに決めたという感じです。

|
|---|
――RTIでは、ヴィエラ族の設定が細かく解説されていて「やはりここまで作り込むのか。スゴいな」と思っていました。
松野:それなんですが、じつはあの設定はもともと『FFXII』用に書き下ろしたものなんです。バンガ族の設定はメディアなどに公開されていたと思いますが、ヴィエラ族のものは私が退社した影響か、お披露目されることなく眠っていまして。今回、開発から「ヴィエラは女性のみが実装される」と聞いたので、これは『FFXII』と同じ設定でいけるなと。だったら、そのまま使っちゃえばいいやと(笑)。ですから、基本は『FFXII』の設定のままですね。
吉田:そうなんですね!? 「『FFXIV』のヴィエラ族は~」という説明だったので、書き下ろしていただいたものだと思っていました。
松野:あくまでも、設定をそのまま流用したという形で、テキストは新たに書き下ろしていますから手間はかけてますよ(笑)。
ちょっと話が飛びますが、『FFT』をテーマにしたわりには『FFXII』も大きく扱っていることについて補足すると、これはプレイヤーさん的に20年前の『FFT』よりも10年前の『FFXII』のほうが記憶に新しいだろうと考えたのが理由の1つです。
また、『FFXIV』の開発チームにもともと『FFXII』チームだった人間がけっこう多くいるのも関係しています。『FFT』はドット絵のシミュレーションRPGだったこともあって、ビジュアルアートが少ないんですね。背景画がほぼなく、あっても戦闘マップの元絵なので流用しにくい。一方、『FFXII』には豊富にアートがある。加えて『FFXII』は3Dモデルもありますから、それを見ながら『FFXIV』の作業ができるため、1から作る場合と比べて手間を減らせるんです(笑)。そのような作りやすさの面を考えたうえでそうしたところもあります。
例えば“失われた都 ラバナスタ”を作る際、私はひと言「ラバナスタを作って」と言うだけで済むので、余計な説明をする必要がありません。開発側も詳しい説明を受けなくても「ラバナスタはこう。これをどう『FFXIV』にアレンジしようか」とスムーズに動き出せます。

|

|
|
|---|---|---|
販売本数的にプレイヤーさんも『FFXII』を遊んだことがある人のほうが多いはずですから、「ラバナスタを歩ける!」というほうが感動するだろうなという考えもありました。そういう意味では、開発側のイメージのズレがなく作れたと思いますね。ボスに『FFXII』のキャラクターが多いことにも理由があります。アートもあり、更にモーションの付いた3Dモデルもあるので、リメイクがしやすいわけです。
――ちなみに、まだビジュアルとして描かれていないルカヴィは複数いますが、そのなかで人馬王ロフォカレを選んだ理由はなんでしょうか?
松野:人馬王ロフォカレは今回初登場ですが、これは雨宮慶太(※6)さんにデザインをお願いしました。『FFXII』側では登場していないのでアートがないという理由もありますが、『FFT』では吉田明彦(※7)さんが描いたデザインがありました。その比較というプロモーションができるかなと思ったので選んだ次第です。
――モデル制作という意味では、バンガ族もRTIの中でしか出てこないのに、ものすごい作り込みですよね。
松野:あれは鈴木くんの意地ですね(笑)。「出せる?」と聞いたら、全部作ってくれました。思い入れがあるんでしょうね。“失われた都 ラバナスタ”にはシーク族も出てきますが、あれは私が指示したものではないんですよ。あれを作ってくれるあたりに、鈴木くんたちの『FFXII』愛を感じますよね。
吉田:ですね。ただ、そこはコスト度外視で徹夜をしてやっているわけではなくて、ほかのコンテンツのみんなも含めてボリュームを調整して「ここのコストをこっちへ引っ張ってこよう」「このパッチで使うキャラが1体浮いているから、そのコストをこっちに持ってこよう」といった、ものすごい量のコストのパズルを組み合わせて捻出しているんです。それを成せるのは、やっぱり愛だと思います。
松野:先日、電撃さんで公開された鈴木くんのインタビューを拝読したのですが、「松野さんたっての希望で、今までの2倍くらいの量を作った」とか言っていまして。私そんなこと言ってないですよ?(笑)「切るものは切っていいよ」って言ったはず!(笑)
吉田:もしかすると、現場には「松野さんが出したいって言っていたから」なんて報告してる可能性もありますね(笑)。
一同:(笑)。
松野:私もたしかに盛ろうとしますけど、そこは切っていいって言っているんだけどなぁ(笑)。
吉田:でも、松野さんが盛りに盛ったうえでの「切っていいよ」はズルいんですよ(笑)。だって、おもしろいんですもの。断れない。……もちろん狙ってやっているんですよね?
松野:ズルいのはわかっているんですけどね(笑)。まあ、結果的にバッガモナンだけでなくブワジなどを全員入れてくれて嬉しかったです。
吉田:“封じられた聖塔 リドルアナ”開放前のイベントで、バッガモナンの腕が膨張するシーンがありますよね。あの表現は、当然ですけどシェイプ変形では対応できないので、ボーン(キャラの骨格)を追加して対応するしかないのですが、テクスチャの解像度を含めてどこまで可能か、かなり検証して決断したはずです。
松野:じつは、バッガモナンたちには代替案があって、「きつそうならマムージャ族でもいいよ」という話をしていました。バッガモナンのために、いちいちモデルを起こしてもらうのは、さすがにコストが高いなと思ったので、「僕はマムージャ族でもいいよ」と。あとの判断は現場にまかせました。そんな感じのオーダーは多いですね。フランも、最初は「“エレゼン族の女性でフランという名前のキャラクター”でもいいんじゃない?」と話していたんですよ。
吉田:でも、そこは『FFXIV』チームのプライドが許さないんですよね。「エレゼンを“フラン”といって出せるわけがないだろう!」みたいな(笑)。
松野:(笑)。
吉田:松野さんは、そのへんのくすぐり方がお上手なんですよ。
松野:でも、本当にがんばってくれたなと思っています。
――『FFT』の正史をあえて戯曲としてRTIのエンディングの表現にするというのは、発案当初から考えられていたのでしょうか?
松野:ジェノミスがアラズラム・J・デュライであるということはRTIの第1弾で公にしています。当初、“じつは『FFT』というゲームの物語はそのジェノミスが書いた戯曲である”というエンディングに帰結させようと考えていました。ですが、ネタを盛り込みすぎかなと考えやめようかと悩みました。最終的に当初案どおりの実装にしましたが、それでよかったと考えています。
吉田:最後の劇中劇は、最初のプロットに“劇場艇プリマビスタ”を登場させるという提案があったときから、おそらく松野さんのなかでイメージはあったと思います。
松野:第1弾の時点で、吉田さんや織田さんには「ラストは劇場艇で終わらせよう」という話をしていました。ただ、それは前述の二重構造の話ではなく、あくまでも物語は劇場艇から始まり劇場艇で終える、どうせなら演劇シーンで終わらせようと話だけはしていたんですね。ですが、最終章の打ち合わせでどうにもシナリオの全体量が長すぎて。それで、「織田さん。カットしませんか?」と最初の話に戻るわけです。
吉田:僕らは、いつも実装しているアライアンスレイド以上のマップコストと時間をかけて、ラストの締め用のステージを作っていたんですよ。ですが、松野さんのショートバージョンのシナリオ案では、そのシーンが全部なくなっていて(笑)。ですが、僕も織田も生粋の松野さんファンなので、「とにかくシナリオを見たい!」という気持ちが強くて。「意地でもカットしないようにお願いしよう」と、2人で話していました。
松野:それでもかなり短縮しましたけどね。
吉田:そうですね。シーンの構成やつなぎのセリフを変えたりして、最初期のものよりも短くなっています。
海外からも絶賛の声――リターン・トゥ・イヴァリースに対する光の戦士たちの反応
――RTIの、プレイヤーさんの反応を見ていかがでしたか?
吉田:Twitterでは、「涙で画面が見えなくなるほど感動した」といった感想がありました。それと、日本だけでなく海外の反響もすごかったんです。「とにかくすばらしい」「レイドシリーズのなかでも最高傑作だ」といった声がとても多くて、ポジティブな意見が圧倒的に多かったのが印象的ですね。
松野:RTIはバトルがおもしろいですからね。
吉田:「過去の『ファイナルファンタジー』作品を扱いながら、ストーリー体験とゲームプレイがこんなにもリンクしているのは驚きだ」みたいに、ベタ褒めでしたよ。
――海外プレイヤーさんも『FFT』をプレイ済みの方がかなり多いんですね。
吉田:驚くぐらい『FFT』を知っている人が多かったですね。全体の割合はわからないですが、海外では『FFXII』が大ヒットしているので、そこからたどって『FFT』を遊んだプレイヤーさんは少なからずいるのではと見ています。
松野:20年前の話ですけど、『FFT』は国内で120万本、海外で50万本ぐらい売れたとは聞きました。それからどれぐらいプレイヤーさんが増えたのかはわからないですね。
吉田:実売数を見たら、270~280万本ぐらいになっていたので、かなり売れ伸びしていると思います。北米の反応を見ると、日本ほど感動の置いてきぼりを感じた人はいなかったようですね。
松野:海外の方は、RTIのシナリオで感動するものなのかな? じつはそのあたりの感覚は、ぜんぜんつかめてないんですよね。
吉田:すごかったです。日本よりも熱狂していたかもしれませんね。
――僕もRTIのエンディング見たあと『FFT』を引っ張り出して再プレイを始めてしまいました。
松野:本当ですか? ありがとうございます。
吉田:ネットでの感想を拝見していると、新たに始めたという人も含めて、『FFT』を始めたくなる方が多いみたいですね(笑)。
松野:先ほど「ラストは演劇シーンで終わらせる」と話しましたが、当初はバトル後の勇者ラムザとディリータの会話シーンから一気に演劇シーンへ移行することを考えていました。あの握手のシーンから一気に劇場艇へ移動し、同じシーンを役者が演じている…という流れですね。ただ、これは開発サイドと話したところ、やはりマップ間の移動に難がありましてボツにしました。で、どうしようかな~と考えていたとき、たまたま『FFT』のサントラをかけていたんです。丁度、エピローグムービーの曲が流れていて。その瞬間、あのとき、ラムザとアルマは何を考えていたんだろう、『FFT』では語られることのない二人の言葉を演劇シーンに盛り込んでみよう、そう思いつきました。で、エピローグ曲の尺に合わせて台詞を何度も書き直し、最終的にああなったわけです。特に二人に「これからは自由に生きるんだ」と言わせてるんですけど、あれは雷神シドやアグリアスら仲間にも当てはまる台詞です。立場や身分に縛られず、これからの未来を歩んで欲しい、そう考えて執筆しました。カットシーンの実装チームも私の意図を汲んでよくまとめてくれましたね。完成したカットシーンを観て満足すると共にちょっと泣けたのは本当です。
さて、電撃さんからリクエストがあったので持参したのですが……これが2016年10月時点でのRTIのプロットです。これをもとに、吉田さんや織田さんを含めた開発チームと打ち合わせを始めました。さきほどの“パッチ4.5でラムザとディリータの会話で終わる”というのもプロットに書いてあります。
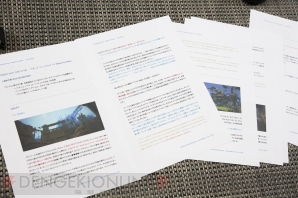
|
|---|
読んでいただくとわかると思いますが、ほぼこのプロットどおりに作られています。ただ、登場するボスに関しては変更をいれていますね。鈴木くんは当時『FFXII』のチームにいたこともあり、RTIの制作時もいろいろと相談しました。たいてい、彼に「できますか?」という質問をするんですよ。これは“技術的にできるか”という話だけではなく、手間的に可能かという質問です。
じつは「フランをパッチ4.3に登場させたい」と言っていたのですが、その段階ではヴィエラの実装が確定していなくて「ダメです」と言われたんです。「ダメなら仕方がない」と、第2弾のシナリオを調整しました。それに合わせて全体の流れも変更を加えていて、もともとの案では第2弾で“ゴルモア大密林から機工都市ゴーグに行く”、第3弾は“リドルアナからミュロンドに行く”という流れだったんです。
ですが、第2弾を作っている最中に、吉田さんのほうから「松野さん、ヴィエラ実装が決まりました!」と言われまして。これでフランの実装ができることになったので、パッチ4.5でお披露目できることになりました。
吉田:仮にパッチ4.3の時点でフランを出してしまうと、プレイヤーさんがそれを見たときにきっと「次にヴィエラが新種族として出るぞ!」って盛り上がりますよね。そんなことがあったあとにもし“検証の結果ヴィエラ族は実装できない”となった場合、さすがにマイナスイメージが大きすぎるので……フランの登場は待っていただいたんです。
松野:すべての要素が流動的だったので、そこに合わせて柔軟にシナリオを変えていくことはありましたね。
――プロットを拝見すると、中ボスの変更がいくつかあったようですね。
松野:鈴木くんは『FFXII』に思い入れがあるので、『FFXII』の召喚獣をできるだけ多く登場させたかったみたいですね。変えてほしくないものだけピックアップをして、あとは「きみの好きなものに変えていいよ」と伝えました。最終章のボスはさすがにプロットのままです。そこは変えたらマズイ部分なので。
――第2弾の中ボスとしてプロットに書いてある、ウィーグラフや銀髪鬼(エルムドア侯爵)はぜひ見てみたかったです。
吉田:そういったボス周りの調整が終わったあとに、「雨宮さんにどのボスデザインを依頼しますか?」という話をしていきましたね。

|
|---|
松野:最終的には、人馬王ロフォカレ、冷血剣アルガス、鬼龍ヤズマット、雷神シド、聖天使アルテマの5体を雨宮さんにお願いしました。
――雨宮さんも含め、『FFXIV』の大きなコンテンツをゲストクリエイターに手掛けてもらうということ自体が初めての試みですが、そもそも“ゲストクリエイターを呼ぶ”というのはどのような効果を狙って行われたのでしょうか?
吉田:僕をはじめとした開発チームのコアなメンバーはロジカルにものを作る傾向があって、作り終えたルールから逸脱するさじ加減がとても難しいんです。ゲストクリエイターの方々には、その規定パターンを壊してもらいたいというのが狙いです。僕らと異なるゲームデザインのセンスを持つ方が“僕らだと先回りして言わないだろうな”というところを、あえて言ってくれるのではないかといったところも大きかったです。
あとは単純な話なのですが、僕は松野さんに憧れてゲーム業界を突っ走ってきました。ですが、まだ一度も松野さんと直接お仕事をさせてもらう機会がなかったので、なんとしても松野さんとお仕事をしたかったんです。松野さんにお食事に連れていっていただけるようになった際、「何か書かせてよ」と言っていただけたので、「じゃあ、ぜひお願いします!」と飛びついたことがスタートです。
また、松野さんはヘヴィな光の戦士ですので、シナリオだけでなくゲームデザインという部分でも「こうしたら?」と言ってもらえるかなという目論見もありました。
松野:でも、今回はゲームデザインに口出しはしてないですよね?(笑)
吉田:そうですね(笑)。むしろ、こっちの仕組みを理解してシナリオ執筆をしていただいた感じです。いずれにせよ、スタートとしては、作り手としても遊び手としても松野さんとかかわってみたかったというのが大きいですね。
雨宮さんに関しても、同じような理由です。僕は雨宮さんがデザインした『FF』のモンスターが動く姿を見たかったですし、それは世界に対してもアピールできるポイントだと思いました。そこで、“牙狼”でコラボ企画が立ち上がったときに、『FFXIV』側のメリットとして「ぜひボスを描いてください」と依頼しました。それらを踏まえたうえで、松野さんに「雨宮さんにボスのデザインをお願いしようと思っているのですが」とお伝えした流れです。
松野:この業界で私たちくらいの世代の人間は、雨宮さんがすばらしいクリエイターであるということを当然知っているんです。私の場合は、例えば『未来忍者』(1988)とか『ゼイラム』(1991)といった映像作品を観ていた大ファンですから。そんな雨宮さんにRTIのボスを描いてもらえるのは、願ったり叶ったりというか、チャンスだなと思いました。
――RTIは、2年という長いスパンで開発・実装されていますが、具体的にはどういった流れで開発が進んでいったのでしょうか?
松野:まずさきほどご覧いただいた大枠のプロットを提示し、その次は各章のより詳しいプロットを提示します。これを見て、開発側はどれぐらいの作業ボリュームが必要かということを判断し、フィードバックをもらいます。「ここはもっと膨らませられます」「ここはコスト的に難しいです」とか、そうしたやりとりを何度か行います。
日付を見てもらえればわかりますが、初期プロットと第1弾の詳細プロットの間は半年ぐらい空いています。これは開発スケジュール的に、半年間が必要だったわけではなく、他のコンテンツを実装し、RTIの第1弾に手をつけられるようになるまでのタイムラグといえます。詳細プロットのやりとりが終わった段階で、開発側は「ラバナスタのマップはどうしようか」「バンガ族は実際に作ろうか」といったより具体的な行程に進むわけです。
吉田:そうですね。
松野:そして、こちらはそのフィードバックを反映した脚本を執筆することになります。
――それを受けて、バトルも開発が始まるのでしょうか?
吉田:バトルは雨宮さんへのボスイラストの発注などもあるので、じつはもっと早い段階から動いていまして。デザイン的に“どんなバトルにしていくのか”“どういう展開でボスが登場するのか”といったことを見たうえで、独立して企画を進めます。ボスがどういう動きをするか、どういう攻撃をするかがわからないと、何も進まなくなってしまうので、バトルの進行はすごく早いんです。こういう方法をとらないと、3DモデルがFIXできないんですよ。
ただ、ほかのコンテンツでもそうですが、バトルチームは“シナリオに寄り添ったバトル体験”を信条にしているので、最終的に企画が詰まってきたら、それに合わせて少しずつ調整を加えています。
松野:一方で、冷血剣アルガスは雨宮さんのデザインあってのバトル内容となりましたね。
吉田:たしかに、アルガスの“仮面”の話はデザインのなかで出てきた話ですね。
松野:雨宮さんへは、まず“アルガスは自尊心が高く他者を見下す尊大なキャラクター。一方、内心は臆病者で中身のない人間である”というイメージを伝えました。
吉田:そこから、ものすごいスピードで7バリエーションぐらいのラフ画が届きました。アルガスだけでですよ?
雨宮さんから、「まずはこれを見て、吉田さんと松野さんだけで話して」と言われていまして。雨宮さんのスゴイところは、“どれがいいか”を尋ねるのではなくて、“どの画のどの部分がいいか”を聞いてくるんです。
松野:“このラフの腕とこのラフの脚”みたいな感じですね。そこから、こちらが指定した部分を組み合わせて雨宮さんに完成体を作っていただきます。
吉田:「なるほど、じゃぁこんな感じかな」と2~3バージョンの画がきて……といった具合です。最終的にFIXしたら、彩色・詳細画に入ってもらいます。その際、雨宮さんがアルガスの人柄を表すために、仮面が浮遊しているような状態の姿を描かれて。松野さんも僕も非常に気に入ったので、バトル側に「仮面をスイッチして攻撃やモードが変わるようにできないか」と打診し、あの表現が生まれた形です。

|
|---|
――真実の仮面と偽りの仮面のギミックは、そこから生まれたんですね。ちなみに、今回のバトルはコンテンツごとにお1人ずつ担当がついた形になるのでしょうか?
吉田:いえ、ボスごとに担当者がいます。中川(※8)の下にバトルプランナーが何人かいて、その1人ひとりがボスを担当している感じです。例えば雷神シドだと“次元の狭間オメガ零式:シグマ編4”や“次元の狭間オメガ零式:アルファ編4”を作ったスタッフが担当しています。中川は、全体のリードをしていて、特定の何かを担当してはいません。全体の統一感のチェックや、やりたいことと体験が伴ってないなどのジャッジをしてくれていました。雷神シドの担当は、若手エースですね。まだまだ表に出していないスタッフはたくさんいるんです。
松野:良い意味で“いやらしいな”と思うギミックは、だいたい彼ですよね?
吉田:そうですね。あとは、新しいことにチャレンジすることが多いですね。「“画で見て避ける”をコンセプトにしたいので、統制者ハシュマリムでは柱が出てきてナナメにぶった斬ります」とか。“ナナメにスライドして倒れて、そこにコリジョンを出す”って、プログラマーは超大変だろうなと思ったのを覚えています(笑)。
松野:おもしろかったですよ。私もいちヒカセンとして、楽しませてもらいました。
――ちなみに、松野さんは実機での確認はどのタイミングで行われるのでしょうか?
松野:最後の最後ですね。じつは、テストプレイのときは、吉田さん以外はなるべくライトな『FFXIV』プレイヤーを集めるので、めちゃくちゃ苦戦するんですよ。最初それがわからなかったので「今回は難しいな」と思っていたのですが、実際に公開されたものを遊んでみるとあっさりクリアできちゃって。「難度下げた?」と聞いても「下げていませんよ」という話になったり(笑)。
吉田:でも、テストプレイではプライベートでレベル70のジョブを持ってない人は入れてないんですよ。ただ、カジュアルに遊んでいる人が中心で、レイドをガッツリやっている人は入れていません。言い訳させてもらうと、テストプレイのときはアイテムレベルを下げすぎなんですよね、きっと。
松野:たしかに、それはあるかも。けっこうギリギリの数値なんですよね。
吉田:そうですね。プレイヤーさんの平均アイテムレベルよりも、少し下の装備で挑むようにしています。
――初見のアライアンスレイドは本当にギリギリでクリアできるので、そのバランスにはいつも感動しています。
吉田:初見ではクリアできずに終わるぐらいのイメージで出しているので、逆にプレイヤーのみなさんの平均的な強さがこちらの想定よりも上なんですよ。
松野:“楽欲の僧院 オーボンヌ”の初回プレイは、やはり雷神シドがキツかったですね。防御ダウンのデバフがスタックするアクション“星天爆撃打”を使ってきますが、当初はエスナをしないと最終的に即死する攻撃だったので何回も死んでしまって。そのときは、私がタンク、白魔道士が板鼻(※9)さんで、「板鼻さん、デバフ解除して!」って(笑)。
――“楽欲の僧院 オーボンヌ”は演出的にも集大成といった感じで、かなり力を入れて作られていましたね。

|

|
|
|---|---|---|
吉田:そうですね。とくに機工士ムスタディオは、まったく新しいモードを1つ開発したくらい気合いを入れて作りました。“ファイナルテスタメント”での“バトル中に全員のカメラを乗っ取って、1つの演出を見せる”という仕組みはカットシーンで構成されておらず、今までにやったことがないパターンです。しかも、全員のポジションを記憶しておいて、演出後はすぐに元の場所に戻す作業をシームレスかつちょうどいい尺で行うようにしたのですが、上手くできたと思います。ただ……あの狙われている場所というか……視力検査の“C”みたいなの。あの表現は担当者も苦労していましたね……僕も良いアイデアを出してあげられなくて、今も悩ましいです(苦笑)

|
|---|
松野:パッと見、逆ですよね。普通は、穴が空いている部分が危険だと判断するかと。
吉田:そうなんですよ。「そこを撃たれるんだよね……うーん!」って。 “朱雀征魂戦”を担当している新卒2年目の子が作ったのですが、彼もどんどん成長していっているので、その成長を見ているのも、頼もしかったり、楽しかったりします。
松野:個人的に感心したのは“楽欲の僧院 オーボンヌ”の背景ですね。特に聖天使アルテマ戦でバトル中に背景を一気に変えているんですよ。「“次元の狭間オメガ零式”の4層も後半に入ると背景が変わるじゃないか」と思うかもしれませんが、じつは根本的に条件が違うんですよ。これはけっこう新しい試みで、アライアンスレイドという長いマップがつながっているなかでの背景変更は、かなり手間もかかっているはずです。あれは、ビックリしました。
吉田:そうですね。途中に読み込みを入れているわけではないので、すべてメモリに入れながら行っています。あれは、本当に難産だったんですよ……。
松野:ちなみに、ムスタディオ、アグリアス、シドがバリアを張ったり、ラムザがアルテマの攻撃を防御するというあたりはノータッチです。そういえば、ネットでもラムザの“大”は色々とツッコミがありましたね。吉田さんはツッコまなかったんですか?(笑)
吉田:むしろ、あれはギリギリまで調整して、やっと“大”までこぎつけたんです……。最初は片手でバリアを張る感じだったのですが、空中で踏ん張るモーションはどうしても見栄えが悪いのです。「どの角度から見ても守られていることがわかるポーズは“大”しかない」という結論に……。ポーズだけでなく、ラムザの位置が高すぎて最初は何に守られているかわからなかったので、最後まで位置を上げ下げしていましたね(笑)。
松野:なるほど(笑)。
吉田:そういえば、聖天使アルテマ戦の担当者を決めるときに、スタッフの1人が「アルテマ戦を担当するには、条件があるんです!」って言い出して。「いわゆるセクシーアルテマ(※10)を使わせてくれるなら、担当してもいいですよ」と言っていたので、「それは好きにしなよ」って(笑)。
松野:そういえば、セクシーアルテマを使っていいかと確認が回ってきていましたね(笑)。

|
|---|
吉田:そうしたら、気合いが入りすぎてコストが大変なことになりまして(苦笑)。アルテマ戦はAOEが少しずつ進んでいくのも新しい仕組みですね。予兆を見たら確定という部分の裏をかきたかったんだと思います。
――AOEが表示されてから動くといえば、“グランドクロス”の十字範囲が動くのはびっくりしました。
吉田:ドキドキしますよね、あれ(笑)。プログラマー的には“当たり判定を実際に動かすのか、またはサーバでは当たり判定を最終地点に設定しつつ画だけを動かすのか”といったことを考える必要があって、実装にはかなり気を使ったと思います。
リターン・トゥ・イヴァリースのボイスは過去最多――コンテンツ中のセリフについて
――RTIは全体を通してボス戦でのボイスが多めだったことが印象的でしたが、とくに“楽欲の僧院 オーボンヌ”に関してはものすごいボイス量でしたね。
松野:そこは、完全に私のワガママですね。説明すると、アグリアスたち3人の専用モデルを作るだけのコストはかけられないので、せめてボイスだけは全員分を入れてくださいと懇願したんです。フランやバッガモナンは出番も多いので例外的に専用モデルを用意していただけました。ですが、さすがに彼ら3人を作ることはできない。とすると、どうしても汎用モデルの流用になってしまう。人気のあるキャラクターなので楽しみにしているファンの方々からすると残念に思われるだろうなと。なので、“楽欲の僧院 オーボンヌ”は、最初から4人のボイスを入れるようにオーダーしたんです。ただし、ボイスの収録はかなり早い段階で行われるので、「テキストを早くください」と言われまして。最終章のシナリオよりも先に提出することになりました。具体的に述べると、最終章シナリオの初稿を提出したのが2018年7月27日、それに対してバトルボイスのテキストの提出は2018年5月21日と2ヶ月ほど前になります。
吉田:僕らが各パッチで4言語を同時に実装するには、当然ですが4言語を同時に録らないといけません。また、毎パッチごとに収録しているとスケジュールが噛み合わないので、僕らは2パッチまとめて収録しています。つまり、パッチ4.5のボイスはパッチ4.2が終わった段階でパッチ4.4と同時にボイス収録していないといけないんです。
ですので、松野さんには「最後の脚本ができあがっていなくても、バトル中に喋らせたいセリフはこの時点でもらえないと収録できません。申し訳ないのですが、このタイミングでテキストをください」「専用の声優のオファーはできないので、このキャストの中から選んでください」と2つのお願いをしました。そこを飲んでもらえるのなら、全力で応えますと。
松野:じつは、“楽欲の僧院 オーボンヌ”に関しては、それでもラクだったんです。「おそらくこういう技を使うだろう」というリストをいただいていたので、『FFT』から詠唱メッセージをそのまま持ってきました。もちろん、オリジナルのものも書いてはいますけどね。例えば、アグリアスに喋らせた「人の夢は儚く脆い……されど夢を語らずして叶うわけもなし! 見せてみろ、貴様の信念とその証をッ!」という究極履行技の台詞。これは『FFT』のアグリアスの「人の夢と書いて儚い、何かもの悲しいわね」というヘルプ・テキストに対するアンサーなのですが、バトルに合うように、かつオリジナルの上を行くようにと頭をひねって考えました。
逆に、辛かったのが鬼龍ヤズマット。バトル企画は白紙で雨宮さんのイラストしかなかった。シナリオも執筆前で詳細プロットのみ。バッガモナンの恨み節と荒くれ者的なイメージのみで、「こんなもんかな」というのを書いて提出しました。ヤズマットといえば「エスナがほしいか言ってみろ!」が何かと話題になっていて、私が生放送でしゃべったのが元ネタだとか言われていますが、じつはあの段階ですでにヤズマットのセリフは決まっているんですよ。それを、私が生放送の場でうっかり口走ってしまったわけですね。
――時系列的にはむしろ逆だったんですね。
松野:はい、そのとおりです。
吉田:それぐらい、みなさんにコンテンツをお届けするかなり前からいろいろなものを並行して作っていて、それでやっと3.5カ月×5のパッチサイクルができているんですよ。時間で言うと、みなさんとは半年ぐらい感覚がズレているんです。
――ボイスといえば、技の名前は英語だとどうなっているのでしょうか?
松野:PSP版の『FFT獅子戦争』に準拠しているんじゃないかな?
吉田:そうですね。コージ(※11)がものすごく『FFT』が好きで、翻訳にも相当こだわっていますね。
松野:詠唱メッセージにボイスを当てたとき、はたしてカッコよくなるのかというところが懸念でした。ですが、実際に聞いてみたら、めちゃくちゃカッコよくて。
吉田:声優のみなさん、本当にさすがでした。
――あらためて、こういう読みなのかと気づいた技もありました。
松野:私も「暗の剣」が、「あんのつるぎ」と読むんだと知って驚きました。「あんのけん」だと思っていたので(笑)。あれは伊藤(※12)さんが考えていたから、わからないんですよね。
吉田:声優の方には、いわゆる兼ね役でお願いしているので、意外と皆さんがメインシナリオで会っている人が担当していたりします。それを意識するとおもしろいかもしれないですね。
――アグリアスはユウギリ役の佐藤利奈さん……ですよね?
吉田:はい、そうですね。アグリアスは人気キャラクターなので、ちょっと心配だったんです。派生タイトルでは、沢城みゆきさんが声を当てているので、「それと違う」と言われるかと思ったのですが、皆さんにすんなりと受け入れてもらえたのでホッとしました。
――最終章の道中で登場するのがムスタディオ、アグリアス、シドの3人だったのはなぜでしょうか?
松野:「人気的にはやはりこの3人だろう」と。ただ、シドは“バランスブレイク”を言わせることを前提として登場させました(笑)。
吉田:あの「お前が言うな!」感はイイですよね(笑)。
松野:そうツッコんでほしいから入れたんです(笑)。Twitterで長尾さん(※13)にもツッコまれましたけど、もともとの履行技名は漢字で「衡平壊変」と書きます。その上で「バランスブレイク」と読ませるつもりでした。
吉田:テストプレイのときに、QAチームからも「これは正しいのか間違っているのか、仕様なのかバグなのかがわからないです」という反応がありました。たしかに、ボイスと表示されているテキストが違いますしね。
松野:『FFXIV』のシステム上、テキストにルビは振れないんですよ。織田さんに「漢字で書いて、読みはカッコ書きでいいんじゃない?」と話したのですが、「それはダサイですよ」と言われたので最終的にカタカナ表記で実装しました。ただ、あれをカタカナ表記にするなら、聖天使アルテマの履行技名の「究極幻想」(アルティメット・ナリファイア)もカタカナだけでよかったのかなとも思います。
この“漢字で技名を書いて、読みはまったく異なる英語名をカタカナで書く”……、これは単純な私の遊びなんですけど、『FFT』は1997年発売のゲームなので、なんとなく90年代後半の雰囲気を仕込もうと思いまして、当時好きだった某漫画のテイストを入れてみました。
また、モンブランのセリフで「とっても×2」と書いて「とってもとっても」と読ませる部分があるんです。この理由は2つあって、1つは単純に仕様上、長い台詞を書けないから。もう1つが、『FFT』の発売5日後にリリースされた某人気アイドル(現女優)のJ-POPが流行りましてね。それに代表されるように、90年代は「×2」でフレーズを繰り返すという文化が流行りました。今では死語ですが(笑) そんなちょっとした“遊び”も入れてます。
吉田:へぇ~(笑)。
松野:ですが、公式フォーラムに「世界観に合いません」と書かれていて「ゴメンナサイ」という気持ちになりました(笑)。
――詠唱といえば、聖天使アルテマのサモンダークネスは、『タクティクスオウガ』のものが使われていますね。
松野:あれは、召喚魔法ということで『タクティクスオウガ』から引っ張ってきました。死者の宮殿で屍術師ニバスもすでに出ていることですし、世界観的にも問題ないだろうということで。ただ、他の技よりも明らかに多用されていたので、これならちゃんと新たな詠唱文を書くべきだったと反省しています。
――シナリオ内の会話でほんの少し触れられてはいましたが、そもそもとして聖天使アルテマはハイデリンにおいてどういう存在なのか、あらためてお聞きしてもよろしいでしょうか?
松野:ものすごくカンタンに言ってしまうと、“オメガと同じで、どこか別の惑星または次元から来た存在”で、それ以上でも以下でもないんです。ちなみに、詳細設定の一部ですが、聖天使アルテマフィギュアのパッケージに英語で書かれています。お持ちの方は是非確認してみてください。設定すべてについては、いつか設定本第三弾に掲載……されるのかな?(笑)
――デザイン的には、『FFXII』の機械的な聖天使アルテマがモデルになっているのでしょうか?
松野:雨宮さんには、『FFXII』のアートをあくまでも参考資料としてご覧いただきました。ですが、雨宮さん的に、「皆葉(※14)さんのデザインが完成されすぎているので、あえて崩す」と言って、あの姿にデザインされたようです。崩すという意味では、私も『FFT』のルカヴィの設定を変更しています。RTIでは、アルガスやバッガモナンのように聖石の力を借りて変化したものをルカヴィと称していますが、ハシュマリムやファムフリートなどは“聖石の力に惹きつけられ現れたモンスター”程度のレベルに格下げされています。
――妖異的な感じですか?
松野:そうですね。ヴォイドか何かからきているんだろうという感じです。格下げしておくと、このあとのパッチ5.Xで普通のモンスターとして使えるという利点もあるので(笑)。
ノア・ヴァン・ガブラスの登場――余韻を残す終わり方に
――ストーリーで言うと、最後に帝国絡みのイベントがあって、今後を匂わせる展開が用意されていましたが……?
松野:あれはとくに次への伏線とかではなく、単に余韻がほしかったので入れただけなんですよ。じつは当初は“ゴーグの上にヴァンとパンネロ、バルフレア、フランがいて、聖石を拾ったところで終わりにしよう”と考えていたんです。最終章で手に入る装備品の資料もすでに確認していたので「バルフレアは作れる、ヴァンも作れる、フランも作れる。ならいけるかな」と思っていたのですが、鈴木くんに「パンネロを再現できないですけどいいですか?」と言われて……「パンネロを作れないなら無しだな」と(笑)。そんなこともあり、今回のオチになりました。
吉田:個人的に、松野さんは“世界を創る人であって、閉じる人ではない”と思っているのですが、その性質が、あそこに象徴されていますよね。RTIという物語自体はすごくキレイに閉じているけれど、世界の設定は物語の先にも広がっているはずのものですし。そういった先の展開を匂わせるような帝国の使い方も、松野さんが『FFXIV』プレイヤーだからこそ出来たものだなあと感じました。まあ、帝国との決着もまだついていないですしね。その後としては、「ダルマスカは、どうなっていくんだろう」というところも見どころですし。
松野:「ダルマスカ解放戦争」については、使う使わないに関係なくプロットは書いてあります。『FFXIV』に実装されないとしても、どこかで発表する機会はあるんじゃないかな~と。例えば、「光の回顧録」とかね。
吉田:フランのセリフのいくつかは回収されないままですし。僕らに見えない部分で、ネタを作っているんだろうなと見ています。
松野:最終的にはプレイヤーさんの想像を広げてもらえるネタであれば十分かなと思っています。
――設定の回収としては、サブクエストでフランやレジスタンスについて補足がされていましたね。
松野:織田さんから「ナグサとかも東方連合に入るかも」みたいな話をいただいて、となると「ダルマスカのレジスタンスも入ってくるんだろうね」という話になって。「じゃあ、今現在レジスタンスが東方連合に入ってない理由が必要だろう」と。また、メインシナリオには盛り込めない内容なので、「レジスタンスはバラバラで意思統一されてない」という話をサブクエストでフォローしてみました。
この他、レジスタンスの資金源をどうするかという話になったときに、ハンコックに「東アルデナード商会としては表立ってバックアップはできないが、商売としてなら問題ない」という説明をRTIの本編側でさせています。それに対するアンサーをサブクエストのほうで「なら、ここにレアなワインがあるので売却して資金源にしよう」みたいな流れを作りました。
吉田:このあたりの設定は、本当に絶妙ですよね。
松野:開発チームも、“楽欲の僧院 オーボンヌ”にちゃんとワイン蔵を作ってくれていますよね。

|
|---|
吉田:開発に、シナリオを読み込んでない人はいないです。参加するんだったら、ちゃんと理解してからやる開発です。仮に、この先何かがあるとしても、松野さんがいかようにも料理してくれるんだろうなと思いながら作っていますよ(笑)。広がりがあるからこそ、終わって「あぁ、おもしろかった」だけでなく、「あれがあるんだし、もっとこうなるのかな?」みたいな議論ができるのがいいところだと思います。
――ちなみに、劇場艇プリマビスタは、パッチ5.0以降もクガネにあり続けるのでしょうか?
吉田:そこはまだ、とくに決めてないです。
松野:あれ、景観的に邪魔と感じる人もいるみたいですね。
吉田:とはいえ“景観”って、人がコントロールするものでもないしなぁ。
――残るとするなら、パッチ5.0以降でもサイドクエスト的なものがまたあるのでは……と実装に期待が持てますね。
吉田:パッチ5.0以降とか……。もう、パッチ5.0に集中していっぱいいっぱいなので、今はその先は考えられていません(笑)。
――サイドクエストについて、もう1つ。いろいろと話題のワインクエストに関してですが……。
松野:それに関して、お騒がせしてしまってすいません。第2弾の本編側に入れてしまったのは失敗だったと反省しています。サイドクエストはもともとパッチ4.3を前編、パッチ4.5を後編とする計画でして、あのまま投げっぱなしにするつもりはありませんでした。ただ、パッチ4.5のボリュームが膨大ですから、最悪カットされる可能性はあるかもという懸念はありました。
吉田:パッチ4.5のワインクエストに関しては、松野さんには非常に気を使っていただいていて。できるだけ最小のコストで作ってもらえればと、テキスト量も削りに削ったものを持ってきてくれていたのですが、逆にカットシーンの開発チームが気合いを入れてしまって。松野さんからの指示はほぼなかったのですが、最終的にかなり盛ったカットシーンになっていました。
松野:ミコッテの女の子が冷たくにらむところとか、お金をもらったらニッコリするところとか、私の指示ではありません。ゲゲルジュのパーソナリティを表している、いいシーンだと思いました。
吉田:ワインを奪い合って割れるシーンも、松野さんは「ブラックアウトしてラベルだけでもOK」としていたのですが、あんな感じに(笑)。じつは、あれ実際に水を入れたワインの瓶を地面で割って、それを写真に撮って加工したらしいです。
松野:この一連のイベントは、前述のレジスタンスの資金源問題や東方連合への加入問題など本編側で語るには難しい事柄を語らせるための目的で実装しています。ですが、一番の目的はワインポート近くの小屋でPTSDに悩む、ダルマスカから逃れてきたドレストに、救いを与えたくて作ったんです。本当だったら、ワイン畑で働くというところまで持って行きたかったのですが、さすがにメインシナリオ以外でポジション移動という分岐をさせるのは問題なので、せめてそういった展開を匂わせて終わらせようと思い、あの形に落ち着きました。
吉田:ダルマスカという単語を用いて始めてしまったものを、松野さんが“あの小屋に生き残りがいたじゃん”と覚えてくださっていて。さらに“そいつを救ってあげよう”と思ってもらえたことは、本当にうれしく思います。だからこそ、僕はあの一連のクエストが大好きです。
松野:前廣くんが広げた風呂敷を、私が畳むというね(笑)。
吉田:うちの前廣がすいませんでした!
松野:冗談です(笑)。むしろ、前廣くんのそうした一連の“遊び”がなければ、そもそもこのRTIは成立しなかったでしょうね。前廣くんには感謝しています。
それはともかく、パッチ4.3のワインクエストで公式フォーラムがちょっと荒れちゃって。実装時点でその先の展開があるんだよという余韻が足りなかった。そのあたりの書き方が適切ではなかったと猛省しています。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
吉田:プレイヤーのみなさんは、先があることを知りようがないですからね。「これ、人によっては気分を害する人もいるかもしれないですね」とチラッと議論は出たんですが、そのまま実装してしまいました。
――個人的には、ワインの産地がレアモンデ(※15)というところに「おぉ!」となりました。ファンサービスありがとうございます。
光の戦士・松野泰己が感じる『FFXIV』の魅力とは
――ここからは、松野さん・吉田さんのゲームに対する想いを聞かせていただければと思います。まず、松野さんはコアな光の戦士として知られていますが、松野さんが考える『FFXIV』の魅力をぜひ教えてください。
松野:やはり飽きさせないように、パッチごとに新しいコンテンツを用意してくれるところでしょうか。現実のディズニーランドやUSJといったアミューズメントパークがどんどんサービスを変え拡張されていくのと同じように、その勢いをしっかり維持し続けているというところが、今までのオンラインRPGと違うところだと感じています。
あとは単純にゲーム性ですね。私はストーリーを創る側の人間なので、“世界観を大切にしつつも、プレイヤーさんの予想を裏切るように物語を展開させてくる”というスタンスには、好感を覚えます。また、バトルが楽しいことも魅力ですね。何度もリトライして、クリアした瞬間の快感は非常に気持ちがいいんですよ。脳内麻薬が出まくるというか(笑)。最近忙しくて、やっと“極朱雀征魂戦”に挑みだしたタイミングなんですが、やはり楽しいですね。
吉田:あれ、実装当初はサーバと判定がズレるという不具合があってですね……。
松野:おぉ……?
吉田:隣に移動しているはずなのに、もう吹っ飛んでいるみたいな。公開初日に、バトルチームの面々とプライベートのキャラクターで挑んだんですが……「……判定ズレてるぞ、これ……」と。おかしいからコンテンツに再突入してリトライしてみてもダメで、すぐ緊急の赤電話が飛ぶという(苦笑)。
松野:レイテンシーに関係するズレとかはどうしようもないですものね。
吉田:実装の方法というか、判断の順番にミスがあり、申し訳ありませんでした。
松野:話を戻しますが、『FFXIV』は飽きさせない作りになっていることがすばらしくて。例えば、『ウルティマオンライン』のようなサンドボックスゲームは、飽きないように自分自身で遊ぶ目的を作っていきます。逆に、消費型オンラインRPGは、パブリッシャー側がどんどんコンテンツを実装していかないと消費のスピードに追いつかなくなってしまいます。消費型オンラインRPGである『FFXIV』は、その点をすごく上手にコントロールしていますよね。その追加コンテンツを開発予算や人員体制という制限された枠組みの中で巧みに構築していく点については、私も開発者の一人として実に興味深く注目してまして、その観点からしてもよく作っているなぁと。感心することばかりです。このあたりは、開発者じゃないとわかりにくいとは思いますが。
私は、そこまでハードなプレイヤーではなく、いわゆる準廃的なポジションだと自負していますが、そのポジションなりの遊び方がたくさん用意されているので、そういう意味で色々なプレイヤーさんに対応している幅の広いゲームだなと感じています。
――昔からオンラインRPGを遊ばれている松野さんから見て、“禁断の地 エウレカ”の印象はいかがですか?
松野:全体としては非常におもしろかったと思います。なにより『FFXI』に対するリスペクトを感じました。担当されている中川さん自体が、『FFXI』の廃プレイヤーですしね(笑)。『FFXI』のNMは基本的に取り合いですが、“禁断の地 エウレカ”はNMを狩るのに野良パーティがサッと組まれます。戦闘不能の人がいれば、そこまで移動して蘇生してあげる。そういう意味で、エウレカはけっこう温かい世界だなと思いました。いい意味で『FFXI』時代の要素と『FFXIV』ならではのお手軽さが融合していて、新しいコンテンツになっていたのではないでしょうか。
ですが、問題もやや感じました。エウレカは時間を使うことで、プレイヤースキルに依らずクリアができ、エウレカウェポンを作っていくというコンテンツです。でも、思っていた以上に時間を取られてしまうんですよね。アネモス編は、エウレカウェポンを作るのは簡単で、レベルを上げ終える時には武器3本分程度のアネモスクリスタルが集まっています。ですが、“パゴス編”以降はそれができない。レベルを上げ終えたところからが強化の本番になる。
そうなると、サラリーマンの方など時間を確保しにくいなかで『FFXIV』をプレイしている方たちにとって、エウレカは時間泥棒になってしまう。ほかのコンテンツを遊んでいる暇がなくなっちゃうんですね。Time to Winの部分はあるにせよ、そういうプレイヤーさんにとっては時間を取られすぎてツライんじゃないかなと。
吉田:松野さんが今おっしゃったところは、僕らが初期設定でかけ違えたボタンでして。僕ら的にはむしろプレイヤーさんが先鋭化して、Time to Winだからこそ好きな人しか残っていかないだろうと思っていたんです。ですが、“アネモス編”の間口がいい意味で広すぎたので、“パゴス編”で先鋭化したことに対する抵抗感が強く出てしまいました。
さっきもお話ししましたが、僕らはかなり前から……それこそ“禁断の地 エウレカ”は大きいマップなので半年以上前から制作しているので、ゲームデザイン上あとから変えてしまうわけにはいかない部分が出てきてしまったんです。また次に似たチャレンジをするときは、今回の経験を活かしていきます。
ただ、もともと『FFXIV』の中にあるルールを壊して、そこでしか遊べないゲーム体験を提供するというチャレンジとしては、“バルデシオンアーセナル”も含めてしっかりとやりきった感じはあります。
松野:ただ、総合的には実に楽しいコンテンツでした。かつてのMMOに対する愛をしっかりと感じられておもしろかったです。
吉田:ありがとうございます。今回の「バルデシオンアーセナル」は、日本と欧米でフィードバックの割合が大きく異なることになったのも、FFXIVでは初のことでした。この辺りは、新しいことに挑戦し、ミスもあったからこそではありますが、今後のFFXIVにとっては大きな試金石になったと感じています。

|
|---|
松野:そもそも、『FFXI』など旧来のMMORPGに寄せたゲーム性で『FFXIV』の手軽さを味わいたいと考えること自体が大きな間違いなんですけどね。なにしろサービス開始当初の『FFXI』はもっと過酷なゲームでしたから(笑)。楽しい部分だけをピックアップして、今の時代に合わせた手軽さを念頭におき再構築する。それは正しい考え方だと私は思います。
吉田: “バルデシオンアーセナル”も『FFXI』と比べればそこまで厳しい仕様ではない気もしますよね……。
――『FFXI』のデュナミス(※16)は、3日に1回、1カ所につき1団体のみが突入できるという仕様でしたしね。競合したら負けた団体の数十人は、そこを諦めざるを得ないという。それと比べたら優しいですよね。今回登場したアブソリュートヴァーチューも、もともとは複数の海NM(※17)がドロップするトリガーアイテムを集めて、さらにそれで出現させられるNMを倒すと低確率で登場という……挑むまでにそもそも長い道のりを経る必要がありました。
吉田:『FFXIV』は、全体的に“手つなぎゲーム”である側面があって。それで楽しくやってきたというプレイヤーさんからすれば、先鋭化によって手をつながせてくれない状況が生まれたことによる拒絶反応だったんだろうなと思います。
――今までの『FFXIV』のレイドの手つなぎとは違う、別ベクトルの手のつなぎ方でしたね。
吉田:バルデシオンアーセナルは、もっと互いが手を伸ばさないと届かない感じにしたのですが、そこは国民性があるのかなとも思います。これから、遅れて中国、韓国でも実装されますが、中国は北米・欧州と同じように「順番にクリアするから、まず手伝ってくれ」という感じで、韓国は日本と同じような反応になるんだろうと予想しています。
松野:とはいえ、かなり温かい世界でしたけどねぇ。2人乗りマウントに乗れる人が初心者を乗せてくれたり。「本当にすみません、ありがとうございます」と言うと、「いえ、私も最初そうだったので、今は恩返ししているだけです」みたいなやりとりがあったりして。
吉田:2人乗りマウントの価値ですね(笑)。
松野:私としては、通常フィールド全体があんな感じに、エウレカのような遊びができるようになるのが理想だと思いますけどいかがですか? それだと、エウレカを遊びながら、他コンテンツにもトライできるし、マケボも覗くことができる(笑)。
吉田:それがですね……。なかなか難しいんですよ……。
――光の戦士である松野さんとしては、今回初めて『FFXIV』開発現場に入って共同作業を行いましたが、現場の雰囲気を体験していかがでしたか?
松野:みんな同じ方向を見ながら仕事をしているなというのが、よくわかる開発現場でした。制作チームって、それがバラバラな場合もあるんですよ。正確な仕様や目指すべきゲーム性をディレクターしか把握していないとか、スタッフは言われるがままになんとなく作っているとか。ですが、『FFXIV』チームはそこをしっかりと共有されているんですね。各セクションリーダーが、チームをうまく結束しているのがよくわかります。
だからこそ、レスポンスが非常によくて、“できる・できない”の判断が速いんです。「○○さんに相談しないとわかりません」ということがほとんどなくて、あったとしても返答に一週間かかるわけでなく即座に返事が返ってきます。また、返事にブレがないんです。「先週はこう言いましたが、やっぱりこうしましょう」というのがない。もしかしたら私のためにそうしてくれたのかもしれませんが、仕事は非常にやりやすかったです。
吉田:さすがに、松野さんだから特別そうしたわけではありません。ただ、今回よかったのは、松野さんと仕事をしてみたいという人たちと、松野さんのゲームが好きだという人たちが大勢いたことですね。『ファイナルファンタジー』を作っているので当然ですけど(笑)。「我こそは!」ときた人たちばかりだったんです。
『FFXIV』開発のコンテンツ担当は挙手制で決まるんです。例えば、パッチ4.Xシリーズのシナリオのなかでも「パッチ4.3は私が」「パッチ4.5は僕が」みたいな感じですね。バトルも同じで、中川が「これだけのボスがいるという話が吉田さんとシナリオチームからきたんだけど」と企画案をテーブルに広げて、バトルコンテンツを作っている人たちでリクエストを募ります。そのうえで、中川が各人のスケジュールを鑑みて担当を決めるんです。
そういう意味でもやりたいと思っているものを担当してもらっているので、そこの噛み合わせは必然的によくなります。そして、自分で挙手したからこそ、彼らはものすごく下調べをしてコンテンツ制作に挑むんです。“世界設定的にこうでないと”といったところや、原作があるものに対しては“オリジナルはどうだった”みたいなところですね。僕は、そういった並々ならぬ努力を欠かさないメンバーを本当に尊敬しています。
松野:オリジナルへの愛が強いのはこちらとしてはありがたかったですね。不要な説明をせずにすみますし、ノータッチでも良いものに仕上がるし。
吉田:愛があったうえで、“でもトレースするのはイヤなので自分たちで解釈して『FFXIV』らしくして「どうだスゴイだろ」と言ってやりたい”という思いで作っているようです。それはカットシーンでもそうですし、バトルでもそうです。そこのコダワリがみんなスゴイ。
僕は彼らの裁量の範囲を決めて、彼らでは決められない案件を、その場で即時ジャッジします。そうすることで、あとはみんなのモチベーションでゲームが出来ていきます。
――逆に、吉田さんとしては念願の松野さんとのプロジェクトでしたが、仕事をしてみていかがでしたか?
吉田:答えたいことがいっぱいありすぎて、何て言ったらいいんだろう(笑)。ネットとかには「松野は仕事が遅い」みたいな書き込みもありますが、僕は松野さんこそ仕事が一番速いんじゃないかという気がしていて。おそらく、松野さんの筆が進まないときは、こちらの準備なのか決めごとなのかはわかりませんが、何かが足りていないんだと思います。
松野:いやいや、そんなことはなく。単純に酒が足りないだけだったりして(笑)。たしかに禁酒していると筆の進みが遅いという自覚はあります(笑)
吉田:(笑)。全部そろったときの仕事は、ものすごく正確で速いんです。あと、近年の松野さんはシナリオで注目されがちなのですが、ゲームデザイナーとしてもやはり超一流だと感じました。それが最も表れているのが、この対談でも話題に出ていた“コスト感”ですね。「これを使えば取り回しがラクだよね」「昔のアートがあるなら、わざわざ新しく書き起こさず、そのための時間を作り込む時間に充ててクオリティを上げよう」といった部分です。プロットの段階で、打ち合わせをせずとも“ゲームを作る”前提で決められていて、これはもうゲームデザイナーとしての視点がないと書けないシナリオなんです。
『FFXIV』チームのレスポンスが速いと言っていただきましたが実際は逆で、「ここだけ決めれば大丈夫」というように詰めなくてはいけない部分が少ないから、レスポンスも早くできたわけです。
――では最後に松野さんから、ある意味バトンタッチ先となるヨコオ(※18)さんに向けて、メッセージをお願いします。
松野:ヨコオさんにですか? では……「キャラクターを殺さないシナリオを期待しています!」(笑)。いや、嘘です(笑)。
ヨコオさんとはちょくちょく呑む機会があるんですが、近々、呑む機会があるので、そのときに「『NieR』に特化しちゃうと置いてきぼりになる人が出てくるから気をつけて」といったことだけは話しておこうかなと思っています。真面目な話、今回の反省点だけはお伝えしておこうかな~と。まぁ、それはそれでハードルが上っちゃうのかもしれないけど(笑)。
一同:(笑)。
吉田:近々、齊藤さん(※19)と4人でメシ食いにいきますしね。「生放送しないのは勿体ない」って誰か言ってましたね。
松野:お酒を呑んじゃうと、たくさん喋っちゃう。しかも余計なことを(笑)。
吉田:ダメです、危ない危ない。その4人とか、ダメですよ絶対(笑)。

|
|---|
松野:ちなみにコラボレーションが決まってからヨコオさんには、「『FFXIV』をプレイしないと、わからない部分がたくさんありますよ」と言い続けていたんです。彼的には少し二の足を踏んでいたようなんですけど、齊藤さんに勧められたこともあったらしく、最近スタートしていましたね。
吉田:この前2人で食事したときに聞いたんですけど、過去に『ドラゴンクエストX』にハマりすぎて仕事がおろそかになったことを激しく後悔しているらしくて。オンラインRPGにハマっちゃうと引き返せないから、それで二の足を踏んでいたんでしょうね。
松野:齊藤さんは齊藤さんでスゴイですよね。もうイシュガルドに到達していますし。
吉田:あの人もものすごく忙しいはずなんですけどね。
松野:会社でやっているのかと思ったら、自宅に戻ってからプレイしているそうで。
吉田:オンラインRPGに関しては、あの人も並々ならぬ情熱を持っている方なので(笑)。
松野:けっこう寄り道をしているみたいで。各パッチが意外と長いですし、メインシナリオだけ追いかけていっても十分にレベルが上がるので、さっさと先に進んでしまったほうがいいと思うんですけどね。
吉田:齊藤さんは、プレイヤースキルが伴わないのがイヤなタイプなんですよ。『ワールド・オブ・ウォークラフト』に引き続き、『FFXIV』でもタンクをやっているらしいです。「どうせデータセンター内をテレポできるようになるんでしょう? そのあとで移動すればいいから、今はとりあえず優遇ワールドで育てるよ」って言ってましたね。
松野:極タイタン討滅戦に行って、タンクの洗礼を受ければいいんですよ(笑)。そういえば、ワールド間テレポっていつからでしたっけ?
吉田:4.57です。4月下旬には試していただけると思います。いろいろガラッと変わりそうですね。自分がやっていたことをより多くの人に見てもらえたり、もっと違う価値観の人と出会う機会が増えたりと、そういった面でまた盛り上がってもらえるんじゃないかなと思っています。まずは東京でのファンフェス、そしてそのあとの展開もぜひ楽しみにしていただければと思っています。
――ありがとうございました!

|
|---|
※1:織田万里氏/『FFXIV』の世界設定、メインシナリオを担当。
※2:鈴木健夫氏/『FFXIV』のリードアーティスト。
※3:石川夏子氏/『FFXIV』のメインシナリオライター。
※4:前廣和豊氏/『FFXIV』のシナリオセクション:マネージャー。
※5:公式設定資料集/Encyclopaedia Eorzea ~The World of FINAL FANTASY XIV~。
※6:雨宮慶太氏/有限会社クラウド代表。映画監督、イラストレーター。代表作は牙狼〈GARO〉など。
※7:吉田明彦氏/株式会社CyDesignation取締役。イラストレーター、ゲームデザイナー。『FFXIV』のイメージイラストなども手がける。
※8:中川誠貴氏/『FFXIV』のリードバトルコンテンツデザイナー。Mr.オズマの愛称で知られる。
※9:板鼻利幸氏/スクウェア・エニックス所属のゲームクリエイター、キャラクターデザイナー。
※10:セクシーアルテマ/「楽欲の僧院 オーボンヌ」の聖天使アルテマ戦で、聖天使アルテマが「デミ・ヴァルゴ」を使った際に出現するルカヴィ。『FFT』のボスである聖天使アルテマと同様に、セクシーな赤いハイレグ姿。
※11:マイケル・クリストファー・コージ・フォックス氏/『FFXIV』のローカライズディレクター。
※12:伊藤裕之氏/スクウェア・エニックスのゲームクリエイター。ATBやアビリティなど、『FF』の根幹を作り上げた。
※13:長尾隆央氏/テノール歌手にして光の戦士。
※14:皆葉英夫氏/『FFVI』『FFIX』『FFXII』などでアートディレクションを担当したアートデザイナー。現在は株式会社CyDesignation代表取締役社長。
※15:レアモンデ/PlayStationの名作『ベイグラントストーリー』で物語の舞台となった廃都。
※16:デュナミス/特定のアイテムを使って突入する特殊なエリア。実装当時は挑戦権取得競争が激しかった。
※17:海NM/ルモリアというエリアに出現するノートリアスモンスター。ルモリアには、クラゲやエイ、イカなど海洋生物をモチーフにしたモンスターが配置されていたため、プレイヤー間では海と呼ばれていた。
※18:ヨコオタロウ氏/『ドラッグオンドラグーン』シリーズや『NieR』シリーズを生み出した、ゲームクリエイター。パッチ5.Xで展開する「YoRHa: Dark Apocalypse 」のシナリオも担当。
※19:齊藤陽介氏/スクウェア・エニックス取締役執行役員。 『ドラゴンクエストX』『ドラゴンクエストXI』や『NieR』シリーズなどのプロデューサーを務める。
リターン・トゥ・イヴァリース最終章を最大限楽しむための振り返り&考察コラム
◆第1回:『FFXIV』でのダルマスカをめぐる情勢
◆第2回:イヴァリースへの導き――新たな物語の幕開け
◆第3回:絶海の孤島、リドルアナ大灯台へ
※本インタビューは2019年3月上旬に行われたものです。
(C) 2010 ‐ 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
データ