2017年9月4日(月)
竹安氏、外山氏が考えるゲームの新しさとは。『ザ・ロストチャイルド』クリエイタートークレポート第2回
オカルト雑誌のライター伊吹隼人となり、天使と悪魔と堕天使が争う“天魔抗争”を神に選ばれた“選民”として生き抜いていくPS4/PS Vita用ソフト『The Lost Child(ザ・ロストチャイルド)(TLC)』。

|
|---|
『エルシャダイ』の系譜を受け継ぐ“神話構想RPG”である本作の発売を記念して、本作のプロデューサー、竹安佐和記氏が運営するギャラリーエルシャダイに、竹安さんに縁のあるクリエイターがひそかに集結。
竹安氏を囲み、『エルシャダイ』にまつわる昔話から『TLC』に対する熱い想いまでざっくばらんに語る、特別な夜の第2弾をお届けします。
神話構想の夕べ
~『The Lost Child』発売記念スペシャルフリートーク~
【第1弾】『エルシャダイ』回顧録、そして『TLC』へ ~『TLC』生誕の秘密に迫る~
◆参加者:
角川ゲームス 竹安佐和記氏
(『TLC』プロデューサー・キャラクターデザイン)
株式会社Groove 代表 竹下和広氏
(元Ignition Entertainment Ltd.日本支店代表)
角川ゲームス 長谷川仁氏
(『TLC』開発ディレクター)
【第2弾/本記事】クリエイター同志対談 ~今、新しいって何?~
◆参加者:
角川ゲームス 竹安佐和記氏
(『TLC』プロデューサー・キャラクターデザイン)
ソニー・インタラクティブエンタテインメント 外山圭一郎氏
(『GRAVITY DAZE』シリーズ ディレクター)
【第3弾/今後公開予定】0Gauge(竹内良太、寺島愛、プログラマ寺島博樹)×『The Lost Child』 ~こんなコラボで大丈夫か? 大丈夫だ、問題ない~
◆参加者:
角川ゲームス 竹安佐和記氏
(『TLC』プロデューサー・キャラクターデザイン)
0Gauge(ゼロゲージ)バンドメンバー 寺島愛氏
(竹内良太(ルシフェル役)代理。現在『TLC』プレイ中かつコラボ楽曲制作者)

|
|---|
| ▲写真左から順に、外山さん、竹安さん。 |
そんな原点で大丈夫か? あの名言のルーツになったのは吉本新喜劇
──まず、お二人がお知り合いになられたきっかけから教えてください。
外山:初対面はかなり前です。当時のボクの上司の紹介で、「デザイナーが来たので会ってみないか」とフリーになったばっかりの竹安さんを紹介されたんですよ。そこでポートフォリオなどを見せていただいたんです。
竹安:『大神』が終わった直後で、ソニーさんにご挨拶に行ったらお会いできたんですよ。
外山:面接というわけではなかったのですが、うちもデザイナーさんを探していたんですね。
最初は若干面接的なモードだったのですが、ポートフォリオを見た瞬間にあまりにもおもしろくて、「この方は既成の仕事をどれぐらいできますかという話をするべき方ではない」と感じたので、もうそういう話はやめて、ポートフォリオにまつわるお話ばかり聞いていました。
『鉄騎』とかも描かれていて、どれだけ引き出しがあるのだろうと思いましたね。それまでもたくさんの方のポートフォリオを見る機会があったのですが、すごく印象に残ってます。
竹安:『Devil May Cry(デビル メイ クライ)』と『鉄騎』と『大神』と、あとはぼくの趣味の絵が入ってましたね。
外山:『大神』は色彩が鮮やかだけど和のテイスト、というのが斬新で、すごい人がいるものだなと思っていたんですよ。そこからしばらく経って、ある日雑誌を開いたときに『エルシャダイ』の記事があって、そこで竹安さんの名前を見てすごくビックリしたんです。
「この人はすごい人なんだよ」と周りに言っちゃうほどで。記事で初めて『エルシャダイ』を知ったときも「ほかの誰とも違うこの感じ、これだ!」と思いました。竹安さんがディレクションして自分の世界観で作品を作ったのがすごくうれしくて。
それから、竹安さんとは柴田さん(※柴田誠氏。『零』シリーズのディレクターを務める)と一緒に飲みの席などで懇意にしていただいて、いつか一緒にお仕事できないかと思っていました。
先日配信された『GRAVITY DAZE 2(グラビティデイズ2)(GD2)』のDLCで、ようやくゲストキャラクターデザインとしてお仕事をお願いできました。
──もともとのオファーは『GRAVITY DAZE(グラビティデイズ)(GD)』の1作目からあったとお聞きしています。
外山:はい。もともとは前作の時からお願いしていました。じつは1作目も追加でDLCの構想があったのですが、そのときは続編に移行しようということで、今回はごめんなさいという形になったんです。
竹安:東京ゲームショウで呼ばれてお願いされたんですよね。なつかしいなぁ。
──『GD2』のDLCは、どのようなオーダーで描かれたのでしょうか?
外山:言ってしまえば、DLCのなかのラスボスというキャラクターなのですが、それが設定的にすごく難しかったんですよ。
具象的な何かでもないし、遺跡かもしれないし、神様かもしれないし、データかもしれない。極めてあいまいな文章の設定しかないものだったので、「どこにもないものを形にできるのは竹安さんしかいない」と思って、すぐに竹安さんに頼んだんです。

|
|---|
竹安:それもオーダーですよね。「どこにもないもの」というオーダーだったので、「それならどこでも見たことがない物を描こう」と思って。やっぱり、「俺の世界を形にしてやるぜ」というのではないんですよね。そもそも、あまり自分の世界を持っているとは思っていないので。
外山:あまりにも漠然としたイメージだったので、正解という物はなかったんです。それでも自分なりにやっぱり少しは想像してはいたのですが、竹安さんからいただいたラフはそれともまた違う。わりとたくさんラフをいただいたんです。けっこう長い間、やり取りをしたのですが、やり取りするなかで見えてきた感じですね。
竹安:ゲームの設定はいただいてましたね。ゲームの設定に即して、わりと筋が通って形状が見えている物にしないといけないな、というのはありました。そこはルールを入れようかな、と。
外山:そうですね。お仕事をやり取りするなかで「あ、すごくそういうところを気にされる方だったんだな」というのが意外といえば意外でした。
竹安:いつもボク、“意外”と言われるんですよ(笑)。
外山:どちらかというと、理屈を突き詰めて創作されるタイプですよね。「どこをどういう風に動いて、どういう攻撃をするのか知りたい」とリクエストを受けたので、プランナーを呼んでやり取りしました。
竹安:そうそう。2時間くらい閉じ込められて、できたてのビルドとか遊んでましたよね。
外山:そうなんですよ(笑)。「ゲームから何かフィードバックが欲しい」ということだったので。
竹安:思い出を集めるのがDLCのテーマだったから、体に思い出のパーツをいっぱいつけてるんですよ。でも最初の何もないところに思い出をつけていったら「なんかまとまんないなぁ」と。
かと言って、まとめすぎちゃうとファンタジーになっちゃうんですよ。リアルって、そこにある理屈によって起こっている現象にすぎないので。そういったところも考えながらずーっとチクチクチクチクつけてましたね。
外山:脅威だけど何を考えているのかわからない感じが欲しかったのですが、最終的にいいところに落ち着きました。
パッと見で「こいつ怖い」というだけでもなく、本当にふざけているのか、怖がらせようとしているのかわからない存在。子どもの妄想チックなところも含めて本当にうまく作っていただけました。
竹安:おだてるわけじゃないですが、それは外山さんの感性が非常に高いからやりやすかったんですよ。
目線がすごく高いので、既視感で物事を考えるのではなくて、ゲームのつじつまや理屈の先で形状を考えてくれる。自分が今まで見てきたアニメや漫画の“好き”で語るタイプの方にはない、すごくクールな嗜好性がカッコよかったですね。
外山:おもしろかったのは、『GD』を作ってきたときにバンドデシネというフランスのコミックジャンルに影響された部分があったので、『エルシャダイ』をはじめて見た時、ボクは当然竹安さんにもそういうところがあると思っていたんです。
でも竹安さんに「バンドデシネがお好きなのですね」と聞いたら、「なんですかそれ?」と言われまして(笑)。あれにはビックリしました。
竹安:最近まともに知り出したくらいで、本当に知らなかったんですよ、バンドデシネ。よく「バンドデシネっぽいですね」とは言われるんですけど、なんのことかわからなくて。失礼に聞こえたら申し訳ないのですが、まったく興味がなかったんです。
あんまりこういうことを言うと誤解されると思うのですが、あこがれているスタンスとしては、矢沢永吉さんなんです。
外山:今日はじめてお聞きしました(笑)。
竹安:矢沢さんには、有無を言わせずみんなに「あの人はナンバーワンだ」って思わせるパワーがある。そこがカッコいいなって。そういう憧れがあるんですよね。
人って何に感動しているんだろうといつも考えているんですよ。やっぱり、他人と考えがずれているんだろうなっていつもモヤモヤしてますけど。

|
|---|
外山:『エルシャダイ』の斬新な表現の数々に対して、ルーツとして何に影響を受けたかお話を聞いてみると、身近なものを挙げられることが多いんです。“吉本新喜劇”がルーツだといわれたこともあります。
竹安:掛け合いの部分ですね。
外山:「こんな装備で大丈夫か?」「大丈夫だ、問題ない」って、どうやったらこういう展開が出てくるのか聞いたら、「新喜劇がルーツです」って。
竹安:ずっと新喜劇を見ていたんですよ。今回の『TLC』も、電源を入れると最初にルシフェルの解説が始まるんですけど、それも新喜劇に影響を受けた部分です。
最初に権利表記がどうとか、つまらないことを言われるじゃないですか。それを本当につまらなくやると、たぶんおもしろいのかなと思って。
みんなが思っていることや、たぶんみんなはこう思っているだろう、というところをやれば共感を得られるから、長い文章でも聞いてくれるかなと思って。
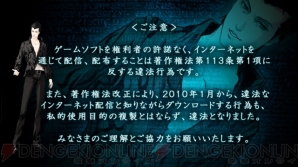
|
|---|
外山:見たものの咀嚼力がすごいですよね。それが竹安さんのすごいところだと思います。
竹安:まあ、ニッチな能力かな、とは思っています(笑)。
『TLC』の実制作における竹安さんが果たした役割
──竹安さんから見た、外山さんの人間像というか、クリエイター像や作品の印象はいかがですか?
竹安:もともと、カプコン時代から外山さんが手がけた『SILENT HILL(サイレントヒル)』や『SIREN(サイレン)』は見ていて、カプコン社内ではずっとライバル視していた方なんですよ。
『GD』シリーズも世界観にすごい振れ幅があって、本当に業界のトップクリエイターで雲の上の人だと思っていました。まさか、その本人に会えるとは思わなかったので、最初はすごく恐縮しましたし、こうやってしゃべれるとは思ってもみなかったです。
実際お会いしてみると、イケイケのディレクターじゃなくて知的なディレクターだなと感じまして、すごく話しやすい方だと思いました。普段そんなに会うわけではないのですが、会うと仲のいい友だちみたいな感じになります。
外山:ボクらが会うときによく一緒になったのが『零』シリーズの柴田さんなのですが、あの人とよく一緒に飲んで話したりしています。
竹安:柴田さんもおもしろい方ですよね。あの方もオシャレなディレクターだなと思います。
──作る過程でのカラーや人となりは、ユーザー側からだとわかりにくい部分があるのですが、作品ににじみ出てくるものなのでしょうか?
竹安:個性って作品からにじみ出てくるものだと思うので、そういうことだと思います。逆に出さないでおこう、出さないでおこうと思ってもにじみ出てきちゃうものかなと。
外山:それは確かにありますね。
竹安:だから、個性を出そうと思ったことはないですね。作ったものを見られると、結局「これアンタが作ったんだろう」と言われますし。『TLC』もできるだけバレないようにしよう、バレないようにしよう、とやってました。最終的に、バレないどころか「前面に出ろ」って言われちゃいましたけど(笑)。

|
|---|
──先日、金子一馬さんと対談されていましたが、『TLC』は悪魔を使役する現代劇ということで、どうしても周囲から『女神転生』シリーズと比較された部分があると思います。そこは、ある程度想定していたのですか?
竹安:そうですね。ボクもゲームがあらためて形になった段階で「RPGにしたら、やっぱり『女神転生』みたいになったな」と思ったので(笑)。それをひた隠しにするよりはむしろ、前面に出しちゃったほうがいいんじゃないかなと思いました。
『女神転生』みたいだからよくないという気持ちはあまりなくて、ゲームを見たときに、「むしろ、それっぽいことをスタート地点にして、最後はどう楽しんでもらうか考えよう」と思ったんです。
──今は、昔以上に100%オリジナルではないとダメという雰囲気はなくなっているような気はします。何かに似ていてもそこに新しい世界があったり。
竹安:そもそも新しいものといっても、やりつくされている感はありますよね。それに、企業も簡単にリスクを負えない時代ですから。だから、なるべく既視感があってユーザーが安心して手に取りやすいものをベースにして考える流れはあると思います。
外山:『TLC』は、まだPVを見せていただいただけでゲームはプレイできていないのですが、実際に手を動かされて作られている方たちが、すごく若いのかなと感じました。今の日本的な感じというか。
竹安:そうですね。昔からコンシューマーを作っていた方々みたいなのですが……。ディレクターが長谷川さんなので、じつはボクは開発メンバーとはほとんどあってないんですよ。
外山:そういう意味では、竹安さんのコンセプトというか種が軸になって生まれたところと、現代的なところが、いい意味でカオス感というか、不思議な世界観になってますね。
竹安:実際に遊べば、そういった意味では独自の世界を感じてもらえるかなと思います。
──ある意味では、『女神転生』のほかに『ウィザードリィ』的な肌触りもありますね。竹安さん的には、『TLC』で何か新しさを出さなければいけない、みたいな気持ちはあったのですか?
竹安:『エルシャダイ』を作り終わったあと、ボクは神話構想というコンテンツをずっと作ってきて、ファンの方がそれについてきてくださっていたんです。
ですから、『エルシャダイ』という名前で売るなら、その人たちを裏切りたくないなというのはありました。だから、『エルシャダイ』というより、神話構想を知っている人たちが、クスリとする種をいっぱい入れさせてもらった感じですね。
システム面でいうと、ゲームを遊んでみて、普通に面白いとは思ったのですが、最初に遊んだビルドだと難易度が高いと思ったんです。よく作られているのですが、いろいろなところをがんばって作りすぎるとそれぞれがケンカしちゃうじゃないですか。どこかを突出させたら、どこかを抜かないといけない。
だからそのバランスは多少調整しました。そのほか、ビジュアル面でも多少気になった点は修正させてもらいました。胸のテカりを減らしてエロゲーっぽさを抑えたり、ピンク調に見えた背景をぼかして凛とした感じにして、クトゥルーに似合う色味にしたり……。
あとホラーにはよくあるのですが、“じつは何の意味もないんだけど、コレがあると怖いよ”という感じの物をちりばめました。最初に出てくる女子高生が、いきなり血痕がいっぱいついて現れるのですが、これ、ゲーム中ではどういうことなのか一切説明しないんです。
最終的にできあがったときに「もしかしてこのゲームに出てくる人って全部死んでるんですか?」とスタッフに言われて。それを聞いていい反応だなって思いました。畏怖を感じてもらえるということは、妄想の広がる世界に仕上がったことの証明だと思うので。

|
|---|
外山:要所要所で具体的な監修をされてるんですね。
竹安:最後、前面に出ろって言われたときに、「やれることをやらないとな」と思ったので、ちょっと口だしていいですかと、最後の3カ月くらい口を出させてもらいました。なんだろう。カレーにガラムマサラを入れた感じですかね?
──料理で例えるならレシピを考えて、最後に味の調整をした感じですね。
竹安:あと、開発の人たちもボクと同じことを考えていた人もいると思うんですよ。でも、なんか言い出しにくい空気ってあるじゃないですか。ボクは第3者視点だし、もともと言い出しっぺなので、そういう意味では言いやすかったですし、みんな聞いてくれました。
──そういう意味では、前回のレポートでおっしゃっていたような恐怖政治は……
竹安:いやいや、全然してないです。恐怖政治はいっさいしてないです。本当にお願いする感じでした(笑)。
新しいものは本当にいいものなのか? 2人が考える新しさとは
──外山さんは、ゲーム作りで自分の意思を伝えるとき、どういう風にされているのでしょうか。
外山:竹安さんが先ほどおっしゃっていたのと同じく、ボクも自分のタイプで言うとコンセプト型だと思っていて、具体的にアウトプットをこうしたいというのは、基本的にはやらないようにしています。
あとは、最近とくに意識するのは、作品はチームありきというか、チームのスタッフ個人の能力の総量でできるということです。どういう風な種の蒔き方をすると、よく育つのか、良さが出るのか、というところをすごく意識するようになりました。
うちのスタッフにも「具体的にああしろこうしろと言われない」とよく言われるのですが、実際言わないようにしています。結果的には、お互いの関係性ですかね。すごく少ない言葉とか、お互いのやり取りの中で、お互いにきっとこういうことを言ってほしいんだろうな、というところを感じるとか。
そういった感じの関係性でチーム作りを進めてきてだいぶ長いので、最近はああしてこうしてというのはほとんどないですね。本当に特殊だと思います。ボクは本当にコアなスタッフと長く組ませてもらって、ゼロからプランニングするというスタイルのプロジェクトだけを今までやらせてもらってきたので。条件が違うとまた全然違うと思いますが、今まではそんな感じです。
──そういう意味で言えば、竹安さんはチームを組んで長くやる作り方とは違いますね。
竹安:いろいろなタイプの仕事をしていますからね。外山さんがおっしゃったようなチームの仕事もやりましたし、指示を受けてやるのもありましたし、いろいろなことをやっているからケースバイケースですね。毎回、カメレオンのように自分が合わせていく感じかな。
外山:竹安さんは総合ディレクターであり、アートディレクターでもあり、原作者でもありというか。立ち位置としても珍しいタイプですよね。
竹安:たまたまですけどね。よく言われるんですよ。竹安さんみたいな人はいないよねって。
外山:竹安さんみたいな人はいないよね、は同意します。この業界では本当にいないです。
竹安:自分としては、できるだけ普通にしようと思ってやっているだけなんですが(笑)。
外山:DIY力というか。それ、自分でやっちゃうんだという驚きがあります。
竹安:「それ、自分でやっちゃうんですか?」とは確かによく言われます。
外山:それが本当に不思議ですね。自分は基本、会社員としてプロジェクトをやったことしかないので根本の発想から違っていて。自分でやっちゃえばいいやと思ったから自分でやりました、みたいな感じがすごく自由というか。
竹安:さっきも言いましたが、お仕事はその人のオーダーに応えようとしてやるので。自分でやりたいなら自分でお金を出してやればいいと本当に思っちゃうんですよ。自分でお金を出すと規模が小さくなりますけど、でもそれが自分の実力だと思うんです。もっと大きい規模でやりたいなら、大きくなれるように努力するしかないと思うんですよね。
──他人からのオーダーで、たとえば“より新しいもの”を求められたりして、産みの苦しみを感じることはありますか?
竹安:うーん……。仕事をする上で最初に考えるのは、一緒に仕事をする人たちのスキルのことです。みんなが漫画やアニメに精通している人ならそのレベルに合わせるし、そうじゃないなら一番理解していない人に合わせます。
こちらで合わせていかないといけないというのがあるので、苦労するというか、時間を割くのは、一緒に仕事をする人たちを理解することですね。チャネリングみたいに、ずっとその人のことを考えてます。
──意識のすり合わせというか、向いている方向を合わせるのに時間をかける、と。
竹安:そうですね。あと、ボクはやり直しが嫌いなんで、基本的にトライアル&エラーってしないんですよ。絵も一発描きだし、文章もほぼ一発で書いちゃう。外山さんのときのように、相手の意見に合わせて修正するようなトライアル&エラーはやりますが、それも相当ラフな段階で出して、だんだん軸を合わせていく感じです。
そういう意味でも一番苦労するのは、一緒に仕事する人とのコミュニケーションかな? そこに一番時間をかけますね。その傾向が年々強くなっています。でも、ボクはみんなそうなんじゃないかなと思いますよ。
──外山さんは、新しい物を作るうえで一番苦労されることはなんでしょうか。
外山:そうですね……、新しい物と言うよりはゲーム制作全般に言えることかもしれませんが、プロジェクトとして成立させるにあたって、“わかりやすい新しさ”があったほうが、やっぱりやりやすいところもあります。ボク自身は業界に入って古い人間なので、新要素、新システム、といった“新しいメカニック”から入りがちなタイプなんですよ。
ただ、そのやり方がベストなのかどうかは、周囲の環境がすごく変わりつつあるので、ちょっと悩んでいるところですね。今までいうと、『SIREN』の視界ジャックや『GD』の重力操作のような“新しいこと”は、はたしてユーザーさんにとって絶対必要なものなのか。今は、そういうことじゃなくなりつつあるのかなって。市場の変化もあって、最近ちょっと悩んでいたりしますね。

|
|---|
竹安:新しいってなんだろうって話ですよね。
──昔は技術革新により新しいハードが生まれると、そのスペックを活かしたギミックには求心力が生まれましたが、今では昔のアイデアでも一周回って改めての発見があるなど、必ずしも新しい物が求められているわけではない感じはします。
外山:そうです。「ゲームのギミックとして何かこれまでになかったものは必須か?」と言われると、じつはそんなことはなくて。はっきりいって、“それが存在しなくても受け入れられている作品”は現在たくさんあります。ゲームクリエイターとしては、なかなか難しくもあり、おもしろくもあり、という状況ですね。
竹安:昔の我々って高いクオリティをずっと見たいと思ってきましたが、今の人たちは高いクオリティと低いクオリティを同時に見るところからスタートしてしまうから、クオリティというよりは、これはこういうところがいいね、これはああいうところがいいね、と、すごく客観視しているところがあると思うんですよ。
動画もそうじゃないですか。昔だったら、きれいな画質で見たいと思っていましたが、今はニコニコ動画やYoutubeの低画質の動画でも常に見られ続けていて、じゃあ、Blu-rayディスクで買うかと言ったら、必ずしもそうじゃないじゃない。
──たとえば、ニコニコ動画だったら画質が落ちてもコメントを一緒に見たいという需要のもとに、それを見るということですよね。
竹安:そうです。ユーザーさんの母数がすごく広がったから、昔よりも感性が広がって豊かになったんじゃないかと思うんです。
外山:そうですよね。今の若い人たちは新しいことに価値を置いてないですね。やっぱり、コミュニティの中で機能するかとか、そういうことに重きを置いているんだなと感じますね。
竹安:ボク、外山さんと話しているから言いやすいんですけど、モノづくりをしてくるとだんだん作家性が強くなって芸術を志向しがちになるのですが、それってもしかしたら若いころのノスタルジーに浸ってるだけじゃないかと思うんですよ。
それはそれでいいと思うのですが、でも結局そこに浸りきるならシャットダウンして山の中にこもったほうがいい。市場に問いかける以上は市場に評価をいただくので、作家性を追及しちゃうとウケない可能性が高いと思ってるんですよ。
だから最近は、ボクより目上のクリエイターが嫌がることがたぶんいいんだろうなと思っています(笑)。「お前、何やってるんだよ」と言われるほうが、たぶん若い人にとっては新しくて新鮮で、一周しているといわれていいんじゃないかなと。
外山:そうですね。それらは音楽や映画でも既にあったことでもあると思います。竹安さんは殻を作らない感性がすごいなと思うんですよ。やっぱり、いい年になってくると殻を作りたくなっちゃうこともありますから。
竹安:わかります。ボクは殻が砕けた決定的な瞬間があって。技術的な話になっちゃうんですけど昔“Softimage3D”ってあったじゃないですか。もうサービス終了したソフトウェアなんですけど。ボクはアレの技術をものすごくつけたんですよ。
でもサービスが終了して、“Softimage3D”はいっさい使えなくなってしまった。もちろん、基礎的なところは生きるのですが、「オレの8年間どうしてくれるんだよ!」と(笑)。クッソー、じゃあ“ZBrush”に行くしかないのかって。
外山:やってないんですか?
竹安:一応、この間ワコムのイベントにはいきました。
外山:ボクは完全に趣味だけどやってます。楽しいですよ。今までの“デジタルとしての手順”みたいなのが全部吹っ飛んで、すごくいいですよ。
竹安:ちょっと話がずれちゃいましたがw
竹安さんのフットワークの軽さのルーツは“失恋の捉え方”にアリ?
──何らかの方向に最適化しすぎると危ないということですね。
竹安:そうですね。世の中の人に求められる物を作り続けるのだったら、やっぱり自分のこだわりはないほうがいいのかな、という考えは年々強くなっています。
外山:と言っても、絵描きの作風やディレクターのディレクションの方向性とか、そういう次元でもなくて、「経理もやったほうが都合いいんだったらやろう」、とスッとやれてしまうのが竹安さんの思い切りの良さですよね。営業もやれちゃうんじゃないですか?
竹安:昔よく言われました。個展でも、設営は自分でやるんです。10分後にサイン会が始まるのに自分は段ボールを運んでいて、何にも準備してない(笑)。
外山:これは俺の仕事じゃないわ、という感じをこんなに微塵も感じない人ってめずらしいですよ。
竹安:コストがかからないならそのほうがいいじゃないかと思っちゃうので。人を雇うとお金がかかるし、めんどくさいし、言うことを聞いてもらわないといけなくなる。じゃあ自分でやったほうがいいわ、と自分でやってたら驚かれてしまうんですよね。
ギャラリーエルシャダイの企画展も、企画から設営まで自分でやってると言うと驚かれる。でも要は、自分でやるほうが好きというか楽なんです。
外山:吉川さん(※吉川達哉氏。代表作に『ブレス オブ ファイア』シリーズのキャラクターデザインなど。竹安氏にとってカプコン時代の先輩にあたる)は、あまりご本人は露出が好きじゃなくて、「いつかは個展を開きたいけどオリジナル作品が少ないし……」みたいなことをおっしゃっていたのに、竹安さんが声をかけてあっという間に個展を実現してしまって。
竹安さんの殻のなさが周りにも良い影響を与えている好例ですよね。ファンも喜んでいますし、吉川さんも「こういう機会があってよかった」とおっしゃってますし。周りが本当に楽しんでいるのが竹安さんのいいところですよね。
竹安:そういうのができたらいいかなと思ってやっているだけですよ。
外山:本当にうらやましいです。すごいな、と。ボクだと「何言ってるんだろうこの人」って思われるんじゃないかとか、「失敗したらどうしよう」というのが先に立ってしまうので。
竹安:いや、思われることもありますよ。でも、思われても「思われちゃったー」で終わるので。
外山:強いですね。
竹安:強いというよりなんでしょうね……。それで今思い出したのですが、昔友だちに言われたことが衝撃的で。恋愛で失恋すると、悲しいじゃないですか。「失恋って悲しいよね」って友だちに言ったら、「お前、それは好きなやつが少ないんだよ」と言われて。
「1人だけ好きになっていたらお前、そりゃしんどいわ。いいやついっぱいいるだろ」って言うんですよ。「同級生だったら誰かいけるだろ、と思うから、そんな悲しくなったりしないよ」って言われて。
ソイツは実際、フラれまくってもぜんぜん元気で「まだまだいるわー」みたいな感じで(笑)。そのたくましさはすごいなと思って、尊敬していたことがありましたね。

|
|---|
外山:竹安さんがタフなのはその影響があるんですかね(笑)。周りにはそういう方が結構多かったんですか?
竹安:ヤンキーの友だちとか、たくましかった人間は周りに多かったですね。傷つかない、という感性を持っているやつはいました。……大丈夫かな、この対談(笑)。
将来はハイパーなクリエイターに……?
──お互い、こういうことをぜひやって欲しいという希望はありますか?
竹安:外山さんに希望することなんてないですよ。今まで通り、SIEでPlayStationの最先端というものはこういうものだ、というのを示してくれれば、なるほどここが基軸かってわかりますので、それだけかなぁ。
外山さんのことはPlayStationのベンチマークみたいな人だと思っているんです。だから、外山さんがいなくなったら日本のゲーム業界はさみしくなるなぁ、と思っていて、本当に最後の砦みたいに感じています。
外山:苦しいですけどね(笑)。
──やっぱりSIEという会社は、ソフト制作の際、技術的な面も含めて新しいことにチャレンジしやすいですか?
外山:それはすごくしやすいです。やっぱり、初期段階のプラットフォームは軌道に乗るまで、サードさんがなかなか大きい投資をしにくいところだと思うので。
自分たちも「商売をまったく考えなくていい」とまでは言われませんが、ハードのポテンシャルを引き出すような仕事をする、というのはミッションというか使命に入っています。ボクとしては自分のやりたいことと近いので、本当にいい環境ですね。
最近だとPlayStation VR(PS VR)にすごくワクワクしています。そういえば、PS VRの本で“PlayStation VRを体感せよ(PHP研究所・刊)”ってあるじゃないですか。あれに竹安さんが絡んでると聞いてビックリしました。
竹安:それ、SIEがPS VRを出すと聞いて「それならVRの本が作れるんじゃないか」と思って、ボクがやりたいと言って作ってもらった本なんです。理由はSIEの受付にその本があったら絶対ウケるだろうと思ったからです(笑)。
外山:まんまと置いてありますからね(笑)。その殻のなさは本当にすごいと思います。普通少しは躊躇しますよね。それは俺の畑じゃないって。
竹安:でもすごくやりたかったんです。PS VRって革命的なデバイスじゃないですか。昔からウォークマンを作った人々の本とか、“ソニーの出井革命”とか、そういうソニーの歴史の本を昔から読んでいたので、そういう本をボクも書きたかったんですよ。で、PS VRが出ると聞いて、今の人脈ならいけるんじゃないかなと思った。
外山:仮にPS VRで何か、ともちかけたら、クリエイター100人のうち99人はVRを使ったゲームの企画を考えると思うんです。そこで「本を書こう」という発想に行くのがすごいですよね。
竹安:すごくいろいろできたので、うれしかったです。昔、VAIOっていうコンピューターが好きで、ボクは「なんとかVAIOに関わりたい」とアスキーの人にすごいお願いしたら、「じゃあ工場見学に行きましょう」となって、そこで自分のVAIOを作ってもらったり、週刊アスキーで『パソコンが好きだ!』VAIO Zツアーの記事の連載をできたりして。本当に好きでやれてましたね。
外山:まるでハイパー○○クリエイターですね。
竹安:(笑)
──確かに、ジャンルを横断して活動されている竹安さんは、ハイパー○○クリエイターと言えますね。
竹安:そういうのはカッコ悪いですよ。ワクワクが先に立っちゃって、頭の中でずっと想像するんですよ。「ソニーの受付に俺の書いた本があったらウケるな」と(笑)。
──では、外山さんが今後竹安さんに期待するところはありますか?
外山:それはもう、ハイパー○○クリエイターです(笑)。ハイパー○○クリエイターとしての驚きに期待しますね。「普通にゲーム作ってください」と言ってる場合じゃない。今度は何でビックリさせてくれるのか、今から楽しみです。
竹安:何か面白いことができたらと思っています。
外山:竹安さんは本当に起業家というか、根っからのベンチャー気質ですよね。
竹安:こういうのがベンチャー気質なんですかね?
外山:ご本人は自覚してらっしゃらないようですが、息をするようにベンチャーですよね。本当にすごい人だなぁ。
竹安:でも言われてみれば、確かに組織に所属するのにもあまり興味がないですし、自由自在に生きているなと自分では思いますね。それと、ボクがゲーム制作を終えると、所属している組織も終わることが多くて……角川ゲームスは大丈夫だと思いますが(笑)。自分がいると会社がよくなくなるんですよ。全然そんなこと望んでないんですけど(苦笑)。

|
|---|
──最後に、お互いへのエールで対談を締めさせてください。
竹安:外山さんにエールを送ることがあるとしたら、技術力もあるし感性も高い方なので、あとは今どきの若者の気持ちをつかんでいただければ、もう他の追随を許さない人になるんじゃないかなと思います。……エールになってるのかなこれ?
外山:う~ん、できないです(苦笑)。ボクからは、今回の『TLC』で、またたくさんのユーザーさんが竹安さんに興味を持つきっかけになったと思いますので、これを一過性で終わらせず、どんどんどんいろんな人を驚かせて、違う世界を見せたり人の人生を曲げるきっかけになって欲しいですね(笑)。世の中にはこんなことがあるんだぞと、ぜひ竹安さんに見せつけて欲しい。ボクもその1人として刺激を受けたいです。
竹安:なるほど。確かにあこがれている人が岡本太郎とかですからね。ああいう方に対するあこがれが昔からずっとあるんですよね。誰にも似ていないっていいなって。あまり好かれたくないとも思いますし。マゾっ気があるので、むしろ嫌われていると「この人、すごく俺のこと考えてくれるんだな」って思っちゃうんですよ(笑)。
最終回となる第3回では、ルシフェル役の竹内良太さんの奥さんである、寺島愛さんが登場。現在製作中の『TLC』とのコラボ楽曲はどんな内容になるのかなどを語ってもらっています。
ちなみに、ギャラリーエルシャダイでは、『TLC』の発売を記念して、9月26日まで“ザ・ロストチャイルド展”を開催中。本作に興味をもたれた方はぜひこちらにも足を運んでみてください。
(C)2017 KADOKAWA GAMES
データ