2015年1月1日(木)
PS『闘神伝』20周年記念。2Dと3Dの狭間から生まれた対戦格闘の魅力を振り返る【周年連載】
あの名作の発売から、5年、10年、20年……。そんな名作への感謝を込めた電撃オンライン独自のお祝い企画として展開中の“周年連載”。連載第15回となる今回は、1995年1月1日にタカラ(現タカラトミー)から発売されたプレイステーション用3D対戦格闘『闘神伝』のコラムをお届けします。

|
|---|
| ▲ポリゴンで描かれたキャラクターが自由に動き回る本作。PS本体の発売からわずか1カ月後にこのクオリティで発売されたことや、元日に発売されたことなどもインパクトがありました。 |
■自分にとってコンシューマでの3D対戦格闘との出会いは『闘神伝』でした
今でこそ3D対戦格闘はゲームの1ジャンルとして世のユーザーに認知されていますが、本作が発売された1995年はコンシューマには3D対戦格闘のタイトル自体がほぼ存在していませんでした。
もちろん、アーケードで『バーチャファイター』や『鉄拳』といった3D対戦格闘はありましたが、ゲームセンターでは遊ばず、セガサターンを持っていなかった当時の自分にとっては、対戦格闘といえばドットで描かれた2Dキャラクターがぶつかり合うものというイメージでした。そんな自分にとって、本作の登場は衝撃的だったのです。

|

|
|
|---|---|---|

|

|
|
|---|---|---|
| ▲対戦格闘といえば、胴着を着た男たちがぶつかり合うとイメージがあった当時。個々のキャラクターのビジュアルも新鮮でした。 | ||
奥行きのあるステージに、リングアウトという体力と関係なく勝敗を決める要素。そういった3Dらしい部分がありながら、ゲームシステムの基本は2D対戦格闘のものを踏襲しているというわかりやすさに、即購入を決意しました。

|
|---|

|
|---|
| ▲隠しキャラクターの2人は、キャラ選択時のイラストがないのでバトル中の写真を用意しました。 |
そう、本作はビジュアルこそ3Dですが、ジャンプあり飛び道具ありと基本システムは2D対戦格闘がベース。コンボもしゃがみ弱キック→立ち弱武器攻撃→立ち弱キック→立ち強武器攻撃→必殺技などという、2D対戦格闘らしいものが満載でした。
さらに本作の特徴として、必殺技をボタン1つで繰り出せるボタン設定が可能だったことも忘れてはいけません。ボタンの同時押しで秘伝必殺技(体力が残りわずかになると繰り出せる大ダメージの攻撃。いわゆる超必殺技)も繰り出せ、コマンド入力が下手でも十分に対戦を楽しめたのです。
当時は休日に友人と集まって、朝から夕方までプレイし続けることもしばしばでした。今でこそたいていのコマンドは自由自在に繰り出せる自分ですが、正直、対戦格闘で通常技と必殺技を使い分ける楽しみを知ったのは本作がきっかけといっても過言ではありません。こういう簡単操作は、“初心者にも楽しんでほしい”とうたう対戦格闘には、ぜひ実装してほしいシステムですね。

|
|---|
| ▲飛び道具も突進技も自由自在! 対戦格闘初心者にとって、必殺技を出したい時に出せるというのはうれしいものです。 |
ただし、多くの対戦格闘と同じように本作の必殺技は“弱”で入力するか“強”で入力するかで隙や威力、攻撃モーションなどが異なりますが、ワンボタンで繰り出せる必殺技はどのキャラクターでも共通で“強”のものだけ。きちんとコマンドを入力できる人は、必殺技の“弱”と“強”を使い分けることで初心者よりも多彩な立ち回りができるわけです。
初心者に優しいシステムでありながら、上級者が利用してもそれほど便利にはならない。しかも、初心者は“弱”必殺技を自分で出せるようにステップアップしていく余地が残されているわけで、このシステムは秀逸なものだと思います。弾速が遅い“弱”の飛び道具を盾にして相手に接近するなどという動きができるようになった時は、それはもううれしかったものです。
■相手の飛び道具にはジャンプかガード? いや、側転だ!
さて、そういった2D対戦格闘と3D対戦格闘の要素をあわせ持った本作の中でも特徴的だったのが、画面の奥や手前に移動する側転の存在です。本作は多くのキャラクターが飛び道具を使用できますが、この側転のおかげで対戦格闘初心者にありがちな、相手の飛び道具に対処できなくて負けるということはほとんどありません。
勝敗を決する部分でも側転の存在は重要で、リング直前まで追い込まれても側転でリング際から脱出。反撃で逆に相手をリングアウトさせるなどという最後まで気を抜けない、スリルあふれるバトルが楽しめました。
ちなみにこのリングアウトは、さまざまな状況でも発生します。相手を追いかけようとダッシュしたらそのままリングの外へ。相手の攻撃をガードしようとしたらダッシュで押し出される。空中からの必殺技で攻撃しようとしたらそのままリングの外へ直滑降……と、いろいろな形でリングアウトしましたし、されました。
このリングアウトのしやすさも、ある意味で本作の魅力だったと思います。ピンチになったらあえてリング際に近づき、相手のミスを狙う戦い方もできました。時にはどれだけバカバカしくリングアウトできるかを競うなどという、妙な遊び方もしましたね。それだけ本作のリングアウトには逆転性とおもしろさが詰まっていたと思います。

|
|---|
| ▲こんなリングアウトギリギリの状況でも、まだ勝敗はわからない。そんなところも本作の魅力です。 |
■隠しコマンドもバッチリ搭載!
そうそう、『闘神伝』といえば忘れられないのが豊富な隠しコマンドです。本作はタイトル画面の表示後、2秒弱の時間をかけて“1PGAME”、“OPTIONS”といった各種モード選択の表示が流れてくる演出になっています。この演出中に↓\→+弱武器攻撃の入力で1人目の隠しキャラクター・ガイアが使用可能になります。
さらにそのままゲームを始めずに、デモ画面→プロローグ画面→タイトル画面と移行したところで→↓\+弱武器攻撃の入力で2人目の隠しキャラクター・ショウを使用可能になり、3回目のタイトル画面で\+弱キックを入力するとボタンの同時押しで秘伝必殺技2(隠し必殺技のようなもの。詳しくは後述)が使えるようになります。
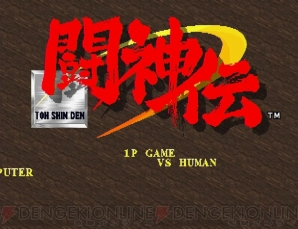
|
|---|
| ▲このタイミングでコマンド入力。成功すれば「FIGHT!」や「FANTASTIC!!」というボイスとともに、各種モード選択の表示の色が変わる親切設計です。 |
そんなわけで、友人と集まった時はタイトル画面を3回見てからプレイを始めるのがお約束。自分と同じように当時遊んだ人の中には「“ドゥーン(効果音)”旅立つ者たちがいる」というプロローグの冒頭を聞いた直後にタイトル画面までスキップした記憶がある人も多いことでしょう。
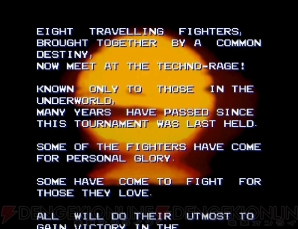
|
|---|
| ▲数え切れないほど見たオープニング画面。隠しコマンドは、いまだに指が覚えています(笑)。 |
さらに、OPTION設定を特定の手順で変更すると、ポーズ中にカメラワークを変更できました。それまで2D対戦格闘しか触れてこなかった自分にとって、さまざまな視点からキャラクターを眺められるというのは驚きでした。
必殺技を出している最中や投げ技を決めた瞬間など、さまざまな状況で一時停止してグリグリとカメラを回したものです。「ここがカッコいい」「実はこの背景に……」などと友人とワイワイ騒ぎながらベストショットを探すのも楽しかったなあ。エリスを側転させて、すかさずポーズ。カメラアングルを変更して……などという思春期らしい遊び方をしたのも、今となってはいい思い出かな(笑)。

|
|---|

|
|---|
| ▲側転中のちょうど逆立ちしたところでポーズをかけるのがポイント。現代の3D対戦格闘と比べるとさすがに荒いビジュアルですが、当時は衝撃的でした。エリスの衣装が半透明になっているところとか、とてもきれいでした。 |
これだけシステム面で隠しコマンドの多い本作。先ほど少し触れましたが、各キャラクターにも秘伝必殺技2という隠し必殺技が用意されています。例えば主人公のエイジであれば、↑↓↑↓→←→←△+○というコマンドで強力な飛び道具を繰り出せます。普通に入力すると当然垂直ジャンプしてしまうので、側転中など他の行動で硬直している間にコマンド入力を行うなどの工夫をこらしたものです。
他にも、モンドの→/↑\←→\↓△+○やホー・ファイの×□△○←→←→△+○など、すさまじいコマンドが満載! 一応上記の隠しコマンドで他の必殺技同様にカンタンに繰り出せましたが、あえてコマンドで繰り出すことがちょっとしたステータスになったものです。

|
|---|
| ▲ホー・ファイを使用して上記のコマンドで繰り出せる技は、どうみてもオナラ。使い勝手もあまりいい技ではありませんが、試合中におもむろに繰り出すことが重要だったのです(笑)。 |
PS黎明期でありながら魅力的な要素を多数盛り込んでいた本作は、残念ながらゲームアーカイブスでの配信は行われていません。とは言え当時多くのユーザーが手にしたこともあって、その気になれば今から入手することは難しくはないでしょう。PSのゲームはPS3で遊べるので、ハード面の問題もほぼないかと思います。PSの対戦格闘史を彩る1本、気になる人は一度プレイしてみてください。シリーズ作もたくさん出ているので、もしご興味があればぜひ!
【周年連載 バックナンバー】
→第15回:PS『闘神伝』20周年記念。2Dと3Dの狭間から生まれた対戦格闘の魅力を振り返る【本記事】
→第14回:“背水の逆転劇”10周年記念。格闘ゲームプレイヤー以外にも知られる梅原大吾氏の名プレイ
→第13回:『ワイルドアームズ2』15周年記念。リメイクを待ち続ける“英雄”をテーマにした激熱RPG
→第12回:『スクウェアのトム・ソーヤ』25周年記念レビュー。敵がリセットを使う怪作を遊び直してみた
(C)TOMY CO.,LTD. 1995.
データ
- ▼『闘神伝』
- ■メーカー:タカラトミー
- ■対応機種:PS
- ■ジャンル:FTG
- ■配信日:1995年1月1日
- ■価格:5,800円(税込)